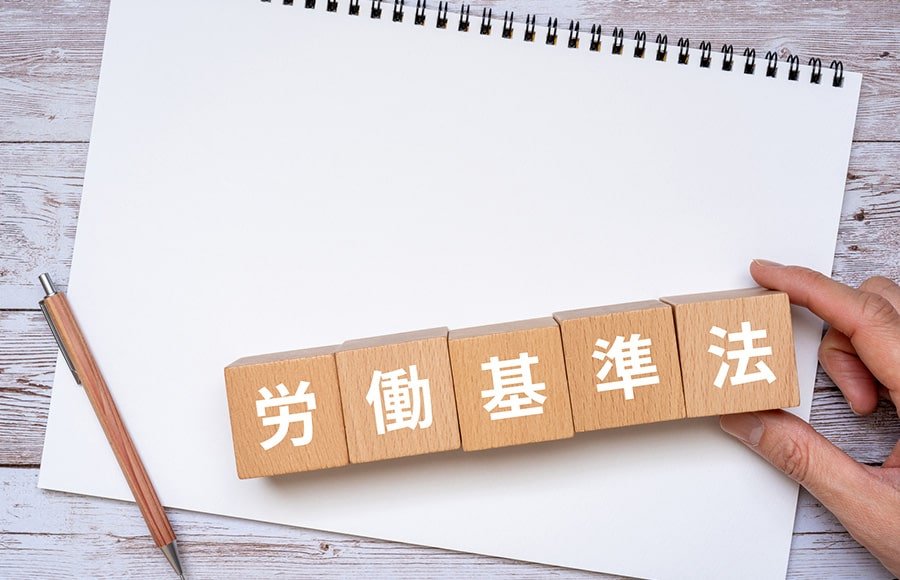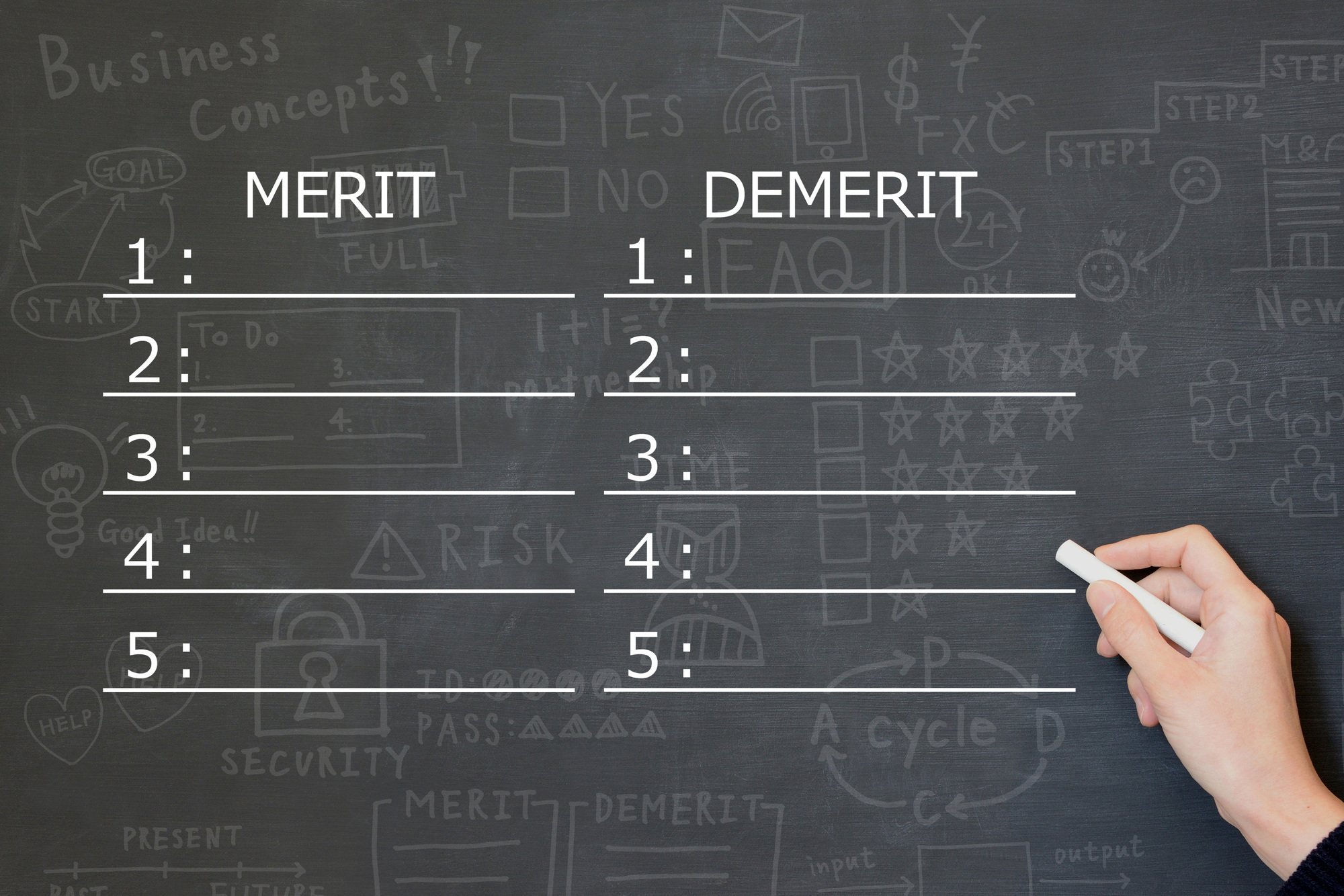【登録販売者】変形労働時間制をわかりやすく解説!薬局の求人などに多い働き方

こんにちは、登録販売者転職のアポプラス登販ナビライターチームです。
一般的には、働く時間の上限は労働基準法によって定められており、1日あたりや1週間あたりの労働時間は一定の時間に決められています。それに対し変形労働時間制とは、労働者と企業側で合意したうえで、忙しい時期には働く時間を長く、仕事の少ない時期には働く時間を短くする働き方です。
季節やイベントによる繁閑の差が激しい薬局やドラッグストアの求人には変形労働時間制が多いため、これらの職場で働くことを検討している人は、変形労働時間制の概要を知っておきたいところではないでしょうか。
本記事では、登録販売者として働く方が押さえておきたい変形労働時間制について、様々な視点からわかりやすく解説します。
目次
- ・登録販売者が覚えておきたい変形労働時間制の基礎知識
- ・変形労働時間制の対象期間
- ・変形労働時間制の残業の仕組み
- ・変形労働時間制のメリット
- ・変形労働時間制のデメリット
- ・変形労働時間制で登録販売者が注意したいこと
- ・まとめ|変形労働時間制でも働きやすい職場はある
登録販売者が覚えておきたい変形労働時間制の基礎知識

変形労働時間制の特徴は、業務の忙しさに合わせて労働時間をフレキシブルに調整できる点にあります。
たとえば、1カ月単位の変形労働時間制を導入している企業の場合、1カ月の労働時間が1日平均8時間×20日の160時間の基準を超えない限り、月末の忙しい時期には10時間働き、閑散期の月初は6時間に抑えるといった調整が可能です。
結果として、閑散期の待機時間を減らせるため、月間の残業時間の抑制につながり、従業員はメリハリのある働き方ができるようになります。企業にとっては、繁忙期に労働時間が1日8時間を超えていても所定労働時間となるため、残業代の発生を抑えることができるというメリットがあります。
しかし、ある一定期間の労働時間を調整する制度には、シフト制やフレックスタイム制、裁量労働制などがあり、違いがよくわからないという方もいるのではないでしょうか。
ここでは、登録販売者が覚えておきたい変形労働時間制の基礎知識として、とくにシフト制やフレックスタイム制、裁量労働制との違いについて解説します。
シフト制との違い
シフト制はコンビニや飲食店など、サービス業や小売業でよく採用されており、週ごとまたは月ごとに異なる勤務予定を組むという制度です。1週間や1カ月といった単位で勤務日や勤務時間帯が変動するため、変形労働時間制と同様の制度であると思われがちですが、両者の間には明確な違いがあります。
シフト制は確かに勤務時間や勤務日を希望によって変えられますが、1日あたりの労働時間上限は8時間(1週間あたり40時間)と法律によって定められており、それを超過する際には残業代が発生するのです。
一方で変形労働時間制では、対象期間全体の労働時間の上限を超えなければ、1日の労働時間が8時間を超えても残業代は発生しません。例えば対象期間が1カ月の場合には、その月の平均労働時間を週平均40時間以内にしなければなりません。対象期間は、1週間・1カ月・1年で設定可能です。
フレックスタイム制との違い
フレックスタイム制は、変形労働時間制の一形態ですが、労働時間の管理と調整方法が特徴的です。
フレックスタイム制では、通常「コアタイム」と呼ばれる労働が必須の時間帯を含んでいれば、日々の始業時間と終業時間を従業員が自由に決められます。
例えば、10時から15時がコアタイムとして設定されている場合、以下のように出勤時間と退勤時間を従業員の裁量で決定可能です。
- 出勤時間:7時、退勤時間:16時
- 出勤時間:10時、退勤時間:19時
フレックスタイム制では、清算期間(労働者が働く時間を調整できる期間)の平均労働時間が週40時間以内になるよう定めます。ただし清算期間が1カ月を超える場合、1カ月の労働時間が週平均50時間を超えてはならず、超えた場合には残業代が発生します。
フレックスタイム制は、従業員の都合に合わせて就業時間を設定しますが、変形労働時間制では繁忙期と閑散期の労働時間を、企業の都合に合わせて調整するという点が異なるとも考えられるでしょう。
裁量労働制との違い
裁量労働制は、実際に働いた時間ではなく、あらかじめ設定した時間を働いたとみなす制度を指します。「みなし労働制」という呼称でも知られるこの制度は、研究員やエンジニアなど、その日の目標や進捗によって必要労働時間が変動しやすい職種には好都合です。
例えば裁量労働制では、8時間のみなし労働時間で契約した場合、実際に何時間働いたかとは無関係に8時間分の給与が支払われます。つまり、ある日は12時間働いたけれど、翌日は4時間しか働かないということも可能です。
裁量労働制が「いつ、どれだけ働くか」を従業員が決められる制度であるのに対し、変形労働時間制は、企業が繁閑を考慮して労働時間を調整します。
変形労働時間制の対象期間

変形労働時間制の対象期間として、1週間単位、1カ月単位、1年単位があり、それぞれに特徴があります。ここでは、変形労働時間制の対象期間ごとに、その特色を見てみましょう。以下の表も参考にしてください。
| 制度 | 対象期間 | 労働時間制限 |
|---|---|---|
| 1週間単位の変形労働時間制 | 1週間以内 | ・1週間の労働時間が40時間以内 ・1日10時間以内 |
| 1カ月単位の変形労働時間制 | 1カ月以内 | ・1週間の労働時間平均が40時間以内 |
| 1年単位の変形労働時間制 | 1年以内 | ・1週間の労働時間平均が40時間以内 ・10時間/日、52時間/週が上限 |
1週間単位の変形労働時間制
労働基準法に基づき、1週間単位の変形労働時間制が認められるのは、常時使用する従業員数が30人未満の小売業・旅館・料理店・飲食店です。
この制度において、1週間単位でそれぞれの日の労働時間を柔軟に設定できますが、あらかじめ書面にて従業員に通知する義務があります。また、働ける時間は1日10時間、1週間40時間が上限です。
1カ月単位の変形労働時間制
1カ月単位の変形労働時間制とは、1カ月の間で1週間あたりの労働時間平均が40時間を超えないように調整する時間制を指します。1カ月の平均労働時間が週40時間以内を満たしていれば、1日8時間や週40時間の制限を超える労働時間を設定できる仕組みです。
例えば、ある薬局では月初に比較的来客が少ないものの、月末になると業務が忙しくなるものとします。この薬局の場合、月初の労働時間を短縮し、月末の労働時間を長くすることにより、1カ月を通して1週間あたりの平均労働時間が40時間になるように調整できます。
1年単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制の対象期間は1カ月以上1年以内で、その期間内で1週間あたりの労働時間平均が40時間以内であれば、特定の日に8時間(または週に40時間)を超える労働時間を設定可能です。また、1日の労働時間の上限は10時間、1週間の労働時間の上限は52時間と定められています。
変形労働時間制の対象が3カ月超になるのであれば、週48時間を超えてよいのは続けて3回が上限、加えて3カ月で合計3回まで、年間の労働日数は280日までです。
1年単位の変形労働時間制は、年間を通じて忙しい時期と暇な時期が明確な業種に向いており、繁忙期と閑散期の労働時間を調整し、年間の法定労働時間内に収まるようにする制度です。
変形労働時間制の残業の仕組み

変形労働時間制を採用しているとしても、それで残業代が発生しないわけではありません。定められた労働時間を超過した分は、通常と同様に残業という扱いになります。
変形労働時間制において、残業時間や残業代はどのように計算すればいいのでしょうか。ここからは、変形労働時間制の残業の仕組みについて解説します。
1週間単位の場合
1週間単位の変形労働時間制における残業は、1日単位と1週間単位の両方で考えなければなりません。1日単位で考える場合、設定された労働時間を超えたところから残業にカウントされるため、例えば9時間に設定した場合、10時間労働すれば1時間が残業になります。
週の法定労働時間は40時間であるため、週の労働時間が40時間を超えたところから残業にカウントされ、1日単位の残業代と別に週40時間を超過した分にも残業代がかかる点に注意が必要です。
1カ月単位の場合
1カ月単位の変形労働時間制を採用する場合、残業代のカウントに1カ月単位の考え方も加えなければなりません。
1日単位の残業代と1週間単位の残業代をカウントしたうえで、月単位の残業時間を加えます。月により暦の日数は異なるため、その月の日数に応じて残業代にカウントされる時間が変動するのが特徴です。例えば週の所定労働時間を50時間とした場合、月単位の残業は以下のようなタイミングで発生します。
- 28日までの月:160時間超
- 29日までの月:165.7時間超
- 30日までの月:171.4時間超
- 31日までの月:177.1時間超
1年単位の場合
1年単位の変形労働時間制を採る場合、年単位の所定労働時間と、それを超過した分の時間を考慮しなければなりません。
うるう年でない場合、年365日で計算した法定労働時間は2085.7時間、うるう年の年間日数366日では2091.4時間を超過したところから年単位の残業がカウントされます。
変形労働時間制のメリット

変形労働時間制の採用によって、企業と従業員にはどのような利益があるのでしょうか。
ここでは、変形労働時間制の具体的なメリットについて解説します。
労働時間を柔軟に調整できる
変形労働時間制を採用する大きなメリットとして、労働時間を柔軟に調整できる点が挙げられます。
例えば、登録販売者の業務では、インフルエンザの流行時期や特定のイベントなどにより繁閑に大きな差が生じます。そのような場合に1カ月単位の変形労働時間制を導入し、月初の閑散期には労働時間を短縮し、月末の繁忙期には労働時間を延長するといった使い方が可能です。
労働時間を柔軟に調整できることにより、無駄な残業代の発生を削減できる効果も期待できます。
健康面の管理がしやすい
変形労働時間制においては、従業員の健康管理がしやすいという点もメリットです。登録販売者は、シーズンごとに大きく業務量が変動するため、繁忙期には集中的に働く必要がありますが、閑散期にはゆっくりと心身の休養を図れます。
忙しい時期と暇な時期で労働時間を調整することにより、過労が続く状態を避けられ、従業員の心身にかかる負担を軽減または分散できます。
繁忙期に労働時間が延長する代わりに、閑散期には労働時間が短くなるため、次第に疲労やストレスが蓄積していく状況も避けやすくなるでしょう。
ワークライフバランスを取りやすい
変形労働時間制では、閑散期に週の労働時間を減らせるため、プライベートな時間を確保しやすくなります。登録販売者の業務はインフルエンザの流行や花粉症シーズンなど、繁閑に大きな差が出るため、変形労働時間制を活用することで効率よくリフレッシュできるでしょう。
従業員がワークライフバランスを取りやすいというのは、この制度の大きなメリットの一つです。従業員のワークライフバランスが整うことにより、企業全体の業務効率化にもよい影響を与えることが期待できます。
変形労働時間制のデメリット

変形労働時間制には多くのメリットがありますが、思わぬ弊害が生じることも想定されます。
ここでは、変形労働時間制におけるデメリットについて解説します。
想定以上の残業が発生する可能性がある
登録販売者は医薬品の販売や相談業務に従事するため、季節や特定のイベントにより業務量が左右されます。そのため、変形労働時間制を採用することで、忙しい時期に労働時間を延長し、そうでない時期には労働時間を短縮できますが、これが常に計画通りに機能するとは限りません。
業務の繁閑を慎重に判断し、計画的に労働時間の調整をおこなったとしても、イレギュラーは発生するものです。予期せず業務が大幅に増えてしまった場合には、想定以上の残業が発生する可能性があります。
労働時間にばらつきが生じやすい
変形労働時間制を採るのであれば、日ごとや週ごとの労働時間にばらつきが生じることは避けられません。しかし、労働時間にばらつきが生じることで、業務の遂行や健康管理に支障をきたすかもしれません。
時期による労働時間のばらつきが大きすぎると、生活リズムの乱れやストレスの原因にもなるため注意が必要です。
変形労働時間制で登録販売者が注意したいこと

想定外の残業発生や労働時間のばらつき以外にも、登録販売者が理解しておくべきことはあります。
ここからは、変形労働時間制において、登録販売者が注意しておくべきことを紹介します。
労働時間は繰り越せない
変形労働時間制では、それぞれの日における労働時間が独立して計算されるため、ある日の労働時間が所定労働時間を超過した場合に、それを他の日で調整できません。
例えば、1日9時間が所定労働時間であるとして、ある日に10時間働いたとします。この日の超過1時間分を、翌日の労働時間を8時間に短縮して調整はできません。そのため、1時間超過した分についてはその日の残業代として独立で計算されてしまうのです。
登録販売者のように、季節やイベントによる業務量の変動が大きい職種では、とくに計画的に労働時間を設定することが求められます。
残業代が正確に支払われているかチェックする
変形労働時間制を導入している企業に入社するなら、就業規則で所定労働時間を確認し、残業代が正確に支払われているか確認する必要があります。
変形労働時間制は企業にとって賃金計算が複雑で手間のかかる制度です。そのため、企業側のミスにより、所定労働時間を超過しているのにもかかわらず適切な残業代が支払われないという問題が発生する可能性もあります。
そもそも企業が定める所定労働時間が法定労働時間を超えていないか、所定労働時間を超えた労働時間の分の残業代が正しく支払われているかをチェックし、不備があったら企業に問い合わせましょう。
まとめ|変形労働時間制でも働きやすい職場はある
ドラッグストアはコンビニのように年中無休で長時間労働となる場合が多く、登録販売者の一人が退職してしまった際には、残った従業員がさらに長時間労働を強いられてしまうことがあります。開店から閉店までの通し労働や、土日の休みの取りにくさなどの状況も生じやすく厳しい職場に思えるかもしれません。
一方で、変形労働時間制を活用することで、繁忙期と閑散期でメリハリのある働き方ができ、仕事が少ない時期にも一定の給与が出るうえ休みが取りやすいという企業も存在します。
登録販売者として働きやすい環境を見つけるためには、就業規則や勤務条件をしっかりと確認し、働きやすい環境を整えている企業を判断することが大切です。
【新着】登録販売者のための業界コラム
- 2025年12月03日 【現役ドラッグストア店長直伝】冬商品で接客スキルを劇的に磨く3つのコツ
- 2025年11月21日 現役薬剤師が教える。登録販売者の新人教育マニュアル|OJTの進め方と後輩指導のコツ
- 2025年11月21日 現役薬剤師が伝授|インフルエンザ時に使える解熱剤の見分け方と登録販売者の声かけ技術
- 2025年11月06日 【2026年法改正で必須!】現役店長が教える「OD対策」現場対応完全ガイド 〜登録販売者が押さえるべき「3大変更点」と心構え〜<登録販売者のキャリア>
- 2025年10月30日 登録販売者はブランク後も復職できる!管理者要件と安心して働くためのポイント