登録販売者に必要な実務経験とは?期間や時間数など条件を解説
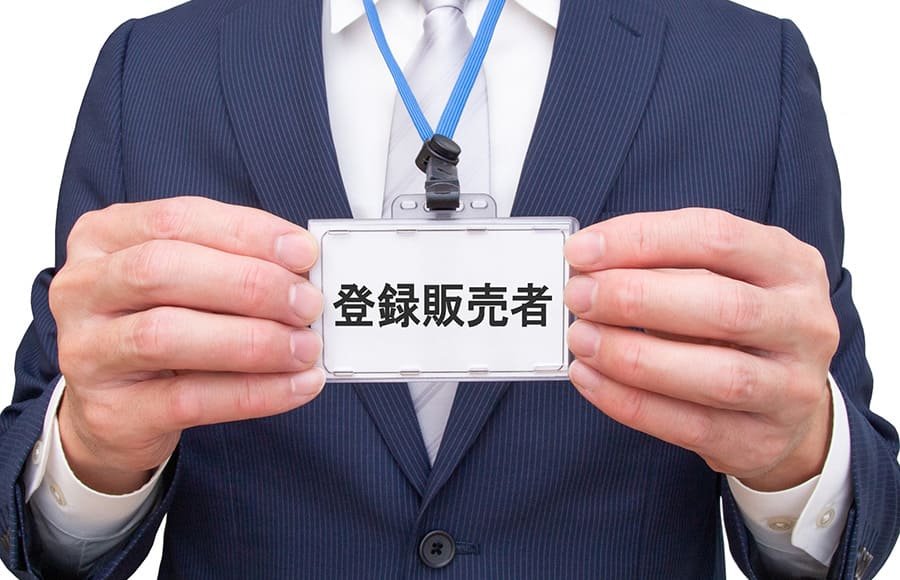
こんにちは、登録販売者転職のアポプラス登販ナビライターチームです。
登録販売者には実務経験が必要だと聞くものの、「詳しくはわからない」という方もいるでしょう。本記事では、登録販売者に必要な実務経験の期間・時間数などの条件を解説します。
目次
- ・登録販売者には実務経験が必要
- ・実務経験緩和が登録販売者に与える影響とは
- ・実務経験の証明として必要となる実務(業務)従事証明書
- ・登録販売者の実務経験と認定される実務の条件
- ・実務経験が必要な店舗管理者の仕事内容
- ・実務経験をクリアすると就職活動でも有利に
- ・まとめ|登録販売者になったら実務経験をクリアして店舗管理者になろう
登録販売者には実務経験が必要

登録販売者は、2014年度まで高校卒業以上でOTC(一般用医薬品)の販売経験が1年以上あることが受験資格でした。しかし、2014年に登録販売者制度の改定がおこなわれ、翌年の2015年の試験から受験資格が撤廃されました。そのため、2014年からは誰でも受験が可能となっています。
その一方で、登録販売者が1人で医薬品の販売をおこなうには、直近5年間のうち2年(累計1,920時間)以上の従事期間が必要となりました。この実務経験を積んでおかなければ、「研修中」扱いとなり実務経験を積んだ登録販売者、もしくは薬剤師の指導・管理の下でしかOTC(一般用医薬品)販売はおこなえません。
実務経験をクリアすると、1人でOTC(一般用医薬品)が販売できるようになるうえ、「店舗管理者」という、ドラッグストアや薬局の店舗における責任者にもなれます。
登録販売者試験を受ける前にドラッグストアや薬局に勤めており、2年(累計1,920時間)以上の実務経験を積んでいる場合は、試験に合格すればすぐに登録販売者の管理者として業務が可能です。
2023年に実務経験が緩和
登録販売者の実務経験は、昨年の2023年4月に改正省令が施行されて緩和されました。直近5年間のうち2年(累計1,920時間)以上の従事期間が必要だったものが、直近5年間のうち1年(累計1,920時間)以上の従事期間と、定められた機関の研修を受講した場合も認められるようになりました。
登録販売者の実務経験をクリアする方法は、以下の通りです。
- 直近5年間のうち従事期間が2年(累計1,920時間)以上
- 直近5年間のうち従事期間が1年(累計1,920時間)以上+継続的研修+追加的研修
- 直近5年間のうち従事期間が1年(累計1,920時間)以上+過去に店舗管理者または区域管理者として業務に従事したことがある。
これから実務経験を積む方は、研修を受けて1年に短縮するのが最短ルートになります。実務経験の緩和以前に1年以上2年未満(累計1,920時間以上)の実務経験を積んでいる場合は、追加的研修を受ければすぐに登録販売者の管理者として勤務が可能です。1年未満の場合は、それまでと合わせて累計1年、1,920時間以上の実務経験を積み、追加的研修を受けなければなりません。
参考:厚生労働省『「登録販売者に対する研修の実施要領」の一部改正について』
参考:登録販売者のキャリア支援アポプラスキャリア「登録販売者の追加的研修」
追加的研修とは?
今回新たに追加された追加的研修の一番の特徴は、講師と受講者の双方がやり取りできる形での研修であることです。研修自体は対面でもオンラインでも実施が可能ですが、録画配信ではなく、ライブ配信のような方法でおこなう必要があります。
研修の時間は合計6時間以上で、厚生労働大臣に届出をおこなった研修実施機関で実施します。
追加的研修の主な内容は、以下の通りです。
- 管理体制、法規、コンプライアンスなどの基本的知識にかかわる講義
- 販売現場、店舗などの管理に即したコミュニケーションにかかわる演習
- 上記を踏まえた、店舗管理者などに求められる対応についての事例研修
登録販売者の資格を持っている方であれば、従事した時間が1,920時間に満たなくても受講が可能で、研修を終えれば有効な修了証を発行できます。その後、従事期間が1年以上、累計1,920時間以上を超えた段階で、管理者要件を満たしたということになります。
実務経験緩和が登録販売者に与える影響とは

実務経験の年数が緩和されて、メリットを感じる方は多いでしょう。しかし、場合によってはデメリットが生じてしまうこともあります。ここからは、実務経験緩和が登録販売者に与えるメリットとデメリットについてみていきましょう。
実務経験緩和のメリット
実務経験が2年から1年に緩和されたため、今までよりも早く店舗管理者になれるようになりました。実務経験をクリアすると、1人でOTC(一般用医薬品)の販売ができるようになり、店舗管理者の立場にもなれるため、早期のキャリアアップにつながります。時給や給料があがり、転職もしやすくなるため、これから登録販売者として実務経験を積む方には、大きな利点となるでしょう。
実務経験緩和のデメリット
実務経験が緩和されたことにより、今までよりも大幅に競争相手が増える可能性があります。今までは、2年以上の従事期間が必要だったために、資格に対して壁を感じていた方も多かったでしょう。しかし、従事期間が半分の1年以上に緩和されたため、ハードルが低くなりました。
これから登録販売者資格にチャレンジする方や、資格を取得しただけだった方が、実務経験を積んで管理者要件を満たそうと考える場合も増えるでしょう。また、過去に店舗管理者として勤めていた方がまた実務経験を積もうとする可能性もあります。
実務経験を積んだ登録販売者が急増すると、採用における、管理者要件を満たしていることの相対的な価値が弱まってしまいます。そして、実務経験をある程度積んでいることが事実上の必須条件となってしまい、条件を満たしていない人が不利になってしまうかもしれません。
今までは実務経験を積んでいるという点だけで店舗管理者になれていた人や採用されていた人も、人格や資質、能力、知識量などにより選抜される場面が増えるでしょう。
実務経験の証明として必要となる実務(業務)従事証明書

実務経験を満たしている証明として、「実務(業務)従事証明書」が必要です。申請書は、各都道府県のホームページから入手可能です。実務(業務)従事証明書は、実務経験を積んだ企業に記入してもらいます。
記入は、現在勤めている企業だけでなく、直近5年で該当の職場があれば、過去の勤め先でも可能です。退職後であっても、実務(業務)従事証明書の申請をされた企業は、実務(業務)従事証明書を発行しなければなりません。
実務経験の計算方法
実務経験は、1カ月に80時間以上の薬事業務に従事した場合に認定されます。また、登録販売者試験の合格前は、同一月に同一店舗で80時間以上の薬事業務に従事した場合に限ります。一方、登録販売者の場合は、同一月に複数の店舗の累計が80時間以上であれば実務経験として認められています。
そのため、実務経験として必要となる1年以上とは月80時間以上を12カ月以上、2年以上とは月80時間以上を24カ月以上の1,920時間の従事期間を指します。
登録販売者の実務経験と認定される実務の条件

登録販売者試験に合格した後、実務経験が一切ない場合は、まず勤める店舗がある都道府県に登録申請をおこないます。その後は「研修中」として、実務経験を積んだ登録販売者か薬剤師の指導・管理の下で実務経験を積まなければなりません。
しかし、登録販売者として実務経験を積んでいたつもりが、実際は認定されていなかったというケースもあります。効率よく実務経験を積むためにも、登録販売者の実務経験と認定される実務の条件についてみていきましょう。
パートやアルバイトでも実務経験になる?
登録販売者の実務経験は、パートやアルバイトなどにかかわらず誰でも積めます。主婦や学生でも直近5年間で2年(1,920時間)以上の従事期間または1年(1,920時間)以上の従事期間と指定の研修を受講すれば、実務経験と認定されます。また、直近5年以内なら連続している必要はありません。
実務経験として認定されないケースは?
OTC(一般用医薬品)を取り扱っている店舗で働いていても、実際の業務内容によっては実務経験として認定してもらえない可能性があります。
たとえば、医薬品のほかに雑貨や化粧品、食料品も扱っているドラッグストアで勤務しているとします。医薬品に対応するスタッフは足りていたため、実際の仕事は食料品と雑貨の補充ばかりだった場合は、実務経験として認められません。
また、ドラッグストアだけでなく調剤薬局でも実務経験を積むことは可能ですが、OTC(一般用医薬品)はほぼなく、医療用医薬品ばかりを取り扱っている場合は、実務経験として認定されません。
認定される業務は職場や都道府県によっても異なるため、就職前に薬務課や職場に問い合わせて、実際の担当業務が実務経験として認定してもらえるものか確認しておくことが必要です。
| 登販ナビ 注目の人気急上昇ランキング |
|---|
| 【2025年発表】登録販売者必見!ドラッグストアホワイト企業ランキング |
| 登録販売者の転職はエージェントにお任せ!おすすめ転職サイトをご紹介 |
| 【大手5社比較】女性登録販売者が働きやすいドラッグストアはどこ?各社の制度や実績を徹底比較! |
| 登録販売者の転職は40代でも可能!採用される人の特徴とは |
| 登録販売者の管理者要件が実務経験1年以上に!追加研修が必要? |
実務経験が必要な店舗管理者の仕事内容

登録販売者の資格を取得しても、実務経験がなければ「研修中」扱いとなり、実務経験を積んだ登録販売者もしくは薬剤師の指導・管理の下でしかOTC(一般用医薬品)を販売できません。実務経験をクリアすることで初めて「一人前」となり、1人でOTC(一般用医薬品)が販売できるようになります。
また、実務経験を積んで管理者要件を満たした登録販売者は、店舗管理者という立場になれます。店舗管理者となった登録販売者の仕事内容は、「OTC(一般用医薬品)の販売」と「店舗運営に関する業務」です。
OTC(一般用医薬品)は、「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」と分類されています。「第1類医薬品」は、服用する際に副作用や相互作用にとくに注意しなければならず、薬剤師がいる店舗でなければ販売がおこなえません。
一方で、「第2類医薬品」と「第3類医薬品」は登録販売者でも販売が可能です。そして販売の際のカウンセリング業務もおこないます。
登録販売者が販売可能な「第2類医薬品」と「第3類医薬品」は、ドラッグストアや薬局で扱うOTC(一般用医薬品)の約9割を占めています。そのため、登録販売者はほとんどのOTC(一般用医薬品)の販売とカウンセリング業務をおこなえます。OTC(一般用医薬品)の販売は、店舗管理者ではない登録販売者もおこなう業務です。
店舗管理者だけがおこなう業務が「店舗運営に関する業務」です。店舗管理者になるとOTC(一般用医薬品)の販売業務だけでなく、「ヒト、モノ、カネ」の管理をしなければなりません。シフト管理や在庫管理、売上管理などの店舗運営の業務をおこないます。
実務経験をクリアすると就職活動でも有利に

OTC(一般用医薬品)を扱うドラッグストアや薬局では、必ず実務経験をクリアした「店舗管理者」を配置しなければなりません。店舗管理者が1人でもいれば店舗運営ができますが、実務経験をクリアしていない研修中の登録販売者だけでは、店舗運営はおこなえません。
そのため、転職活動や就職活動をする際に実務経験をクリアしていれば、研修中の登録販売者よりも有利になります。ドラッグストアや薬局以外のコンビニやスーパー、ホームセンターでは、登録販売者の配置が少ない傾向にあるため、実務経験を積んだ登録販売者がとくに優先されるでしょう。
また、ドラッグストアの店長は、店舗管理者を兼任している登録販売者が多くいます。実務経験をクリアしていると店長への昇格の近道にもなります。
まとめ|登録販売者になったら実務経験をクリアして店舗管理者になろう
登録販売者の管理者要件を満たすには、実務経験が最短でも1年は必要であり、月に80時間以上の薬事業務が必要です。しかし、実務経験を積み店舗管理者になると、給料や時給があがるなどメリットが多くあります。
就職活動や転職活動にも有利に働き、将来店長も目指しやすいでしょう。登録販売者を取得した際は、実務経験を積んで店舗管理者となり効率よく働きましょう。
アポプラス登販ナビでは、登録販売者専用の転職をサポートしてくれます。転職を検討の方は、アポプラス登販ナビを活用して転職活動をスムーズにおこないましょう。
【新着】登録販売者のための業界コラム
- 2026年01月27日 登録販売者必見!疲労を感じるお客さまへのサプリの接客と受診勧奨
- 2026年01月09日 【現役ドラッグストア店長直伝】登録販売者が「辞めたい」と思わない3つのメンタル維持法(2026年対策付き)
- 2026年01月07日 2026年ドラッグストア業界の未来図|市場動向・M&A・登録販売者のキャリアと転職のポイント
- 2026年01月07日 登録販売者の年収は低い?現場にインタビューしてリアルな声をお届け!平均給料を調査
- 2026年01月07日 ドラッグストア店長の年収はいくら?平均額の内訳と600万円を目指す昇給のコツ







