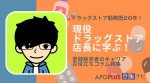【2026年法改正で必須!】現役店長が教える「OD対策」現場対応完全ガイド 〜登録販売者が押さえるべき「3大変更点」と心構え〜<登録販売者のキャリア>

今年2025年、ドラッグストアをはじめとする医薬品販売において大きな変化につながる改正案が示され、来年2026年からの施行が予定されています。
「法律のことはよく分からない」「そんなに大きく変わらないでしょ?」と考えている登録販売者も多いのですが、実は根本的な変化が起こるので全員が前提から理解しておかないといけないのです。
店舗や薬局の開局、薬の販売に関する事項など多岐にわたっていますが、今回は登録販売者が把握しておくべきことを解説します。 多くの情報が飛び込んできてよく分からなくなってしまっている方も多いと思うので、今回は「新ルールの現場対応術」を解説します。
「お客さまにどう説明すればクレームにならない?」「具体的に何をすればいい?」こうした現場の疑問を解消するために、なぜルールが変わるのか、そして明日からどう動けばいいのか、具体的な対応術を理由からしっかり解説します。
【この記事で得られること】
- なぜOD対策が「努力義務」から「法律(罰則あり)」に変わるのか、その背景
- 登録販売者が現場で対応すべき「3つの新ルール」(18歳未満・陳列・記録)
- クレームを回避し、自分を守るための「接客マインド」と「声かけテンプレート」
目次
- ●なぜ「努力義務」から「罰則ありの法律」へ? 登録販売者が知るべき法改正の背景
- ●2026年法改正で"ここが変わる"!登録販売者が押さえたい3つの現場ルール
- ●「クレーム」と「罰則」から自分を守る!法改正対応の接客マインドとテンプレート
- ●法改正を"チャンス"に変える!登録販売者のための「未来型」接客テンプレート
なぜ「努力義務」から「罰則ありの法律」へ? 登録販売者が知るべき法改正の背景

まず前提として、われわれ登録販売者が関係してくる部分の前提が「省令」から「法律」に変わっているのです。
これがどんな意味を持っているのか、なぜ変わったのか見ていきましょう。
ルールが守られるようになってきたのになぜ法律が変わるの?
なぜ国は、これまでのルールをより厳しい「法律」に変えることにしたのでしょうか。 実は以前はルールが守られていない店舗が多かったのですが、最近は現場の努力でかなり改善されているのです。
それでも法律にするのには理由があるのです。
厚生労働省は、薬局やドラッグストアでの医薬品販売ルールが守られているかを調べるため、調査員がお客さまを装って店舗を訪問し、現場の対応が適正かどうかをチェックする定期的な覆面調査を行っています。 これは「医薬品販売制度実態把握調査」というもので、厚生労働省のホームページなどで結果が公表されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62122.htmlここには調査員が「濫用等のおそれのある医薬品」を購入しようとした際に、資格者(薬剤師または登録販売者)からどのような対応を受けたか...というデータが掲載されています。
これによると「濫用等のおそれのある医薬品」を複数個購入しようとしても9割の店舗では購入できなかったとのことです。
年々この数値は改善されているのですが、なぜ更に厳しくなるのでしょうか。
それは報道されている通り「オーバードーズ」が社会問題となっていることがあげられます。
特に若年層に関しては55人に1人はオーバードーズに陥っているという報道もありました。
販売に関して改善している一方で、残りのおよそ1割の店舗では、まだ不適切な販売が行われているという実態があります。
このため「若者の乱用問題が続いていること」が、国が法律を厳しくする直接の理由なのです。
ルールをより強制力のあるものに変える目的は、例外なくすべてのお店にルールを守らせるためなのです。
法改正の背景
そもそも「省令」と「法律」では何が違うのでしょう。
現在は省令で「濫用等のおそれのある医薬品」が規定されていますが、これが法律になるとどうなるのでしょうか。
これまでの「濫用等のおそれのある医薬品」のルールは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則」という、いわゆる「省令」に基づいていました。
これは厚生労働省など各省庁が決めるルールであり、薬機法という法律そのものではないのです。
つまり現場での扱いは「努力義務」であり、覆面調査でルールを遵守していなくてもすぐに直接的な罰則が科されることはなかったのです。 しかし、来年2026年から施行される改正は根本的に違い、薬機法という「法律」そのものの改正なのです。
この改正によりオーバードーズ対策は、「努力義務」から「法的義務」へと変わります。
私たち登録販売者にとって何を意味するのかといえば、「罰則の有無」と「責任の重さ」となります。
いままでの「省令違反」は、あくまで指導の対象だったのが、「法律違反」となり明確な「罰則」の対象となるのです。
ただしここでの罰則等は登録販売者個人ではなく「店舗や会社」が対象となります。
これは「企業マニュアルがより一層厳しくなる」ということです。
ただ現在のルールと手順から大きく変化するのではなく、より厳しくなるということですので、現在のルールに沿って業務をしている方は問題ありません。
「知らなかった」「忙しくてできなかった」「うっかりしていた」は、もう一切通用しないため、今一度確認を含めて新ルールを学んでおきましょう。
法令順守の絶対的な優先順位とは?
とはいえレジも混んでいるし... 納品も前出しも棚替えもあるし...
店舗で勤務する登録販売者は多忙を極めているので「ルールを守らない(簡略化する)」方の気持ちもわかります。
ただ例えば急いでいるからとタクシー運転手に伝えたとして、信号無視やスピード違反をするでしょうか?
もちろんしません。
お客さまの強い要望でも、法律を破れば、罰則の責任はすべて運転手が負うことになるからです。
そしてそれが重大な事故につながる可能性があることを、プロの運転手として知っているからです。
登録販売者も、これとまったく同じです。
「急いでいるから」「いつも買っている」というお客さまの都合と、「法律を守ること」は、まったく別の問題として切り離して考えなくてはなりません。
私たちの優先順位は「法律>会社マニュアル>従業員やお客さまの都合」です。
「こんなことを聞いて迷惑かもしれない」「どうせODする人は他店でも買うから意味がない」といった意見も耳にしますが、それこそが販売者目線の思考であり明確な論点ずらしです。
法律やマニュアルはお客さまの健康を守るためであると同時に、万が一のトラブルからわたし達登録販売者を守るための防具でもあるのです。
「忙しいから」「面倒だから」と、無防備で戦場に出るようなもので、そして罰則もあるということを忘れないでください。
2026年法改正で"ここが変わる"!登録販売者が押さえたい3つの現場ルール

では、ここからは今回の変更点を現場で働く登録販売者目線で見ていきましょう。
現状との違いを意識して覚えてください。
変更1 18歳未満への規制強化(販売数量の制限・年齢氏名確認)
今回の法改正で最も現場での対応が必要になるのが「18歳未満への対応」です。
今までは省令で努力義務でしたが、新ルールではこれが法律で義務化されます。
改正案では、18歳未満の者に対しては厚生労働大臣が定める適正な使用のために必要と認められる数量を超える販売が禁止されます。
改正案では年齢の確認が求められ、さらに18歳未満である場合は氏名の確認も必要となります。
そのため今までのような口頭確認ではなく、現場では「身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、学生証など)の提示」を求め、確実に年齢と氏名を確認する必要があります。
もちろん、明らかに18歳以上と判断できるお客さまに身分証を求める必要はありませんが、特に若く見える場合は確認しなくてはなりません。
これはお客さまを疑うということではなく法律で定められた手続きです。
若年層への安易な販売を防ぐゲートキーパーとして、私たち登録販売者が法的に負うことになった責任でもあります。
変更2 陳列義務化(鍵付き or カウンター越し/空箱)
皆さんの店舗では今「濫用等のおそれのある医薬品」はどこに陳列されていますか?
これまでは省令で「情報提供カウンターから1.2メートル以内」といった努力義務の基準がありましたが、改正案ではこの陳列方法も規制され「購入者が容易に手に取れない場所」への陳列が義務化されます。
現場での具体的な対応は、主に以下の2パターンです。
- 鍵のかかる陳列設備(いわゆる毒薬・劇薬庫のようなケース)に入れる
- 購入希望者が直接触れられない陳列(カウンターの内側など)にする
ほぼ全ての店舗で「空箱対応」となると想定されるため万引き対応を兼ねて実行することになります。
この点は店舗従業員全てが把握しないと納品陳列時の「うっかりミス」が違法になりかねません。
大変危険ですので全従業員への周知徹底をおこなう必要があります。
変更3 新名称「指定濫用防止医薬品」と確認義務の強化
これまでの「濫用等のおそれのある医薬品」という名称も「指定濫用防止医薬品」に変更となります。
そして重要なのが「記録義務」です。
- 購入者への確認に関する手順(年齢、18歳未満の場合は氏名、他店での購入状況、適正数量を超える理由など)
- 情報提供に関する手順(乱用リスクの説明、購入者の理解度確認など)
- 販売方法や陳列に関する手順
- 適正使用ではないおそれ(頻回・多量購入など)への対応手順
現状の店舗状況でこの手順通りにできるか不透明ではありますが、これが「法律を遵守した証拠」となるので各企業はマニュアル改正をおこなうと考えています。
登録販売者の業務内容が変わってくる可能性もあります。
「確認義務」と「手順書の整備」は登録販売者自身を守る防具でもあります。
面倒な雑務が増えたと捉えるのではなく、法律違反と問われないためにも自分自身を守る最も重要な「防具」として活用するべきです。
「クレーム」と「罰則」から自分を守る!法改正対応の接客マインドとテンプレート

ではここからは実際の接客時の考え方を再確認しておきましょう。
「お客さま」と「登録販売者自身」を守る方法です。
クレーム回避の鍵は
登録販売者として最も気になるのはやはり「お客さまからのクレーム」でしょう。
クレームが起こる最大の原因は、お客さまが「なぜこんな面倒な確認をされるんだ?」と不満に思うことにあります。
しかし「急いでいるのにこんなことを聞いて迷惑かも...」「棚替えで忙しいのに...」などと考えてしまうのは、販売者目線の思考です。
おどおどした態度で声かけをしてしまうとお客さまに不信感を与えてしまい、クレームに発展してしまうのです。
クレームを回避する最大の鍵は、今までと変わりません。
「確認は法律で決められたルールです」と、堂々と、毅然とした対応をおこなうことです。
2026年からの新ルールでは、この「盾」がより強力になります。
これからは「法律の改正により、すべてのお客さまに確認することが義務付けられました」と、誰に対しても公平な「法律」を理由にできるのです。
全ての店舗で実行できれば全てのお客さまにとって「当たり前」となり、最も有効なクレーム回避策となるのです。
論点ずらしに惑わされてはいけない
店舗やネットでは必ずと言っていいほど出てくる意見があります。
「本当にODしたい人は複数のお店を回ったりするだけだから意味がない」
「確認したところで販売するなら、業務が増えるだけだ」
これは典型的な論点ずらしです。
「ルールを守っても防げないかもしれない」ことと「ルールを守らなくていい」ことは、まったく別の話だからです。
法律は専門家として守るべき最低限のラインであり、法律や会社のマニュアルを遵守することは、万が一のトラブルから「自分自身を守るための最強の盾と鎧」でもあります。
「忙しいから」「面倒だから」「意味がないと思うから」という自分勝手な判断でその盾と鎧を脱ぎ捨てるのは、無防備で戦場に出るのと同じです。
2026年からは、その「無防備な違反」に対して、会社(店舗)に行政処分という明確なペナルティが科されます。
「意味がない」という無責任な論点ずらしに惑わされず、法律を遵守することが、結果としてお客さまと自分自身、そして会社のすべてを守る唯一の方法だと理解しましょう。
ここまでの内容を踏まえ、現場から寄せられそうな具体的な質問に回答します。
Q. 法律違反になったら、登録販売者個人が罰せられますか?
A.罰せられることは考えにくいですが、社内での懲罰はあり得ます。
解説した通り、薬機法違反による罰則(業務停止命令や罰金など)の対象は資格者個人ではなく「店舗の開設者(会社・店舗)」と考えられます。
ただしこれは「個人に責任がない」という意味ではありません。
所属する会社が行政処分を受ければ、会社の就業規則に基づく懲戒処分の対象になる可能性は十分にあります。自分と会社、両方を守るために法律を遵守してください。
Q. 明らかに成人の方にも身分証の提示を求めるべきですか?
A.必要はないと思われます。
法律の趣旨は「若年層の乱用防止」のため、現段階では明らかに18歳以上と判断できるお客さまに対して身分証の提示を求める必要はないと考えられます。
10代後半から20代前半に見えるなど、年齢確認に迷う場合に「法律で義務化されましたので」と理由を添えて、丁寧にご提示をお願いする運用が現実的です。
法改正を"チャンス"に変える!登録販売者のための「未来型」接客テンプレート
では最後に、2026年の法改正に対応した、新しい接客テンプレートを紹介します。 わたしの店舗では資格者全員がこの流れで対応することを徹底しているので、クレームなどは発生していませんし、登録販売者以外の従業員も法令順守意識は高いと感じています。
「未来型」接客テンプレートのステップと接客トーク例
| ステップ | 項目 | 接客トーク例 | 補足事項 |
|---|---|---|---|
| ①法律(義務化)の告知 | 法律による確認の義務化の告知 | 「こちらのお薬は『指定濫用防止医薬品』に指定されており、2026年から法律で確認が義務付けられました。大変恐れ入りますが、いくつかご質問よろしいでしょうか?」 | 確認の必要性を説明し、協力を依頼する。 |
| ②年齢確認 | 年齢確認 | 「法律に基づき、年齢確認をさせていただいています。お客さまは18歳以上でしょうか?」 | 法令に基づくものであることを伝える |
| (18歳未満と思われる場合) | 「法律に基づき、年齢確認のため身分証明書のご提示をお願いしております」 | 身分証明証の提示を求める。 | |
| ③状況確認 | 重複購入の確認 | 「同じような市販薬(咳止め・風邪薬・鼻炎薬など成分によってお聞きする)を他の店舗やインターネットで購入されていませんか?」 | 乱用防止のため、他の場所での購入状況を確認する。 |
| ④禁忌確認 | 持病の有無 | 「こちらのお薬は『高血圧・糖尿病』などの持病の方は『使用禁止』となっています。持病はございませんか?」 | 成分や禁忌の種類によっては冒頭で確認する。 |
| 運転の有無 | 「このお薬は服用後に眠気や注意力低下(成分によっては「眩しさ」)の副作用があるため『自動車運転』が禁止となっています。道交法違反にもなりますが運転はされませんか?」 | 副作用と運転禁止の関係、道路交通法違反の可能性を伝える |
むしろ「濫用による依存リスク」より「持病」「運転」の方が高リスクの場合が多いため、この確認は非常に有効です。
「のどの痛み」だけで総合感冒薬を使う高血圧をお持ちのお客さまや、自動車通勤をする季節性アレルギー鼻炎のお客さまなど、ここで登録販売者が依存以外の「ゲートキーパー」として活躍できるのです。
来年の新ルールスタートまでまだ時間がありますし、新ルールの微調整も入るかと思います。
ただこの新ルールは登録販売者にとって活躍の場が広がるチャンスでもあるため、前向きに捉えてスキルアップを目指してください!

執筆者:ケイタ店長(登録販売者)
ドラッグストア勤務歴20年、一部上場企業2社で合計15年の店長経験を活かし、X(旧Twitter)などで登録販売者へのアドバイスや一般の方への生活改善情報の発信を行っている。X(旧Twitter)フォロワー数約5,000人。
【新着】登録販売者のための業界コラム
- 2026年01月09日 【現役ドラッグストア店長直伝】登録販売者が「辞めたい」と思わない3つのメンタル維持法(2026年対策付き)
- 2026年01月07日 2026年ドラッグストア業界の未来図|市場動向・M&A・登録販売者のキャリアと転職のポイント
- 2026年01月07日 登録販売者の年収は低い?現場にインタビューしてリアルな声をお届け!平均給料を調査
- 2026年01月07日 ドラッグストア店長の年収はいくら?平均額の内訳と600万円を目指す昇給のコツ
- 2025年12月03日 【現役ドラッグストア店長直伝】冬商品で接客スキルを劇的に磨く3つのコツ