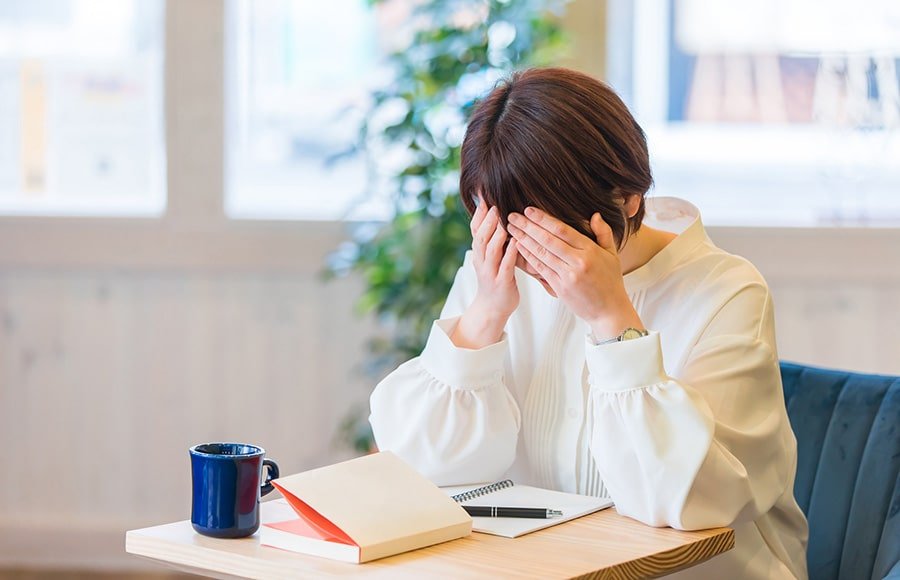【現場で使える!漢方】登販向け:葛根湯だけじゃない!風邪の引きはじめにおすすめの漢方薬リスト

感染症が気になる季節ですね。
店頭でも風邪のご相談が増える時期ではないでしょうか。
ここで、質問です!
風邪の引きはじめ、と聞くとどんなOTC(一般用医薬品)が頭の中に浮かびますか?
...多くの方が反射的に葛根湯を思い浮かべたのではないでしょうか。
決して間違いではありませんが、風邪の引きはじめのすべてのケースで葛根湯が適するわけではありません。
今回のコラムでは、風邪の初期に確認すべきことや対処法の見極め方、状態に適した漢方薬を紹介しています。
風邪の引きはじめといえば「葛根湯」しか思い浮かばない状態から一歩進んで、お客さまからの「風邪かな...?」という相談に、細やかに対処できるよう接客スキルをブラッシュアップしましょう!
- ●扱う漢方
- 銀翹散(ぎんぎょうさん)
- 麻黄湯(まおうとう)
- 葛根湯(かっこんとう)
- 桂枝湯(けいしとう)
- 香蘇散(こうそさん)
目次
風邪の引きはじめのお客さまへ、確認すべきこと

風邪の引きはじめに確認すべきは【寒熱】です。
漢方の考え方、特に急性期の症状の場合は病邪(病気の邪気)の性質をしっかりと把握することが大切です。
病邪が、体に熱をあげる性質を持つのか、体を冷やす性質を持つのかを判別しますが、これが寒熱の判断です。
- 熱の邪気に侵されているのか⇒ 赤い風邪
- 寒い邪気に侵されているのか⇒ 青い風邪
お客さま自身が漢方薬と風邪薬を持参されるような場面があるかと思いますが、適切なセレクトなのか登録販売者が判断する必要があります。体調の悪さを強く訴えられると慌ててしまうかもしませんが、「寒熱」を把握するだけで初動での対処の精度が格段にあがります。
登録販売者が理解しておきたい風邪の初期の寒熱

赤い風邪について(熱)
熱の邪気に侵されている場合、赤い風邪といいますが、その特徴は
- 既に熱っぽさがある
- 喉の痛みなど炎症症状がある
など、赤いイメージで捉えられると思います。
この場合は「冷ます漢方」を使用して、熱の邪気を追い返し、風邪の進行を食い止めることが大切です。
お客さまのなかには、少し熱っぽかったり、少し喉が痛かったりする状態で、風邪の引きはじめだから、と葛根湯を服用してしまう方が多くいらっしゃいます。
熱っぽい、喉が痛い、という赤い症状に対して更に温める漢方を使用してしまうと、症状が悪化してしまうことすらあります。
このような赤い風邪の引きはじめに使用するのが銀翹散(ぎんぎょうさん)です。その特徴と使い方を見ていきましょう。
銀翹散
耳慣れない漢方かもしれませんが、清熱解毒の生薬を含むため、風邪の引きはじめの熱っぽさや喉の痛みに最適です。
以前は漢方薬局などの専門店でないと手に入りにくい漢方でしたが、現在は店頭でお取り扱いがあるドラッグストアが多く見られます。
これにより、なかなか難しかった赤い風邪の初期の対処がしやすくなりました。
風邪の引きはじめの赤い症状には銀翹散がおすすめです。
青い風邪について(寒)
寒い邪気に侵されている場合、青い風邪といいますが、その特徴は
- 寒気や悪寒があり熱っぽさがない
- 水っぽいサラサラの鼻水が出る
など青いイメージで捉えられると思います。
この場合は「温める漢方」を使用して寒い邪気を追い返し風邪の進行を食い止めることが大切です。
ゾクゾク寒気のある初期の青い風邪の状態は長くは続きません。
タイミングを逃すと発熱やのどの痛みといった赤い症状に進行することがありますので、この場合は赤い風邪に対する漢方に切り替えましょう。
温める漢方の仲間
- 麻黄湯(まおうとう)
- 葛根湯(かっこんとう)
- 桂枝湯(けいしとう)
- 香蘇散(こうそさん)
など
温める漢方は、その発散性によって、身体をあたため発汗させ、体表にいる寒気を追い出すイメージです。まずは大まかにその発散性の強さが
- 麻黄湯 > 葛根湯 > 桂枝湯 > 香蘇散
と理解してください。
そのうえで具体的にそれぞれの使い分けを見ていきましょう。
麻黄湯
しっかりした発散性がある漢方なので、身体が頑丈で体力のしっかりある方、または、寒気や悪寒が極端に強いという点がポイントです。
実際にはインフルエンザなど、強い感染がある際の激しい悪寒があるときに使われることが多い漢方です。
麻黄という生薬は、エフェドリン作用により胃腸に負担をかけたり、就寝する前に服用すると寝付きづらさを感じてしまうことがありますので注意しましょう。
葛根湯
もっとも有名な葛根湯は、麻黄湯よりも発散性がマイルドです。寒気があるときの第一選択となりますが、判断のポイントは汗をかいていないことです。
汗がすでに出ている場合は、発汗をさせすぎてしまう可能性がありますので、後述の桂枝湯を検討します。
麻黄湯よりはマイルド、とはいえ麻黄+桂枝のしっかり発散する生薬が含まれていますので極端に虚弱な方や胃腸が弱い方は桂枝湯や香蘇散を選択します。
麻黄を含みますので麻黄湯同様、エフェドリンの影響を考慮する必要があります。
桂枝湯
桂枝湯は葛根湯から桂枝と麻黄を除いた漢方です。
使用を判断するポイントは、すでに発汗があることです。
葛根湯よりも発散性が弱めてあるので、すでに発汗が始まっている人を発汗させすぎない特長があります。
桂枝湯が当てはまる人は、すでに発汗している人のほか、虚弱で汗腺を閉める力も弱く、汗をだらだらかきやすい人も含まれます。
葛根湯で発汗ができたけれどもまだ寒気が抜けない、という場合、桂枝湯に切り替えていくこともあります。
香蘇散
桂枝湯よりもさらに虚弱な方や配慮が必要な方に使用します。
具体的には、胃腸が非常にデリケートな方や妊婦さん、高齢の方など、発散による負担を考慮すべき場合に選択する漢方なので、提案頻度はあまり多くないかもしれません。
葛根湯と解熱剤の併用について

ここでは、お客さまからよくいただく「葛根湯と風邪薬の併用は可能ですか?」というご質問について考えてみましょう。
これまでの内容を踏まえると、その違和感に気づけるのではないでしょうか。
風邪薬は解熱剤が入ります。
熱を下げたい風邪薬と、身体を温めたい葛根湯、狙いたい効果が真逆のものを組み合わせてしまっていますよね。
併用できるか否かの前に、患者さんの体調回復に意味のある事かどうかをまず考えてみるとよいと思います。
風邪薬を服用したいような、発熱やのどの痛みなど赤い症状が出ている場合は、葛根湯を使用できる時期が過ぎているかもしれません。
風邪薬の中に葛根湯成分が入るものがありますので併用自体ができない、という事ではありませんが、このような背景を理解して対応しましょう。
漢方も肝臓に負担をかけますので、あれもこれも服用することはおすすめしません。
寒気のある風邪の初期に、葛根湯・風邪薬両方を購入し、まず葛根湯を服用。それでも寒気から発熱症状へと、青い風邪から赤い風邪に進行してしまった際に風邪薬を使ってください、というご案内でもいいかもしれません。
寒気もない、というときに予防として葛根湯をだらだら服用することも、本来の葛根湯の「体を温め寒い邪気を追い出す」という目的と異なってしまいます。
また、葛根湯には発汗を促すための発散性の強い生薬が含まれますので、症状がない中、予防として長期服用することはおすすめしません。
まとめ
今回は、風邪の引きはじめの漢方についてお伝えしました。
風邪の引きはじめといえば「葛根湯」しか浮かばない、という状況から、一歩前進できましたでしょうか。
お客さまから「葛根湯をください。」と言われた場合も、お客さまが「風邪の引きはじめ=葛根湯」と思い込んでいるだけで、実際の証と合わない可能性もあります。
ここでしっかり現状をお伺いし適切な提案ができると、お客さまの喜びにつながります。
まずは、みなさん自身で風邪の引きはじめの適切な対処により進行を食い止める、という成功体験をしてみてくださいね。

執筆者:猪子英恵(いのこ はなえ)
薬剤師・国際中医専門員
臨床漢方カウンセリング協会理事
神奈川ME-BYOスタイルアンバサダー
集英社LEEキャラクター
首都圏を中心に全国の医療機関で漢方外来を受託。
「現場で使える」漢方とカウンセリングスキルの講座を
薬剤師・登録販売者に向けて開催。
臨床漢方カウンセリング協会
- 【執筆、監修など】
-
- わかさ出版ムック本 ハトムギ水 執筆、監修
- セントラルメディエンスコミュニケーションズ出版 月刊雑誌「からだにいいこと」2020年1月号 ハトムギ美容記事 執筆、監修
- 株式会社ハルメクホールディングス出版 月刊雑誌「ハルメク」2021年1月号ハトムギ美容記事 監修
- 第一三共ヘルスケアダイレクト株式会社 化粧品「RICE FORCE」web ボディシミに注意!記事執筆
【新着】登録販売者のための業界コラム
- 2025年12月03日 【現役ドラッグストア店長直伝】冬商品で接客スキルを劇的に磨く3つのコツ
- 2025年11月21日 現役薬剤師が教える。登録販売者の新人教育マニュアル|OJTの進め方と後輩指導のコツ
- 2025年11月21日 現役薬剤師が伝授|インフルエンザ時に使える解熱剤の見分け方と登録販売者の声かけ技術
- 2025年11月06日 【2026年法改正で必須!】現役店長が教える「OD対策」現場対応完全ガイド 〜登録販売者が押さえるべき「3大変更点」と心構え〜<登録販売者のキャリア>
- 2025年10月30日 登録販売者はブランク後も復職できる!管理者要件と安心して働くためのポイント