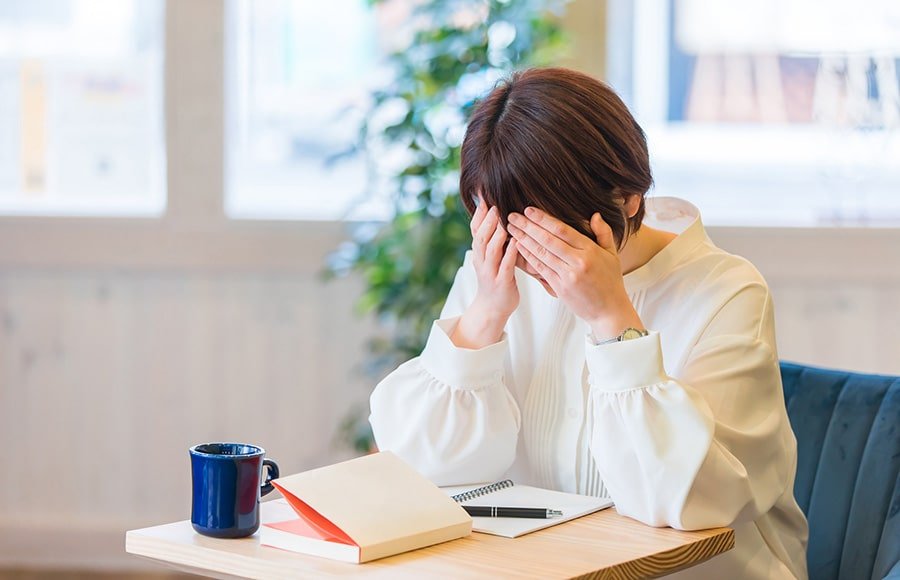【現場で使える!漢方】登録販売者のためのアレルギー症状に対する漢方薬の使い分け

花粉症といえば春先のスギやヒノキが注目されがちですが、実は一年を通して悩まされている患者さまも少なくありません。特に夏は、イネ科やブタクサなどの花粉が飛散し、見過ごされがちな季節性アレルギーの原因となっています。
今回は、登録販売者として知っておきたい「花粉症」と漢方による体質改善のアプローチについて、季節を先取りしてお届けします。
花粉症は、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、目のかゆみなどの不快な症状が多岐に渡り、日常生活に支障をきたす方も少なくありません。こうしたアレルギー症状の緩和には西洋医学的なアプローチだけでなく、漢方医学の知恵を活用することで、より包括的な対応が可能になります。
漢方での花粉症に対する対応では、単に症状を抑えるだけでなく、体質改善を通じて根本的な治療を目指します。本コラムでは、登録販売者として知っておくべき、花粉症をはじめとするアレルギー症状に効果的な主要な漢方処方とその使い分けについて解説します。
漢方医学から見たアレルギー症状
漢方医学では、アレルギー症状を「邪気(外邪)」の侵入と、それに対する体の反応と捉えています。また、西洋医学では免疫反応の過剰としてアレルギーを捉えますが、漢方医学では「気・血・水」のバランスの崩れや「虚実」の状態により、症状の現れ方が異なると考えます。したがって、患者さまの体質や症状の特徴に合わせて適切な漢方薬を選択することが重要です。
それでは、花粉症の主な症状別に効果的な漢方処方を見ていきましょう。
- ●扱う漢方
- 小青竜湯(しょうせいりゅうとう)
- 苓甘姜味辛夏仁湯(りょうかんきょうみしんげにんとう)
- 辛夷清肺湯(しんいせいはいとう)
- 麻黄附子細辛湯(まおうぶしさいしんとう)
- 越婢加朮湯(えっぴかじゅつとう)
目次
- ・鼻水・くしゃみに効果的な漢方処方
- ・鼻づまりに効果的な漢方処方
- ・目のかゆみ・充血に効果的な漢方処方
- ・西洋薬との併用について
- ・患者さまに合わせてお伝えしたい生活養生
- ・患者さまに寄り添った漢方薬の販売のために
1. 鼻水・くしゃみに効果的な漢方処方

1-1. 小青竜湯(しょうせいりゅうとう)
【構成生薬】
- 麻黄(マオウ)
- 芍薬(シャクヤク)
- 半夏(ハンゲ)
- 乾姜(カンキョウ)
- 五味子(ゴミシ)
- 細辛(サイシン)
- 桂皮(ケイヒ)
- 甘草(カンゾウ)
【特徴と使い分け】
小青竜湯は、水っぽい鼻水やくしゃみ、咳などの症状に効果的な代表的な漢方薬です。とくに「水毒」とよばれる水分代謝の異常を改善することを目的としています。
鼻水が透明でサラサラとしており、寒気を感じやすい方に適しています。症状が強く、鼻づまりよりも鼻水・くしゃみが主訴の場合に選択します。体を温める作用があるため、ドロドロした鼻水や黄色い鼻水など、熱症状には不向きです。
麻黄による発汗作用や気管支拡張作用、半夏による去痰作用など、各生薬の特性が花粉症症状の緩和に寄与します。
【服用上の注意点】
- 体を温める作用があるため、のぼせやすい体質の方や高血圧の方は注意が必要です。
- 麻黄を含むため、動悸や不眠を起こすことがあります。寝る直前の服用は避けた方がよいでしょう。
- 妊娠中の方の使用は医師へ確認しましょう。
1-2.苓甘姜味辛夏仁湯(りょうかんきょうみしんげにんとう)
【構成生薬】
- 茯苓(ブクリョウ)
- 甘草(カンゾウ)
- 乾姜(カンキョウ)
- 五味子(ゴミシ)
- 細辛(サイシン)
- 半夏(ハンゲ)
- 杏仁(キョウニン)
【特徴と使い分け】
この漢方薬は小青竜湯から麻黄、芍薬、桂皮を除き、杏仁を加えたものです。小青竜湯よりも穏やかな作用があり、体力がやや弱い方や、刺激に敏感な方に適しています。虚弱な方で、小青竜湯を使うのは少し心配...という方に向いています。
とくに、咳を伴う水様性の鼻水や、喉の不快感がある場合に効果的です。水分代謝を改善し、「水毒」を解消する働きがあります。茯苓や半夏の利水作用により、体内の余分な水分を排出します。
小青竜湯では刺激が強すぎる場合の代替としても覚えておきましょう!
【服用上の注意点】
- 麻黄を含まないため、小青竜湯よりも刺激は少ないです。
- 細辛を含むため、長期連用には注意がひつようです。
- 妊娠中の方は念のため医師に相談しましょう。
2. 鼻づまりに効果的な漢方処方
2-1. 辛夷清肺湯(しんいせいはいとう)
【構成生薬】
- 辛夷(シンイ)
- 黄芩(オウゴン)
- 桔梗(キキョウ)
- 防已(ボウイ)
- 麻黄(マオウ)
- 石膏(セッコウ)
- 白朮(ビャクジュツ)
- 川芎(センキュウ)
- 甘草(カンゾウ)
- 生姜(ショウキョウ)
【特徴と使い分け】
辛夷清肺湯は、鼻づまりを主訴とする花粉症に適した漢方薬です。辛夷の鼻粘膜の炎症を抑える作用と、他の生薬の相乗効果により、鼻腔の通りを改善します。
とくに、粘り気のある鼻水や蓄膿症を伴う鼻づまり、頭重感がある場合に効果を発揮します。体内の「熱」を冷まし、鼻腔内の炎症を鎮める働きがあります。
辛夷には抗炎症作用があり、鼻粘膜の腫れを軽減するのに役立ちます。また、黄芩や石膏の清熱作用も炎症抑制に寄与します。
【服用上の注意点】
- 麻黄を含むため、動悸や不眠に注意しましょう。
- 体を冷やす作用のある生薬(黄芩、石膏)を含むため、胃腸が極端に弱い方は注意が必要です。
- 妊娠中の方は医師に相談しましょう。
2-2. 麻黄附子細辛湯(まおうぶしさいしんとう)
【構成生薬】
- 麻黄(マオウ)
- 附子(ブシ)
- 細辛(サイシン)
【特徴と使い分け】
麻黄附子細辛湯は、わずか3つの生薬からなるシンプルな処方ですが、強い温熱作用があります。冷え症の方の鼻づまりや、水様性の鼻水に効果的です。
とくに体力が低下している方や、寒さに弱い方、顔色が青白い方に適しています。体を温めることで気血の流れを改善し、鼻腔の通りを良くします。
附子の強い温熱作用と麻黄の発汗作用、細辛の鼻粘膜の血行改善作用により、寒さによる鼻づまりを効果的に緩和します。
【服用上の注意点】
- 附子を含むため、体質によっては強い反応が出ることがある。
- 体を強く温める作用があるため、のぼせやすい方や高血圧の方は注意。
- 3種類とも刺激性の強い生薬のため、過敏な方は注意が必要。
3. 目のかゆみ・充血に効果的な漢方処方
3-1. 越婢加朮湯(えっぴかじゅつとう)
【構成生薬】
- 麻黄(マオウ)
- 石膏(セッコウ)
- 生姜(ショウキョウ)
- 大棗(タイソウ)
- 甘草(カンゾウ)
- 白朮(ビャクジュツ)
【特徴と使い分け】
越婢加朮湯は、目のかゆみや充血、まぶたの腫れなどに効果的です。とくに、水分代謝の異常による「水毒」が原因のアレルギー性結膜炎に適しています。
体力がある方で、目の周りや顔面がむくみやすい方に効果的です。石膏の清熱作用と白朮の利水作用により、目の周りの炎症や腫れを抑えます。
麻黄の発汗作用と石膏の清熱作用のバランスにより、体内の余分な熱と水分を排出し、アレルギー症状を緩和します。
【服用上の注意点】
- 麻黄を含むため、動悸や不眠に注意が必要です。
- 石膏の清熱作用が強いため、胃腸が弱い方は注意が必要です。
- 妊娠中の方は医師に相談しましょう。
4. 西洋薬との併用について

4-1. 抗ヒスタミン薬との併用
抗ヒスタミン薬は花粉症の第一選択薬として広く使用されています。漢方薬との併用についての注意点は以下の通りです。
【併用のメリット】
- 抗ヒスタミン薬の即効性と漢方薬の体質改善作用の相乗効果。
- 抗ヒスタミン薬の副作用(眠気など)を漢方薬が緩和する可能性。
- 抗ヒスタミン薬の減量が可能になることがある。
【注意すべき点】
- 麻黄を含む漢方薬と抗ヒスタミン薬の併用で眠気が強まることがある。
- 附子を含む漢方薬と抗ヒスタミン薬の併用で口渇が強まることがある。
- 甘草を含む漢方薬と抗コリン作用のある抗ヒスタミン薬の併用で便秘が悪化することがある。
【効果的な併用例】
- 症状が重い時期:抗ヒスタミン薬を主体に、漢方薬を補助的に使用。
- 症状が軽減してきた時期:漢方薬を主体に、必要時のみ抗ヒスタミン薬を使用。
- シーズン前:漢方薬のみで体質改善を図る。
【安全な併用のために】
- 処方前に患者の服用薬を確認しましょう!
4-2. ステロイド点鼻薬との併用
ステロイド点鼻薬は鼻づまりに対して効果的ですが、長期使用による副作用が懸念されます。漢方薬との併用についての注意点は以下の通りです。
【併用のメリット】
- ステロイド点鼻薬の即効性と漢方薬の持続性の相乗効果。
- ステロイド薬の使用量・期間の削減が可能になることがある。
- 鼻粘膜の乾燥などのステロイド副作用を漢方薬が緩和する可能性。
【注意すべき点】
- 漢方薬の効果発現には時間がかかるため、急性期は西洋薬に頼らざるを得ない。
- 症状が改善してきたら、漢方薬を継続しながらステロイド薬を徐々に減量する。
- 急な中止は避け、段階的に減量することが重要。
【効果的な併用例】
- 辛夷清肺湯とステロイド点鼻薬の併用で鼻づまりの早期改善と再発防止。
- 小青竜湯とステロイド点鼻薬の併用で鼻水と鼻づまりの総合的な管理。
- 麻黄附子細辛湯とステロイド点鼻薬の併用で冷え症の方の鼻閉塞に対応。
【安全な併用のために】
- 処方前に患者の服用薬を確認しましょう!
5.患者さまに合わせてお伝えしたい生活養生

西洋薬の力を借りながらも、東洋医学的な「養生(ようじょう)」を取り入れることで、体質改善のサポートができます。
ここでは、アレルギーに影響しやすい「湿」や「風邪(ふうじゃ)」の観点から、やるべきこと・やってはいけないことを整理してお伝えします。
アレルギーは「肺」と「肝」の乱れ、そして「湿」がカギとなります。
東洋医学では、
- 肺:外敵(外邪)から身を守る「バリア機能」=衛気を司る。
- 肝:自律神経や気血の流れを調整し、春に活発になりやすい。
- 湿:体内の余分な水分や老廃物が滞ると、鼻水やむくみを助長。
この3つのバランスが崩れることで、花粉症症状が悪化しやすくなります。
3つのバランスを保つために必要な養生をみていきましょう。
アレルギーの改善で「やってはいけないこと」
やってはいけないこととしては、「湿」や「熱」をためてしまう行動です。
好まれる方が多い食材には、一方で「湿」がたまりやすいものがあります。
また、日常生活でストレスや睡眠不足が重なると、身体の巡りが悪くなり「気・血・水」の渋滞が起こり熱を発生させるので注意しましょう。
湿気を生む食材や熱を発生させる生活習慣を避けることが大切です。
食材で避けたいもの
- ✖ 乳製品の摂りすぎ(チーズ・牛乳・ヨーグルト)
「湿」を生み、鼻水・むくみ・痰を悪化させます。 - ✖ 冷たい飲食物(アイス、水出し茶、氷水など)
胃腸を冷やし、体内の水分代謝が滞りやすくなります。 - ✖ 甘い物・油っこいもの(ケーキ、揚げ物)
脾胃(消化機能)を弱らせ、「湿」がたまりやすくなります。
生活習慣で避けたいこと
- ✖ 夜更かし・睡眠不足
肝の働きが乱れ、「気・血・水」の渋滞が起こり、熱が頭部へ上昇するため目のかゆみやイライラが悪化。 - ✖ ストレスをためる・怒りっぽくなる
肝気が上がり、「気・血・水」の渋滞が起こり、熱が頭部へ上昇するためアレルギー反応が強く出る原因に。 - ✖ 激しい運動やサウナでの過度な発汗
「気」を消耗し、肺のバリア機能(衛気)が弱ります。 - ✖ 朝イチの花粉の多い時間帯に窓を開ける
外邪(風邪)の侵入を受けやすくなります。
アレルギーの改善で「やるべきこと」
やるべきことは、「湿」や「熱」をためない、または排出する行動が大切です。食事であれば、「湿」を排出したり、「熱」を鎮めるものを選びましょう。
- ◎ 青菜類(春菊・せり・クレソン)
肝の気をのびやかにし、目や喉の不快感を鎮めます。 - ◎ ハトムギ・大根・レンコン
体にこもった「湿」を排出し、鼻の不調を改善。 - ◎ しじみ・はまぐりなどの貝類
肝の働きを助け、目のかゆみやイライラを抑える。 - ◎ 柑橘類(ゆず、レモン、グレープフルーツ)
気の巡りを整え、ストレスによる悪化を防ぎます。
おすすめの飲み物
- ◎ 甜茶
抗アレルギー作用。定番の花粉症対策茶。 - ◎ 菊花茶
目の充血やかゆみに。肝火を鎮める働き。 - ◎ ハトムギ茶
湿の排出を助け、代謝もサポート。
6.患者さまに寄り添った漢方薬の販売のために
本コラムでは登録販売者として、患者さんのニーズに応じた適切なアレルギーに対応する漢方薬を提案するためのポイントをお伝えしました。
花粉症においては、早めの啓蒙から開始し、漢方薬の提案だけでなく、花粉の時期の過ごし方までお伝えできるとより、患者さまとの関係性を深く築くことができます。ぜひ、次のシーズンまでにポイントを確認し、アウトプットできるようにしてください。
今回、漢方を使った花粉症の体質改善や皮膚のアレルギー症状については割愛しましたが、実際には中医処方(中国漢方)を使用することでアレルギー体質自体をケアすることも可能です。 ご興味のある方は学びを進めてみてくださいね。

執筆者:猪子英恵(いのこ はなえ)
薬剤師・国際中医専門員
臨床漢方カウンセリング協会理事
神奈川ME-BYOスタイルアンバサダー
集英社LEEキャラクター
首都圏を中心に全国の医療機関で漢方外来を受託。
「現場で使える」漢方とカウンセリングスキルの講座を
薬剤師・登録販売者に向けて開催。
臨床漢方カウンセリング協会
- 【執筆、監修など】
-
- わかさ出版ムック本 ハトムギ水 執筆、監修
- セントラルメディエンスコミュニケーションズ出版 月刊雑誌「からだにいいこと」2020年1月号 ハトムギ美容記事 執筆、監修
- 株式会社ハルメクホールディングス出版 月刊雑誌「ハルメク」2021年1月号ハトムギ美容記事 監修
- 第一三共ヘルスケアダイレクト株式会社 化粧品「RICE FORCE」web ボディシミに注意!記事執筆
【新着】登録販売者のための業界コラム
- 2026年01月09日 【現役ドラッグストア店長直伝】登録販売者が「辞めたい」と思わない3つのメンタル維持法(2026年対策付き)
- 2026年01月07日 2026年ドラッグストア業界の未来図|市場動向・M&A・登録販売者のキャリアと転職のポイント
- 2026年01月07日 登録販売者の年収は低い?現場にインタビューしてリアルな声をお届け!平均給料を調査
- 2026年01月07日 ドラッグストア店長の年収はいくら?平均額の内訳と600万円を目指す昇給のコツ
- 2025年12月03日 【現役ドラッグストア店長直伝】冬商品で接客スキルを劇的に磨く3つのコツ