【現役ドラッグストア店長直伝】登録販売者試験に合格してからの考え方<登録販売者のキャリア>

毎年、登録販売者の資格試験に合格して新しい登録販売者がデビューしています。しかし「資格は取れたが思ったように活躍できない」とジレンマを感じている方もいるのではないでしょうか。
実は登録販売者を目指している方や登録販売者試験に合格した方に長年接してきてわかった「共通するつまずき」が存在します。
今回はつまずかず登録販売者として大きく羽ばたけるコツを紹介していきます。
目次
登録販売者になった直後に陥るジレンマ

2009年に第1回の試験が実施されたので今年で15回目となる登録販売者試験ですが、毎年のように新たに登録販売者デビューした方と接していると共通する「つまずき」が存在します。
まずは典型的な「つまずき」を見てみましょう。
あなたは陥っていませんか?
勉強と実務の絶望的な乖離
まず十中八九、皆さんが揃って口にするのが「実務との乖離」です。
要は「勉強したことが接客で使えない」ということですね。
これは私も当初は感じましたし、ほとんどの方は共感するはずです。
「お客さまと何を話したらいいの?」
「お客さまの質問に応えられない」
そしてこの「つまずき」がトラウマとなり、お客さまに声をかけ辛くなっていく...
こうなるとまるでペーパードライバーのような「形だけ登録販売者」になってしまいます。
店舗が営業するためにいるだけ... 「濫用のおそれのある医薬品」対応だけ...
これでは登録販売者の本来の役割を果たしているとはいえません。
登録販売者の存在意義は「お客さまのQOL向上のため」だからです。
しかし試験勉強で学習した内容が役に立たない...という声は実に多く耳にします。
果たして、これは登録販売者だけの現象でしょうか?
例えば自動車免許を取得している方、教習所で学んだことは毎日の運転で役立っていますか?
もっと遡れば、中学や高校で学習したことも毎日の暮らしで役立っていることは少ないはずです。
しかし、それらはすべて土台となっているのです。
つまり登録販売者の試験に合格することで、ようやくOTC(一般用医薬品)の販売や相談に応える事ができる「最低限の科学的な知識」を身につけた事になるのです。
薬剤師と同じ店舗で働いている方はその知識に驚かれると思いますが、薬剤師でも薬学部を卒業し薬剤師試験に合格しただけでは「OTC(一般用医薬品)の知識」はほとんどありません。
どの薬剤師も薬の専門知識を得て、OTC(一般用医薬品)の知識を「実務で」学んでいくのです。
登録販売者も試験勉強はその後の実務での学習をおこなうための「基礎」なのです。
合格した皆さんはOTC(一般用医薬品)を「販売」するための資格を得たので「販売」の勉強をおこなうスタートラインに立った...ということなのです。
「できる登販」と「形だけ登販」の分岐ポイント
私はこれまで十年以上に渡り百人弱の登録販売者と接してきました。その中で「できる登販」と「形だけ登録販売者」の分岐ポイントが存在する、ということがわかってきました。
そのポイントは「登販試験合格後の一年間の過ごし方」です。
どんな事でも「最初の一年」は大切で、この期間の過ごし方や考え方でその後の成長速度に大きく差がつくのです。
例えば皆さんの職場でも入社し数カ月で退職してしまう方がいたと思いますが、このパターンも「入社後の過ごし方」で違った結果になった可能性が高いはずです。
「形だけ登販」に陥ってしまう方の特徴は、目標が「登販合格」であることが多く、合格することで達成感に満たされてしまうのが原因です。
もっとも大切な一年間を満足感にひたって能力向上をせずに過ごすのは停滞と同じことです。
大会の出場権利を得ただけで満足してしまうようなもので、本当にもったいないと感じます。
ではこうなってしまう登録販売者のパターンをみていきましょう。
合格後にこの思考はしてはいけない
登録販売者試験に合格後にしてはいけない思考は「受け身思考」です。
- 「合格したらそれでいい」
- 「誰かが教えてくれる」
- 「勤務中に教えてくれて当然」
この思考だと自分の中の基準がどんどん下がっていきます。
店舗で働いていると忘れがちですが、「登録販売者は個人資格」であり社内資格ではないことを忘れてはいけません。
スポーツ選手はチーム練習以外でも自己練習をしますし、営業マンも自己研鑽としてビジネス書を読むでしょう。
つまり自分の価値は自分の努力で高めていく必要があるのです。
そしてここでいう「自分の価値」とは「社会からの需要」のことでもあるのです。
合格後におこなうべき思考法
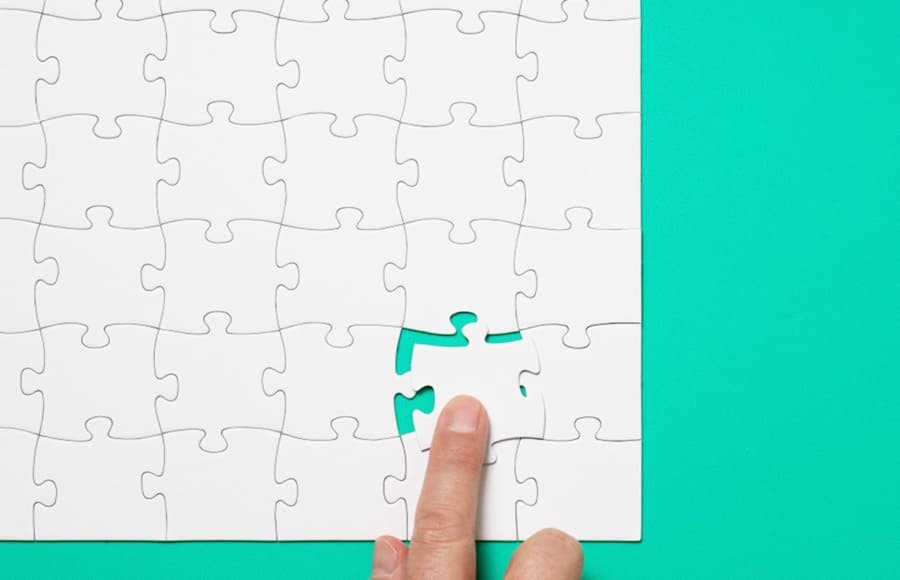
では実際に登録販売者になった直後はどんな思考をしながら働くべきなのでしょうか。
具体的に考えてみましょう。
得た知識を「自分」のために使う
自分の価値を高めるために知識を吸収して経験を増やすべきなのはわかるけど、なかなか身につかない...という悩みを相談として受けることもあります。
また、新人登録販売者の動きを見ていると明らかに行動も思考も右往左往している様子がわかります。
現場でもよくアドバイスをおこなうのですが、最初は資格取得をした知識をすべて「自分のこと」に使うのがお勧めです。
過去に自分が使った薬、現在使っている薬、気になるサプリ、健康法など何でもいいので、せっかく得た知識を自分のために使いましょう。
自分のために使うことがないのなら家族のためでもいいですし、子どもの頃に教えてもらった民間療法でもいいので登録販売者の勉強を通して身につけた知識を通して深掘りして考えてみてください。
これらが実務に役立つかどうかは全く問題ありません。
「得た知識を利用する」という習慣付けが大切なのです。
これを「アウトプット」と呼びますが、まずは自分にアウトプットするのです。
いきなり実務に使える方は問題ありませんが、できていなかったり不十分と感じる方はぜひ自分のために知識を使うところからスタートしてください。
「他人事」だと本気になれないことも、「自分ごと」だと本気になれるものです。
「自分」の経験からアウトプット
アウトプットにも様々な方向があります。
自分にアウトプットすることに慣れてきたら、その経験を「他人」にアウトプットしましょう。
他人とは「家族」「仲間」「お客さま」のことです。
他人の話を聞いたうえでアウトプットすることに慣れないのなら、家族や仲間に自分の体験談を話してみましょう。
「常備薬の胃薬にこの商品を使っていたけど、〇〇という症状なら違う商品の方が良かった」
「この目薬より濃度が濃くて効き目のある商品があった」
「もっと肌に優しくて効果がある湿布薬があった」
このようなアウトプットで充分です。
経験や自身の思考からアウトプットすることで記憶は定着しますし、なによりアウトプットする癖が付きます。
「優秀な人材」とは、どんな資格でもアウトプットする癖がある人のことなのです。
アウトプットの回数が増えると精度も増してくるので、最初は易しいことで大丈夫です。
とにかく回数をこなしてください。
沼にはまらないコツ
登録販売者として経験を積む前に念頭に置かなくてはいけないことがあります。
それは「深掘りしすぎて沼にはまる」ことです。
ドラッグストアをはじめとしたOTC(一般用医薬品)を扱う業態はどんな立地でもさまざまな症状に満遍なく需要があります。
とくに拘りが強い方が沼にはまりやすいのですが、ひとつの分野に集中しすぎて他の分野の知識が疎かになる場合があります。
過去に同じ店舗で働いた登録販売者の中にも、漢方薬の沼にはまり詳しくなった方がいました。
しかしその方は他のOTC(一般用医薬品)を学ぶ意欲と時間がなくなってしまい、販売知識が偏っていました。
この方には毎日少しずつ商品知識をアドバイスしていきましたが、自分の性格が拘りが強いしと自覚している方は注意が必要です。
まずは、いったん自身の店舗の商品ジャンル(鎮痛剤・風邪薬・胃薬など)を一通り網羅してから、2年目以降に深掘りしていくべきです。
それまでの勉強範囲の基準は店舗の売上の大きいジャンルから「接客の際にパッケージで説明できる範囲」と「禁忌」に抑えておくのがベターです。
一通り網羅し、特定のジャンルに興味が出てきたら深掘りしていきましょう。
もっとも必要なのは周囲のサポート

ここまで本人がどうすべきか書いてきましたが、もちろん店舗として新人登録販売者を育てていく努力も必要です。
本人のヤル気が行方不明になってしまわないようコントロールするという意味においてはもっとも重要とも言えます。
店長の役割とは
店舗として新人登録販売者の教育にもっとも責任があるのは、もちろん店長です。
その登録販売者が今後どう育つのか、その時の店長次第といっても過言ではありません。
もちろんどの企業にも登録販売者の教育ツールや勉強のシステムがあると思いますが、店長は登販の教育を会社任せにしてはいけないと考えています。
新人アルバイトはしっかりオペレーション教育をするのに、新人登録販売者は本人の自己研鑽に任せて放置しているという職場が散見されますが、こうした状況はメイン商材であるOTC(一般用医薬品)の販売力を落とすことにもつながり、店舗運営において非常にアンバランスな状態です。
先にも述べた通り、登録販売者試験に合格直後は本人も登録販売者として何をしたらいいかわからない状態です。
自動車学校でも初めて公道で運転した時どうしたらいいかわからないのと同じように、伴走者のように寄り添ってサポートする必要があります。
もし本人が合格したことで「達成感」があり学ぶ意欲が出てこない場合、店長側から興味づけをする必要があります。
おそらくこの場合は試験勉強から解放されたことでいわゆる「勉強」から離れたい気持ちが大きいでしょうから、雑学的な話題でOTC(一般用医薬品)の話をしていくとよいです。
以下は実際に新人登録販売者の方に問いかけたクイズや雑学です。
- 徳川家康が愛用していた漢方薬があるんですよ(八味地黄丸)
- 龍角散って何年前から使われているか知っていますか?(江戸時代末期)
- 実はこれが世界でいちばんおいしいビタミン剤なんですよ
- この中で運転が禁忌の下痢止めってどれだと思います?(ロートエキス60mgのもの)
- この中に冷蔵庫に入れたらいけない目薬があるんですよ(トラニラスト配合や抗菌目薬)
こんな簡単なもので興味を持ってくれます。
こうしたクイズ形式で興味付けをしながら少しずつ深堀りしたり話題を横展開していくと興味を惹きやすいので、コミュニケーションを綿密にする手段にしてください。
内容を忘れてしまって質問に答えられないこともあるでしょうが、そんな時は一緒に調べればよいのです。
先輩としての妙なプライドはいらないので「共に学ぶ」という姿勢で教育をおこなうと自身の復習にもなります。
少なくとも出勤日に一回はOTC(一般用医薬品)の話をすると本人の学習意欲も増します。
ほんの3分程度でも構わないので店長としてきっかけを作ってあげてください。
登録販売者同士のサポートは必要か
登録販売者資格を持っている周囲のスタッフもサポートに参加すると、新人登録販売者の学習意欲がさらに向上します。
店長と同じように自身の復習になるため、積極的なサポートをしてみてください。
この「教え合う風潮」は店舗間格差が激しく、全く薬の話をしない店舗もあれば売場でスタッフ同士が教え合う光景をよくみる店舗もあります。
後者の店舗では登録販売者が育ちやすく、好循環で他の従業員も登録販売者を目指しやすくなるのです。
新人登録販売者にとって孤独な学習ほど成長を阻害するものはありません。
そして周囲の登録販売者同士でサポートをし合える状況を作り出すのは、店長の仕事です。
いったんその環境を構築すると自動的に助け合う環境になるので、店長は一日3分でもいいので薬の教育に時間を割いてください。
サポートに「応える」のがアウトプット
本人もサポートされるだけではいけません。
自分の時間を割いてまでサポートしてもらった同僚や上司に恩返しの意味でもしっかりとアウトプットをおこないましょう。
スタッフ同士のアウトプットでも成長できますし、この循環が生まれていればお客さまに対して積極的な接客ができるようになるのに大きく時間はかからないはずです。
一日の勤務のうち、ほんの数分の積み重ねをおこなうかどうかで数年後の姿が変わるはずです。
小さなインプットを積み重ね、大きな実力を身につけて需要のある登録販売者を目指してください!

執筆者:ケイタ店長(登録販売者)
ドラッグストア勤務歴20年、一部上場企業2社で合計15年の店長経験を活かし、X(旧Twitter)などで登録販売者へのアドバイスや一般の方への生活改善情報の発信を行っている。X(旧Twitter)フォロワー数約5,000人。
【新着】登録販売者のための業界コラム
- 2026年02月04日 【専門家監修】正月太りの原因&最短リセット法|食事・サプリ・漢方で無理なく解消するコツ
- 2026年02月04日 【専門家監修】胃腸炎に効くドラッグストアの市販薬5選!症状や原因別の選び方のポイントもあわせて解説
- 2026年02月03日 登録販売者に年齢制限はあるの?正社員・パートなど働き方別に解説
- 2026年02月02日 登録販売者試験に受かったら。合格後の手続きや流れを分かりやすく解説!
- 2026年01月30日 登録販売者になるために必要な勉強時間は?働きながら合格できるスケジュールと効率化のコツ






