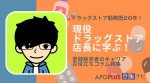【現役ドラッグストア店長直伝】登録販売者1年目の教科書<登録販売者のキャリア>

今年も多くの登録販売者が誕生し、店頭に立つことになります。
わたしの店舗でも合格したパートナーがいるので現在教育をおこなっているのですが、その中で皆さんのような新人登録販売者がつまずきやすいポイントがわかってきました。
今回はそれを踏まえたうえでわたしが教育している内容をお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。
もちろん2年目以降の登録販売者や、店舗で教育をおこなう側の方も参考にしていただける内容ですので、ぜひお役立てください。
目次
登録販売者として心得ておくこと

今まで店頭に立っていた方もそうでなかった方も、資格を取得し店頭に立つということに緊張していると思います。
ここで「登録販売者」とはそもそも何なのかを考えてみましょう。
登録販売者の存在意義とはなんだろう
登録販売者資格を取得する理由は人それぞれでしょう。 自発的に取る人、会社指示で取る人、転職や就職のために取る人、収入アップのために取る人...
理由はどうであれ、お客さまにとって「良きアドバイザー」となる必要がありますし、そのための努力や研鑽が必要となります。
登録販売者はお客さまのQOL(生活の質)向上のための資格なのです。
登録販売者試験はその土台となる知識を得るためのハードルでしたが、この先は皆さんがお客さまにとって安全なOTC(一般用医薬品)を選択するための知識をインプットしなければいけません。
そしてそのためのハードルを自身で設定する必要もあるのです。
教える立場の方は新人登録販売者のレベルに沿ったハードルを設定していただきたいですし、できれば店舗全員で新人登録販売者をサポートしてください。
すべての店舗でこのような動きをおこなうことで国民の健康寿命を伸ばすことができると信じています。
ゲートキーパーとはなんだろう
登録販売者の社会的な意義としてとくに近年話題になるのが「ゲートキーパー」です。
ゲートキーパーとは市販薬を適正な用法容量を超えて大量に服用する「オーバードーズ」をおこなう人に対して、適正な知識と対応で乱用に苦しむ人を救う役割のことです。
参考:一般用医薬品の乱用(オーバードーズ)について (薬剤師、登録販売者の方へ)|厚生労働省
しかし、このゲートキーパーという言葉が重荷になっている登録販売者も多く、クレームを恐れたり説明が難しいと感じたりする方が多いのを感じます。
また、下記のような問題点もあります。
- お客さま自身が持病を申告しない
- 連用や販売制限など、明確な基準が存在しない
- 同じ対応をおこなってもお客さまによって反応が違うので言い辛い
このような問題点はとてもよく理解できますし、業界全体で改善すべきだと感じます。
「登録販売者」という極端に言えばお客さまの健康や命に直結する可能性のある商品の販売資格というのは資格者自身に過度なプレッシャーを与えてしまう側面もあります。
どうして登録販売者はこんなに重いのか?と感じる方もいれば、そこまで考えていない方もいるのが現状です。
果たして登録販売者だけが大変なのでしょうか。
他の職業に置き換えて考えてみよう
ここで視点を変えて他の職業に置き換えてみましょう。
わたしは新人登録販売者に話をする時に「タクシードライバー」で例えて説明します。
タクシードライバーも乗客の命に関わる大切な仕事です。
お客さまの要望を聞き、目的地まで安全で最短の経路を選び、安全運転でお客さまを運んでいます。
これは登録販売者に通ずるものがあります。
お客さまの悩みを聞き、改善するためのメリットが大きくデメリットが少ない商品を提案し、解決していくのです。
しかしこれを大きな障壁と捉えてしまう登録販売者が少なくありません。
中には「そこまで考えなくても...」と考えている方もいるようです。
しかし本当にそうでしょうか?
「急いでいるから赤信号を無視してくれ」「間に合わないから100kmで走ってくれ」と乗客に言われ、その通りに運転するタクシードライバーはいるでしょうか?
もし事故が起きたら誰の責任になるのでしょうか?
お客さま? タクシードライバー?
この場合は間違いなくタクシードライバーに責任がありますし、乗客も怪我をしてしまいます。
最悪の結果、命に関わる可能性も少なくありません。
例外はあるかもしれませんが、タクシードライバーが道交法を守って仕事をしているのと同じように、わたしたち登録販売者も利用者の健康と安全を守るために作られた薬機法や業界ルールを順守しなければなりません。
それが目の前と未来のお客さまの健康に直結するのです。
会社との向き合い方を考える

登録販売者として勤務をすると必ず当たる壁が「会社指示との向き合い方」です。
ここで心が折れてしまったり登録販売者の存在意義を忘れてしまう方もいるのが実情です。
自分のポリシーと会社や上司の指示が相反した時、どう対応すべきか今のうちに学んでおきましょう。
誰もが陥るジレンマを理解しておこう
どの企業でも推奨品や新商品の売上実績を重視しているはずです。
これは小売業である以上、避けられないことです。
推奨品は利益とリピーターを生むことができますし、新商品は購入するすべてのお客さまにとって「最初の1個」なので新規の顧客を生むことができます。
ドラッグストア以外でも小売業なら「利益率」と「客数」に直結するため重視されるべき商品群です。
しかし、医薬品やサプリメントは一歩間違えれば健康被害や副作用が起こる商品であり、登録販売者試験でも何問か出題されたはずです。
必ず、会社が売りたい医薬品やサプリメントの販売についてジレンマを抱える時がやってきます。
売らなければいけないのに該当するお客さまが来店しない...
販売できるお客さまだが、売りたい商品が本当にそのお客さまにとってベストなのか...
他の登録販売者や他店での好事例はどこまで参考にしていいのか...
このような悩みは登録販売者としての責任感が強い方が持つ傾向にあります。
言い方が悪いですが、サラリーマン的な思考だと「売りたいもの優先」となってしまい、登録販売者資格が「お客さまのQOLを向上させる」のではなく、単に「薬を販売できる資格」になってしまいます。
では、このような状況になったとき、登録販売者としてどう対応すべきなのでしょうか。
「登録販売者」は個人の資格
登録販売者という資格は誰のものなのでしょうか。
もちろん登録販売者試験に合格したあなた自身のものです。
登録販売者として法令と科学に基づき判断し、お客さまにアドバイスをおこなうのが理想です。
もし仮に無理な販売指示による販売をおこないお客さまに健康被害が出た場合は、販売した登録販売者に責任が及ぶ可能性もあります。
先ほどのタクシードライバーで例えてみましょう。
会社からの乗車ノルマを達成するためにはスピード違反をしなければ不可能という状況だったら...?
もしそれで検挙されたら...?
免停などの処分を受けるのは運転したタクシードライバーです。
もしかしたら会社も処分を受けるかもしれませんが、タクシードライバー自身の処分が免れることはありません。
登録販売者も無理な販売でのクレームは聞きますし、不十分な確認による副作用で訴えられた事例も存在します。
こうしたリスクは実際に起こり得ることを念頭に入れておくべきです。
会社指示はこう捉えるべし
では実際に業務指示として医薬品の販売に携わるときにどう受け止め、動くのが正解なのでしょうか。
会社や上司の指示に少しでも疑問に思ったとき、登録販売者としての解決法があります。
それは「学び」です。
時には理不尽な指示も出るでしょう。
苦手な商品に注力しなければいけないときもあるでしょう。
しかし商品販売指示であろうと業務指示であろうと、どんな指示も学びの側面があるのです。
わたしが接してきた中で「伸びる登録販売者」はこうした指示をプラスに捉えてインプットの契機にしてしまう人です。
登録販売者の資格を取得し、現場に出た直後におこなうことは商品知識のインプットです。 このインプットの契機にするには「強制的な販売」がもっとも効果的なのです。
会社によっては多くの推奨品が存在すると思いますが、いったん「義務感」のフィルターを外して商品をみてみると何かしらの発見があるはずです。
その発見の積み重ねがスキルアップにつながっていくのです。
ではお客さまとの接客での注意点をあげていきます。
お客さまとの関係と距離感とは

医薬品の販売でもっとも注意すべきは、その商品が「お客さまにとってプラスになるかどうか」であるため、販売実績主体で考えてはいけません。
医薬品やサプリの販売で「数多く販売する」という実績自体は素晴らしいのですが、本当にお客さまにとって最善の商品だったのかは考える必要があるからです。
リスクの伝え方のコツ
医薬品には「副作用」が必ず存在します。
「濫用等のおそれのある医薬品」の確認で頻繁にレジへ呼び出されることも多いはずです。
この医薬品の「副作用」には短期的な副作用と長期的な副作用が存在しますが、大多数のお客さまは副作用についてあまり関心を持っていません。
OTC(一般用医薬品)はほとんどが合剤(配合剤)であり、効能効果も副作用も多岐にわたります。
利便性を求めていると知らず知らずのうちにQOLを低下させてしまうこともあるため、お客さまにはわかりやすいよう伝える事が重要です。
ただ、この際に脅しにならないようソフトに伝えることが重要です。
もしお客さまがOTC(一般用医薬品)を積極的に使えなくなってしまったら国が推し進めるセルフメディケーションの足かせになりかねません。
副作用の情報提供は次の点を伝えるようにしましょう。
- 持病への影響
- 依存の問題
- QOLの低下
この時のポイントは「お客さまの心配をする」というスタンスをとることです。
経験が浅いうちはどうしても教科書的な接客となり、お客さまにとっては押し付けのような感覚を覚える事があります。
「副作用や持病との問題があるので心配ですがよろしいですか?」という態度で接してください。
自らの身を守る考え方
登録販売者として勤務するうえでの重要な考え方のひとつに「自身の身を守る」というものがあると考えています。
これには「クレームなどから身を守る」「自身の雇用を守る」というふたつの意味があります。
まず前者ですが、健康に関する商品の販売ですからお客さまとのトラブルが起こる可能性もあります。
過去のクレーム事例からわたしは店舗の登録販売者に伝えていることがあります。
- 効能効果以外のことを言わない
- 接客の最後に「必ず添付文書をお読みください」と添える
- お客さまの否定をしない
このポイントを抑えておけば大きなクレームは起こりません。
逆に言えばクレームはこのポイントから逸脱しているときに起こるのです。
それでも健康被害は発生する可能性はありますが、店舗側でしっかりと情報提供を行ったのなら責任が及ぶことはないのです。
登録販売者は「お客さまが安全にOTC(一般用医薬品)を使用できる情報と商品を提供する」ところまでが責務です。
安全にOTC(一般用医薬品)を使用し、お客さま自身でも情報を確認し、気持ちよく購入していただけるよう常に考えて接客を行えばクレームの発生は大きく減少します。
信頼感を得るための行動
最後にお客さまから信頼されるためのポイントを3点お伝えしますのでぜひ実戦してください。
・「~と思います」を使わない
口癖になっている人もいますが、「~と思います」はお客さまによってはかなり信頼度を落とす言葉なので医薬品接客においては禁忌です。
「この商品が効くと思います」
「お客さまの症状だとこの商品です」
どちらが信頼されるでしょう。
「~と思います」は憶測や他人事のように感じるため、信頼性を大きく下げます。
・不明点はその場で調べる
経験が浅い間は接客の中でわからないことが出てくるのは当然のことです。
この時に「調べてまいります」が言えるかどうかは大きなポイントです。
今回タクシードライバーの例えをしていますが、どちらのタクシー運転手が安心できますか?
カーナビを使うタクシードライバー
遠回りをしているっぽいタクシードライバー
どう考えても前者ですよね。
登録販売者も同じで「わからなかったら調べる」のは当然です。
医師や薬剤師も同じように不明点はその場で調べます。
お客さまは接客に「安心」を求めているため、不明点は調べてください。
・他の事例を使う
理論でごり押しして販売するのは控えるべきです。
お客さまによってはその方が納得する方もいますが、大多数のお客さまには理屈っぽいと受け取られてしまいます。
マーケティングの世界でもっとも効果的なのは「口コミ」「レビュー」です。
とくに日本は協調性を重視する民族性なので「他の人も使って効果があった」というのは大きなポイントです。
過去のお客さまとの接客、同僚からの情報、自身が使ってみての経験を接客に織り交ぜると話の説得力が上がります。
人間は大多数のデータより「目の前の人が効いた」と言った方が納得してしまう心理を持っているので、効果があったという情報は成分の理屈より心にすっと入ってくるのです。
今回の内容は基本的な考えです。
これから店頭で活躍することでご自身の経験が枝葉となって広がり、やがて結果が実るのです。
実際の店舗での接客を通し、一歩ずつ階段を登っていきましょう。
応援しています!

執筆者:ケイタ店長(登録販売者)
ドラッグストア勤務歴20年、一部上場企業2社で合計15年の店長経験を活かし、X(旧Twitter)などで登録販売者へのアドバイスや一般の方への生活改善情報の発信を行っている。X(旧Twitter)フォロワー数約5,000人。
【新着】登録販売者のための業界コラム
- 2025年09月04日 2025年4月1日から東京都のカスハラ防止条例が施行 - 接客で知っておくべきカスハラ対策をわかりやすく解説
- 2025年08月18日 【完全ガイド】登録販売者が独立開業するには?手順と必要条件を解説
- 2025年08月14日 ドラッグストアでできる熱中症の予防・対策とは?登録販売者が伝えたい実践ポイントを解説
- 2025年08月13日 調剤薬局に転職した登録販売者にインタビュー|面接対策や働き方のリアルがわかる!
- 2025年08月13日 【登販向け】知らずに違反していない?健康食品販売でやりがちなNG表現と対策