【登販向け】知らずに違反していない?健康食品販売でやりがちなNG表現と対策

こんにちは、登録販売者転職のアポプラス登販ナビライターチームです。
健康食品は手軽に購入できることから、生活の中に深く浸透しています。しかし、販売現場においては違反表現を使ってしまう危険が潜んでいるのをご存じでしょうか。違反表現と知らずに説明してしまうと、法令違反と判断されることもあるため注意が必要です。
健康食品やサプリメントの販売・接客に不安を感じている登録販売者の方は、この記事を読めば、法律に抵触しない販売・接客方法、問題発生時の対応方法について把握できます。やりがちなNG表現や通報・相談先、よくある質問についてもあわせてご紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
【この記事で得られること】
- 健康食品販売では、接客時に伝える情報の表現を誤ると、薬機法や景品表示法などの法令に違反してしまうケースがある
- 登録販売者は、正しい商品知識をアップデートし、店舗全体で法令遵守の重要性を認識する必要がある
- 登録販売者は、問題発生時には然るべき機関に通報・相談し、お客さまのケアに努める
目次
- ・健康食品販売に潜むリスクとは?
- ・違反の種類と実例
- ・やりがちなNG表現チェックシート
- ・リスクを回避するために登録販売者ができること
- ・登録販売者が知っておきたい問題発生後の立て直し方
- ・通報・相談先一覧
- ・FAQ|【登録販売者向け】健康食品販売時によくある質問
- ・まとめ|健康食品販売は正しい知識と慎重な対応が信頼につながる
健康食品販売に潜むリスクとは?

健康食品は、OTC(一般用医薬品)ではないため、販売時に効果効能を強調すると薬機法違反に該当するリスクがあります。そのため、販売員の善意や親切心から口にした一言が、法律上の問題になる場合もあるのです。
とくに店舗での対面販売は、お客さまの悩みに寄り添おうとするあまり、違反表現を使う可能性が高まるといわれています。適切な知識を持ったうえで、販売することがリスク回避につながるのです。
健康食品販売における違反表現の実態
東京都健康安全研究センターが実施した調査では、健康食品販売において違反表現が多く見られることが明らかになりました。とくに「がんに効く」「必ず治る」といった断定的な効果を示す表現は薬機法違反に該当するため注意が必要です。
この調査結果は、健康食品販売にかかわる多くの店舗が、無意識のうちに違反リスクを抱えている現状を示しています。そのため、販売員の説明内容を見直し、法律に抵触しない表現を日頃から意識しましょう。
なぜ違反が起きやすいのか?
健康食品販売で違反が起きやすい理由は、販売員が説得力を高めようと努力しすぎるためだといわれています。つまり、お客さまの信頼を得たいという気持ちから「○○に効きます」といい切ってしまうことが多いのです。
たとえば、「最近疲れがとれない」とお客さまに相談されたとき、つい「このサプリは疲労回復に効きますよ」と断言したくなりますよね。お客さまの役に立ちたいという気持ちや、商品を強くおすすめしたいという気持ちから出た言葉でも、法律上のNG表現になることがあります。
また、他店舗や先輩から聞いた話をそのまま説明に使用してしまうケースにも注意が必要です。「よく聞くフレーズ」やインターネットの情報を事実確認せずに使ってしまい、知らぬ間に法令違反になる場合もあります。信頼できる情報源を辿り、根拠のない説明をしないようにしてください。
健康食品市場の拡大と現場の悩み
サプリメントや健康食品の市場は年々拡大を続け、多くの消費者が日常的に取り入れるようになっています。しかし、販売現場では「どこまで説明してよいかわからない」という不安を抱える販売員が少なくありません。
「この商品で治るのか」といった質問を受けることもあるため、販売員はどのように対応すべきか悩んでいるのです。お客さまからの需要が高まるほど説明の機会は増えますが、その分リスクも高まるため、現場では適切な言葉選びが求められます。登録販売者には、正しい商品知識の習得や現場経験の蓄積といった自己成長が求められているのです。
違反の種類と実例

健康食品販売では、知らないうちに法令違反となる表現を使用してしまうケースが多く見受けられます。違反は種類ごとに具体的な表現と根拠法令が異なるため、事前に正しく理解しておくことが重要です。
以下の表に、注意が必要な違反の種類と、その実例をまとめました。
| 違反の種類 | 具体的なNG表現例 | 根拠法令 |
|---|---|---|
| OTC(一般用医薬品)的効能効果 | 「がんが治る」「血圧が下がる」 | 薬機法 |
| 誤認を招く表示 | 「絶対安全」「副作用ゼロ」 | 景品表示法 |
| 根拠なき効能主張 | 「飲むだけで痩せる」「老化防止に効果」 | 健康増進法 |
| 不適切な比較表現 | 「他社製品より効果が高い」 | 景品表示法 |
| 不十分な表示 | 原材料やアレルゲンの未記載 | 食品表示法 |
このように、健康食品販売では薬機法、景品表示法、健康増進法、食品表示法など複数の法律が関係しているため、表現を誤ると重大な違反につながります。販売員は日頃からこれらの違反事例を確認し、リスクを避ける販売姿勢を徹底しなければなりません。
やりがちなNG表現チェックシート

健康食品販売の現場では、違反を防ぐために具体的な表現チェックを日常的におこなうことが大切です。とくに口頭説明の場面では、意識せずにNG表現を使ってしまう危険があるため、事前チェックが欠かせません。
以下の表に、やりがちなNG表現をまとめました。事前に覚えておくと、説明時に役立つでしょう。
| チェック項目 | NG例 | OK例 |
|---|---|---|
| OTC(一般用医薬品)的効能をいっていないか? | 「治る」「効く」「治療できる」 | 「健康維持に役立つ栄養素を含みます」 |
| 効果を断定していないか? | 「必ず痩せます」「絶対改善します」 | 「食生活のバランスを補助します」 |
| 根拠のない情報を伝えていないか? | 「テレビで話題」「口コミで人気」 | 「厚生労働省の基準を満たしています」 |
| 比較や優劣を誇張していないか? | 「他社より優れている」 | 「当社独自の配合です」 |
| 個人の体験談を一般化していないか? | 「私もこれで治りました」 | 「個人差があります」 |
上記のチェックシートを使えば、自分の説明や店舗のポップに違反リスクが含まれていないか事前に確認できます。このように、間違った表現を避け、正しい説明にいい換える習慣を身につけることで、店舗全体のコンプライアンス強化につながります。
ぜひ定期的に確認し、リスク回避につなげましょう。
リスクを回避するために登録販売者ができること
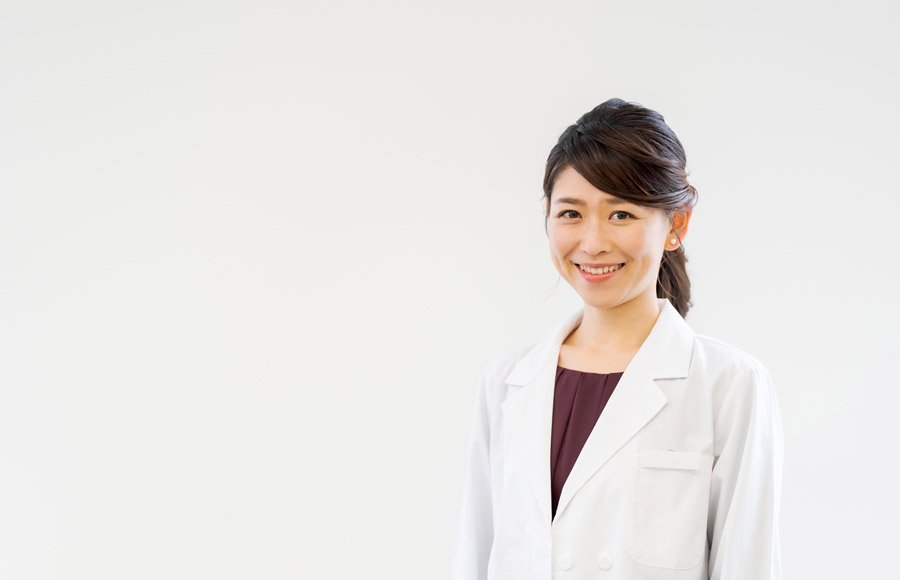
健康食品の販売において、登録販売者が法令違反を防ぐためには、日頃から意識的にリスク管理をおこなう姿勢が求められています。確かに、現場での接客はスピードと柔軟さが必要ですが、焦って不用意な発言をしてしまうと、違反に直結する危険があります。
ここでは違反を防ぐために登録販売者ができる具体的な行動を紹介します。
正しい商品知識のアップデート
登録販売者が健康食品販売でリスクを避けるためには、まず商品知識を常に最新の状態に保ちましょう。なぜなら、サプリメントや健康食品は新商品が次々に登場し、配合成分や特徴も日々進化しているためです。
そのため、カタログ情報だけでなく、メーカー資料や公的機関が発信する最新情報を確認し、確実に知識を積みあげていきましょう。定期的に社内勉強会へ参加するなどして、わからないことを曖昧にしない姿勢を持つこともリスク回避に有効です。
アポプラス登販ナビでは、サプリメント販売時の判断力や商品知識のアップに役立つ、薬剤師監修のトレーニングツールを提供しています。用途に合った商品の選び方や主要成分の効能・注意点を理解し、知識の定着度をテストで確認可能です。現在はダイエットジャンルに特化していますが、今後さらに拡充予定ですので、ぜひスキルアップにご活用ください。
医薬品的効能効果はいわない
健康食品はあくまで食品であり、OTC(一般用医薬品)と同じような効能効果を口にすることは絶対に避けましょう。なかでも「治る」、「効く」、「改善する」といった表現は、たとえお客さまにわかりやすく伝えたいと思っても使用してはいけません。
登録販売者は薬機法を理解したうえで、「健康の維持に役立つ」といった適切な表現を選び、お客さまの質問にも正しく説明することが大切です。このように、OTC(一般用医薬品)的表現を避ける意識を徹底することが違反防止の第一歩となります。
根拠のある情報(公的機関・メーカー公式)以外は伝えない
健康食品に関する情報はインターネットや口コミであふれていますが、根拠のない情報をそのまま伝えることは非常に危険です。「テレビで紹介されていた」、「人気がある」といった話題性だけで説明するのは適切ではありません。
登録販売者が案内する内容は、公的機関やメーカー公式資料に基づいた信頼できる情報だけに限定しなければならないのです。そのため、常に出典を意識して、確かな情報だけをお客さまに届けましょう。
答えられない場合は「確認します」と保留する勇気を持つ
健康食品の接客では、時に難しい質問を受けることがあります。わからない場合にその場で曖昧な説明をするのは、店舗にとって大きなリスクにつながるため避けましょう。登録販売者サイドは即答せず「確認してからご案内します」と正直に伝えるのが賢明です。
答えを出せないときは無理に答えようとせず、メーカーや上司に確認し、後日きちんと説明してください。このように、お客さまとの信頼は、正確な情報提供で積み重ねていくものなのです。
登録販売者が知っておきたい問題発生後の立て直し方

万が一、健康食品の販売において問題が発生した場合、店舗として迅速かつ適切に対応することが重要です。誤った説明や違反表現が発覚した際、登録販売者は自らの行動を振り返り、店舗全体で再発防止に取り組まなくてはなりません。
ここでは、問題が発生したときに登録販売者がおこなうべき立て直しの流れを紹介します。
お客さまへのケア
問題が発生した際は、まず対象のお客さまに誠実に対応することが最優先です。事実関係を丁寧に説明し、必要であれば謝罪もきちんとおこないます。もし、お客さまがアレルギー体質の場合や、お客さまが服用している医薬品との相互作用が懸念される場合など、健康食品の継続使用にリスクがあると判断したら、速やかに使用中止を促しましょう。
さらに、体調不良が見られる場合は、医療機関の受診を勧めてください。このように、誠意を持った対応を徹底し、店舗として責任ある姿勢をお客さまに示すことが信頼回復につながります。
店舗スタッフ全員で法令遵守の再確認
問題が発覚した後は、店舗全体で法令遵守の重要性を改めて共有してください。登録販売者だけでなく、すべての販売スタッフが薬機法や景品表示法を正しく理解し、再発を防ぐための意識を高めましょう。
とくに、日常業務で見落としがちな表現や対応について、スタッフ間で具体的に話し合うことが有効です。このように、店舗全体でルールを確認し合い、適切な販売体制を再構築することが信頼回復につながるのです。
定期的な勉強会・研修の実施
違反を防ぐためには、一度学んで終わりにせず、定期的に勉強会や研修を実施することが大切です。なぜなら、健康食品を取り扱う販売現場では、法令や行政の指導内容が更新される場合があり、継続的に最新情報を学ぶ必要があるためです。
社内で定期的に事例を共有し、法律に抵触しない表現や適切な説明方法を改めて確認しましょう。スタッフ全員が同じ意識を持つために継続した学習の場を設けると、スムーズな立て直しに役立ちます。
POP・広告物の全点検
店舗で掲示しているPOPや広告物も問題発生時に必ず見直してください。なぜなら、口頭説明だけではなく、書面や販促物にも違反表現が含まれている可能性があるためです。
とくに店舗独自で作成したポップは、表現が自己流になりやすく、薬機法や景品表示法に抵触するおそれがあります。そのため、すべての販促物を一つひとつ丁寧に点検し、必要であれば修正・撤去をおこないましょう。
通報・相談先一覧

健康食品販売に関する法令違反や表示の問題が発覚した場合、速やかに適切な機関に相談しましょう。主な相談窓口は以下の表を参照してください。
| 機関名 | 相談内容 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 消費者庁 消費者ホットライン | 商品表示や健康被害に関する相談 | 188(局番なし) |
| 各都道府県 薬務課 | 薬機法違反に関する相談 | 各都道府県窓口 |
| 各保健所 | 食品表示や健康被害に関する相談 | 地域の保健所窓口 |
| 消費生活センター | 商品トラブル全般の相談 | 188(消費者ホットラインと共通) |
登録販売者は、自己判断で問題を抱え込まず、外部機関への連絡を迅速におこなうことが重要です。番号を控え、すぐに連絡が取れるように準備しておきましょう。
FAQ|【登録販売者向け】健康食品販売時によくある質問

健康食品を販売する場面では、お客さまからさまざまな質問を受けることがあります。とくに登録販売者は、OTC(一般用医薬品)と混同されやすい商品を取り扱うことが多いため、説明の仕方に注意しなくてはなりません。
ここでは、健康食品販売時によく寄せられる質問と答え方について簡単にまとめました。
Q1 登録販売者でも健康食品の説明はしていいの?
登録販売者は健康食品の基本的な説明ができる立場にあります。ただし、OTC(一般用医薬品)的な効能効果は説明してはいけません。必ず「効果には個人差があります」と伝え、事実に基づいた情報のみを説明しましょう。
Q2. 健康食品の販売で、とくに気を付けるべきことはありますか?
OTC(一般用医薬品)と誤認される表現や、根拠のない情報を使ってはいけません。口コミや「私の経験では」という話は使わず「あくまで一例です」と伝えるよう心がけてください。
Q3. 体験談は使っちゃダメ?
個人の体験談を販売現場でそのまま使用するのは適切ではありません。「私もこれでよくなりました」という表現は避け「効果には個人差があります」と伝えましょう。
まとめ|健康食品販売は正しい知識と慎重な対応が信頼につながる
健康食品の販売は、登録販売者にとって身近でありながら法令違反のリスクを常に伴います。OTC(一般用医薬品)的な表現を使わず、根拠のある情報だけを正しく伝える姿勢が必要です。そのため、正しい商品知識と判断方法を身につける必要があります。
もし問題が発生した場合は、お客さまへの迅速な対応と店舗全体での再発防止策を徹底しましょう。ぜひ本記事を参考にして健康食品の販売に役立ててください。
【新着】登録販売者のための業界コラム
- 2026年01月09日 【現役ドラッグストア店長直伝】登録販売者が「辞めたい」と思わない3つのメンタル維持法(2026年対策付き)
- 2026年01月07日 2026年ドラッグストア業界の未来図|市場動向・M&A・登録販売者のキャリアと転職のポイント
- 2026年01月07日 登録販売者の年収は低い?現場にインタビューしてリアルな声をお届け!平均給料を調査
- 2026年01月07日 ドラッグストア店長の年収はいくら?平均額の内訳と600万円を目指す昇給のコツ
- 2025年12月03日 【現役ドラッグストア店長直伝】冬商品で接客スキルを劇的に磨く3つのコツ







