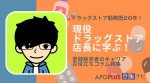【現役ドラッグストア店長直伝】初年度からできる濫用等のおそれのある医薬品対応<登録販売者のキャリア>

このコラムが掲載される頃には今年登録販売者試験に合格した皆さんが店頭で活躍し始めていると思います。
資格取得直後から半ば強制的に始まるのが「濫用等のおそれのある医薬品」対応です。
このコラムでも何回かとりあげましたが、今回は資格取得直後から対応できるよう実践的な解説をしますのでぜひ参考にしてください。
目次
「濫用等のおそれのある医薬品」対応を疎かにするとどうなるか

資格を取得し店舗でお客さま対応をおこなう中で「濫用対応」は様々な業務上の問題点が存在します。
この問題点を考えながらどう対応したらいいか探っていきましょう。
お客さまの納得の有無にかかわらず守るべきこと
通常の接客と「濫用対応」の大きな違いは「タイミング」です。
接客はお客さまが買い物をしている途中におこなうため話をする余裕がありますし、お急ぎのお客さまは接客を断ったりすることができます。
しかし「濫用対応」はお客さまがお急ぎの場合においても必ずおこなわないといけないうえに、お声がけも基本的に「レジ会計時」です。
お急ぎの方も多いですし「会計が終わって帰る」というタイミングで引き止められるのはお客さまにとって大きなストレスとなってしまいます。
この対応を誤るとクレームの原因になりかねませんし、かといって疎かにすると法令違反となってしまいます。
また後述しますが、お客さまにとってのQOL低下リスクを排除するタイミングを逸することになってしまいます。
お客さまがお急ぎなことやお声がけにご理解いただくことと法令順守は別問題なので混同してしまわないよう注意が必要です。
登録販売者が考えるべきポイントは「法令順守」「お客さまに納得していただく」の二点となるので、順に解説していきます。
法令違反の可能性がある
当然のことながら決められたルールを逸脱することは法令違反となります。
ただ「濫用対応」は実施したかどうかという判断は非常に線引きがし辛く、実施したつもりでも受け手によってはそうではない場合もそります。
2024年9月に厚生労働省からこのような発表がありました。
「医薬品販売制度実態把握調査」の結果を公表します
ニュースで報道されたためご覧になった方もいるかと思います。
この調査は要指導医薬品や第1類医薬品販売を含むOTC(一般用医薬品)の販売実態調査ですが、一部店舗でルールが守られていない現状が見受けられるようです。
店舗によって様々な問題や課題はあるかと思いますが、法令順守は何よりも重要です。
これは医薬品販売以外でも同じことです。
タクシー運転手を例にあげてみましょう。
- お客さまがお急ぎなので国道を時速90kmで走行した
- タクシー乗り場に行列ができているので急いで一旦停止を無視して向かった
- 面倒なので会社に提出義務のある乗車記録を出さなかった
どうでしょう、文章にすると専門外のわたし達から見ても「アウト」とわかりますね。
このような運転手に遭遇したらこう思いませんか?
急いでほしいのは確かだがそんなに飛ばして大丈夫なのか...?
タクシー乗り場で待っていて目の前に交通ルールを破ったタクシーが来たら...?
車の暴走や交通ルールの軽視はほとんどの方が危険性を理解できますが薬のリスクへの理解は人それぞれなので、わたし達がある程度のリテラシーを持って対応する必要があります。
そして目の前のお客さまは「薬のことを知らない」という前提で対応をおこなわないと、漏れが生じて健康被害が発生する可能性があるのです。
わたし達は毎日売場に立っています。
そのため「販売者目線」になってしまっているのを忘れてはいけません。
大多数のお客さまにとって「濫用対応」はそこまで大きなストレスではありません。
販売者からすると「こんなことを聞いて迷惑かもしれない」という考えも出てきますが、これが販売者目線なのです。
堂々と毅然とした態度で「濫用対応」はおこなってください。
何よりも、この対応はお客さまの健康を守る対応なのですから。
リスクを伝えられない可能性
さきほどのリンク先に調査員がOTC(一般用医薬品。第一類医薬品を除く)を購入する前に専門家へ相談せずに購入するケースでの店舗の対応を調べたデータもありました。
「医薬品購入前に薬剤師・登録販売者から声をかけられた」...276件中3件
「レジで薬剤師または登録販売者に相談してから会計をするよう言われた」...276件中3件
「薬剤師・登録販売者の説明が必要か聞かれ「必要ない」と答えるとそのまま売ってくれた」...276件中1件
参考:「⑤ 購入時に対応した者の資格(図表Ⅱ-26 購入しようとした際の対応) 」令和5年度医薬品販売制度実態把握調査 調査結果(報告書)|厚生労働省
これらの項目の数値をみると、理想と現実の乖離がリアルに伝わってきます。
思いのほか、法令違反をしていたりお声がけできていない現実が数字として現れているので、皆さんも自身の店舗の状況と照らし合わせてください。
おそらく「やっているつもり」でも客観的に見たらできていなかったり、「業務の多忙さ(人員不足)」も一因としてあるはずです。
しかしだからといって法令違反をしてもいい口実にはなりません。
どんな事でも優先順位は以下の通りです。
- 法律
- 会社規則
- 店舗(お客さま)都合
タクシードライバーはお客さまに「急いでいるから速度違反しろ」と言われても法定速度を守らないといけません。
なぜなら、違反をした責任は運転手(販売員)となるからです。
接客テンプレートを覚えてしまおう

ではここからは「明日からできる濫用対応」を解説していきます。
各社でマニュアルは決まっているはずなので必ず守ったうえでお客さま対応をおこなってください。
法令に基づく声掛けを最初に申告する
実際に登録販売者がクレームなどを受けてしまうのは明らかにお客さまとの「認識のズレ」です。
クレームが起こる原因はお客さまが「法令で定められている」と知らないからであることが多々あります。
これは報道機会が少ないなどの理由があるので、お客さまは知らなくて当然です。
毎日対応していたり情報に触れていると「無知=悪」などという間違った認識になりやすく、態度にも出てしまうので充分注意してください。
まず「濫用対応」をおこなう際には「理由」から説明します。
ここでの理由は作用などの話ではなく、「法令順守」です。
「こちらのお薬は『濫用等のおそれのある医薬品』に指定されていますので、法律に基づき確認させていただきます」
この一言を添えるとお客さまは「これから始まる確認は法律を守ること」と理解できるため、クレームや不満にはなりにくいのです。
もちろんゼロにはなりません。
明らかに不満を感じているお客さまもいらっしゃいます。
「わたし達はお客さまが安全にOTC(一般用医薬品)を使用できるよう、法律に基づき確認する」というスタンスを強く持って対応に当たってください。
真摯に対応をおこなえばクレームや不安は激減します。
お客さまにとってリスクが高くなる可能性の説明
そして濫用対応をおこなううえでもっとも大きなメリットは「強制的な接客」です。
濫用対応をおこなわなかったらお客さまが自身で選び非資格者がレジをおこない販売していた商品も、法律で強制的に接客がおこなえるのです。
すでに登録販売者として経験を重ねている方なら共感していただけるはずですが、想像以上に「禁忌」を犯してOTC(一般用医薬品)を使用されているお客さまは多いのです。
市販薬依存を未然に防ぐゲートキーパーとしての役割が表面上の目的ですが、このタイミングで「禁忌」の確認をおこなうと思いのほか意識せずに使用しているお客さまが多いのが現状です。
わたしの店舗では必ず「禁忌」の確認もおこなうよう意識付けをしていますが、クレームは起きていませんし客数や売上のダメージもありません。
自店から防ぐことのできた健康被害を起こさないよう「禁忌(次の人は服用しないでください)」の確認はおこなってください。
ツールの使用とマニュアル遵守
濫用対応時に使用するツールが準備されている会社もあるはずですが、この場合は必ずマニュアル通りに使用してください。
理由は二点、順に説明します。
- お客さまに理解していただくため
まず大多数のお客さまは店員の発言を聞いていません。
また、店内掲示物も必要と思うもの以外はみていません。
これは自分自身が客の立場で自店以外の店舗におこなった時の事を想像するとわかるはずです。
お客さまは自身が求めている情報以外は、ほぼ見ていないですし聞いていません。
お客さまの目と耳、両方に訴求することでコミュニケーションをとってください。
ツール使用時は手で指し示すなど、動きを伴うことで訴求力が上がります。
- 万が一の時に登録販売者個人が責任を負うことを避けるため
そして万が一の時の責任の所在を明らかにするためにもツール使用は必須です。
万が一、というのは「お客さまの健康」と「クレーム」です。
これらのトラブルが発生した際に、登録販売者の身を守る盾となるのがツールであり、マニュアルです。
店舗でのトラブルで従業員に責任が及ぶのはほぼマニュアルから逸脱したことによるミスです。
「意味がない」「時間がかかる」「見られていない」というのは勝手な思い込みであり、「盾と鎧は重くて走れない」と裸で戦場に行くようなものです。
必ずマニュアルに沿ってツールを使用してください。
正攻法こそもっとも安全な運営方法
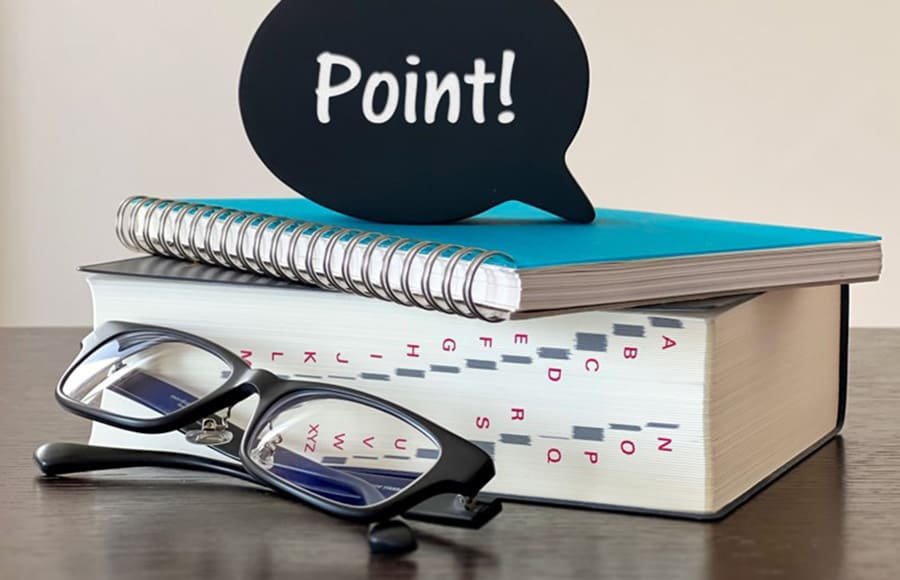
では円滑に、安全で、クレームが少なく、万が一の時も自身が不利益を被らない濫用対応を紹介していきます。
おそらく登録販売者初年度でもっとも抵抗感がある分野だと思いますので、ここを抑えて対応に当たってください。
論点ずらしの意見に惑わされてはいけない
まず意識からですが、同じ店舗で働く非資格者を含む従業員やネットの意見に流されてしまう登録販売者が多く見受けられます。
「風邪薬の確認は意味がない」「確認しても結局販売するのだからから意味がない」「依存の人は複数店舗で購入するから意味がない」などは一見正当性がありそうな意見ですが、デメリットが多いのです。
わたしもそうですが、日々の業務は多岐にわたっていることから濫用対応は生産性や売上だけを考えたら「余計な業務」と感じてしまいます。
業務を途中で切る横槍のように感じてしまうのも理解できます。
ただ、ここで「意味がないから簡略化しよう」という考えだけはしてはいけません。
それは自動車運転で「どう見ても車は来ない」という理由で一旦停止をしないのと同じことです。
先ほども述べたように、万が一の事態になった時の責任の所在や事態収拾するための労力、時間的な損失、お客さまからの信頼、会社自体へのダメージなど、わたし達が考えるよりも莫大なデメリットが存在するのです。
接客テンプレートまとめ
では接客のテンプレートです。
業務の生産性や説明品質の均質化のため、わたしの店舗では次の①~⑤の接客テンプレートで統一した対応をしています。
非常に多忙な店舗ですが、対応でのクレームはゼロです。
テンプレートのうち①②は、わたし達が業務の実情を鑑みて、厚生労働省の指定する確認事項に追加した項目です。
①法律上決められたお声掛けであることを告知

- トーク例:
「こちらのお薬は『濫用等のおそれのある医薬品』に指定されていますので、法律に基づき確認させていただきます」
必ず「法律に基づく確認をおこなう」と告知してください。
②「濫用等のおそれのある医薬品」成分の説明

- トーク例:
「こちらの風邪薬には『咳止め成分で2種類』濫用等のおそれのある医薬品に指定されている成分が配合されています」
確認の名目は理解してもお客さまの立場だと何が問題なのか分かりません。
必ず「濫用等のおそれのある医薬品」に該当する成分の症状を説明してください。
もしこの時点で該当成分の症状がなかったら安全性の高いOTC(一般用医薬品)に変更も可能です。

- トーク例:
「発熱や痛みだけなら解熱鎮痛剤で充分対応可能でリスクも低くなります」
③年齢確認

- トーク例:
「こちらの薬を使用するのはお客さまを含め19歳以上の方ですか?」
厚生労働省の指定は年齢確認だけですが、家族で使用することも考え「お客さまを含め」と追加しています。
そして「購入者が子ども(中学生・高校生)」と厚生労働省の指示にはありますが、具体的に19歳以上かの確認をおこないます。
④複数購入の確認

- トーク例:
「他の店舗やインターネットで同じ効果の市販薬、風邪薬、鼻炎薬、咳止めなどを購入したり使用していませんか」
お客さまの中にはOTC(一般用医薬品)に複数の成分が配合されているということを知らない方も多いため、具体的に商品ジャンルをあげて確認してください。
中には病院で処方された鼻炎薬を使いながら総合風邪薬を使われる方もいるため、ここを逃すとお客さまの健康被害につながりかねません。
⑤長期使用の有無

- トーク例:
「こちらの薬や似たような薬を繰り返し使用していませんか」
複数購入をしなくても頻回購入される方もいらっしゃいます。
また同じ薬でなくても類似するOTC(一般用医薬品。同成分)を購入される方もいらっしゃいます。
「この咳止めで治らないから違う咳止めに変える」というパターンや、通年性のアレルギーで第1世代抗ヒスタミン薬を続けて服用される方の中にはリスクを知らない場合も多いため、ここで確認をおこないます。
お客さまの希望するOTC(一般用医薬品)の代替品がない場合、そもそもその症状がOTC(一般用医薬品)では対応できない可能性もあるため受診勧奨をおこないます。

- トーク例:
「その症状だと市販薬を使い続ける事でデメリットがメリットを上回ります。市販薬ではなく受診していただくのがお勧めです。」
まとめ
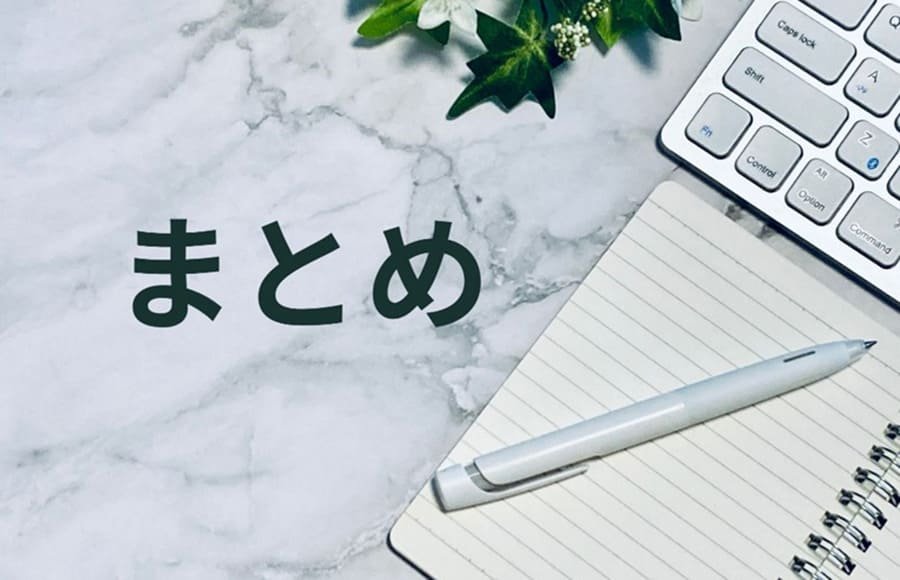
では今回学んだことをまとめながら振り返りましょう。
- 「濫用等のおそれのある医薬品」への対応は、資格取得直後から必ず向き合うことになる業務
どんな多忙な店舗でも登録販売者が最優先で行う必要があるのが「濫用対応」です。
これはどんな初心者タクシー運転手でもお客さまを乗車させるのと同じことで、登録販売者として必須の業務です。
登録販売者として勤務する以上は必ずおこなわなければいけないのでポイントを把握して対応してください。
- お客さまの健康と自身を守るためにも、このテンプレートは必須
「濫用対応」には厚生労働省が定めたテンプレートがあります。
これに沿って対応することで万が一の事態でもお客さまと登録販売者自身を守ることができるのです。
毎日の業務は多いですが、最重要と位置づけて対応しなければいけません。
- 慣れるとスムーズに対応できる
最初は慣れない業務のため大変なはずです。
しかし数をこなすことで必ずスムーズな対応ができるようになります。
お客さまの健康と、自身を守るためにもこのテンプレートは必須と考えています。
慣れるとスムーズに対応できるので、ぜひ毎日の対応に活かしてください!

執筆者:ケイタ店長(登録販売者)
ドラッグストア勤務歴20年、一部上場企業2社で合計15年の店長経験を活かし、X(旧Twitter)などで登録販売者へのアドバイスや一般の方への生活改善情報の発信を行っている。X(旧Twitter)フォロワー数約5,000人。
【新着】登録販売者のための業界コラム
- 2026年01月09日 【現役ドラッグストア店長直伝】登録販売者が「辞めたい」と思わない3つのメンタル維持法(2026年対策付き)
- 2026年01月07日 2026年ドラッグストア業界の未来図|市場動向・M&A・登録販売者のキャリアと転職のポイント
- 2026年01月07日 登録販売者の年収は低い?現場にインタビューしてリアルな声をお届け!平均給料を調査
- 2026年01月07日 ドラッグストア店長の年収はいくら?平均額の内訳と600万円を目指す昇給のコツ
- 2025年12月03日 【現役ドラッグストア店長直伝】冬商品で接客スキルを劇的に磨く3つのコツ