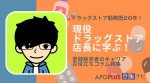【現役ドラッグストア店長直伝】市販薬を安全に販売するためのシンプル思考<登録販売者のキャリア>

新しく登録販売者として店頭デビューした皆さま、そして新人登録販売者さんの所属店舗の皆さま、実際に勤務してみてどうでしょうか。
お客さまからの要望と登録販売者としての責任の間で板挟みとなり、うまく販売できなかったり自信を失ったりしていないでしょうか。
おそらくほとんどの方が「思いのほか厳しい」と感じているはずです。
今回はお客さまとの接客の中で登録販売者の方が陥りやすい思考を例にあげながら、トラブルを避けることができるシンプルな考え方を解説していきましょう。
目次
登録販売者としての責務とお客さまの要望

登録販売者として店頭に立つということは「責任」が発生する、ということです。
そしてその責任感こそがお客さまを守ることになるのですが、過剰に意識すると逆にお客さまに迷惑をかけることになってしまいます。
ここでは「バランスのとり方」を考えてみましょう。
責任感を優先しすぎてしまう失敗例
OTC(一般用医薬品)にはメリットとデメリットがあり、わたし達が強く意識しなければいけないのは「デメリット」です。
お客さまが自店で購入した商品で、説明不足が原因の健康被害は避けなければいけません。
わたし達の責務は効果の有無より、トータルで考えて「お客さまのQOLを向上させること」です。
このため副作用を含めたデメリットを説明するのは最低限の義務です。
特に禁忌事項は確認必須となりますが、例えば9割以上の風邪薬は「機械類の運転操作」が禁忌事項となります。
こうなると特に郊外立地の店舗は風邪薬の販売が大きく落ち込んでしまいます。
ではお客さまに確認しなくてもいいかといえば、決してそんなことはありません。
交通事故などで間接的に第三者の健康を害することにつながりかねないからです。
とはいえ、すべて聞いていると販売するものがなくなってしまいます。
完全にヒアリングをおこない健康被害の可能性を完全に排除しつつ販売をおこなうと、販売成績が大きく下がってしまいます。
ではどうしたらいいのだろう...
これは登録販売者の大きな悩みの一つだと感じています。
ヘルスリテラシーのバランス感
お客さまの中には持病があっても全くOTC(一般用医薬品)に抵抗がない方や、たとえビタミンCの単剤であっても「医薬品」表記であるだけで忌避感を示される方もいらっしゃいます。
これを「ヘルスリテラシー」と呼びます。
このコラムを読んでいただいている登録販売者の方々は特に強く感じると思いますが、ヘルスリテラシーというのはお客さまによって大きく差が出るのです。
タクシーやバスなど、ドライバーによって運転の安心感が大きく異なるのと似ています。
「この人やたらスピードを出すな、早く着くからいいけど大丈夫だろうか...」
このように感じさせてしまう交通機関のように、こう思われた時点でお客さまは店舗から離れてしまいます。
だからといってお客さまの要望通りに販売していると健康被害が起こる可能性が高くなるため、悩ましいところです。
目の前のお客さまが副作用リスクをどう捉えているかは全くわからないのです。
ではお客さまの感覚を知るテクニックは存在するのでしょうか。
残念ですが存在せず、人間関係と同じで安全策を探すしかありません。
ただわたし達、登録販売者のリスクリテラシーはある程度の基準を設けておかなければいけません。
当然、人によって感覚は違いますからプライベートでは違ってきて当然です。
しかし業務上では健康リスクを追うのは自分ではなくお客さまです。
ご自分に対して医薬品に対するリスクを甘めにしている方も、業務上では登録販売者として意識を切り替える必要があるのです。
お客さまに判断を委ねるタイミング
お客さまの基準がわからない以上、ある程度の基準を設けて接客に当たる必要があります。
基準というものは明文化され、誰もが理解できるものでなくてはいけません。
OTC(一般用医薬品)での基準は、添付文書です。
特に未購入でも誰もが確認できる外箱に記載の「使用上の注意」はお客さまと共に確認できる優秀なツールであり、絶大な説得力を持ちます。
冒頭の例のように「ヘルスリテラシー」が極端に偏っている方にも基準を明文化して提示すると説得力が増します。
接客後半で確認するとそれまでの接客内容がすべて無意味になる可能性もあるため、この確認は必ず最初におこなう必要があります。
できるだけシンプルに考える

お客さまの悩みを解消するうえで極力デメリットは少なくしたいものです。
登録販売者の中には接客の中でパニックになってしまう方も多いので対処法を考えていきましょう。
推奨品中心に考えない
登録販売者として会社から求められているのは営業面では「推奨品販売」です。
会社としては効果が高く特徴的な商品を購入していただくことでリピーターを生み出そうと推奨品の販売に力を入れています。
ですが、推奨品の中には知識が充分になかったり、副作用や依存など健康被害の可能性を考え出すと勧めにくいものも存在します。
そして何よりも最大のデメリットはお客さま中心ではなく推奨品中心の接客になりかねないことです。
各社で従業員の教育方針は違うでしょうが、わたしの店舗では初年度は推奨品の販売を一切考えずに柔軟に対応するよう教育しています。
その分、推奨品販売は既存の登録販売者が接客回数を増やすことでフォローしています。
こうした「お客さま中心の接客」を心がけることでお客さまの立場で考えることが可能となり、混乱を避けることができるのです。
既存の登録販売者の方はこの面でも新人登録販売者をフォローしていただけると店舗力の向上につながりますので実践してみてください。
成分の種類が少ないものを選ぶ
特に冬は風邪薬や年末年始疲れからくるビタミン剤の接客回数が増える季節です。
これらのOTC(一般用医薬品)は成分の種類が多く、特に風邪薬はリスクが高くなるので注意が必要です。
皆さんご存じの通り薬は必要な成分のみを選ぶ必要があります。
しかし風邪薬にはものによっては10種類程度の成分が配合されており、こうした製品は効果が高いため人気ですが副作用も多い傾向があります。
これまでのコラムでもお伝えしたとおり副作用リスクを小さく考えるお客さまも多く、特に持病をお持ちの場合は伝え方に苦労する場面が多いのもこの季節の特徴です。
年末年始は自動車運転をする方も多いため注意してください。
このため、リスクが少ないOTC(一般用医薬品)をあらかじめ覚えておくのがお勧めですが、特に重点的に「解熱鎮痛剤」「風邪薬」はおさえておきましょう。
どちらも下記をおさえておくと対応しやすくなります。
・機械類の運転操作
年末年始に多い「自動車運転」が禁忌となるものです。
解熱鎮痛剤は「催眠鎮静剤未配合」のものは暗記しておきましょう。
風邪薬では9割以上の商品が禁忌となるため、抗ヒスタミン剤などが未配合の風邪薬や漢方薬をおさえておきましょう。
意外なところではPB正露丸など抗コリン成分で自動車運転が禁忌となっている商品も存在します。
・高血圧、糖尿病など
持病の禁忌は特に注意が必要です。
特に解熱鎮痛剤や風邪薬でイブプロフェンが高濃度のものは見逃しがちですので細心の注意を払ってください。
そして風邪薬でもこれらの持病が「してはいけないこと」なのか「相談すること」なのか、しっかり確認しておきましょう。
最近はリスクが低めの風邪薬も発売されているので新商品も確認しておくと接客の幅が広がります。
当然これらのジャンルでは成分が少なくなれば禁忌となる確率も低くなりますし、お客さまの症状も少なければ商品の選択肢も絞られてきます。
登録販売者側としては成分の種類が少なく禁忌がない薬を把握し、お客さまが望んだ場合はそれらの組み合わせで対応することも可能です。
そのためにはトローチ剤やのどスプレー、鼻うがいのような補助的なものも紹介できるようにしておきましょう。
最終的にはお客さまに選んでいただく
お客さまに提案する時は「お客さまに選んでいただく」ことがポイントです。
できれば2〜3種類の選択肢を提示すると納得していただけます。
(例)のどの痛みと咳の場合
「抗ヒスタミン剤フリーの風邪薬」か「咳止め+催眠鎮静剤フリーの解熱鎮痛剤」
後者の場合は「症状が出ているときだけ使用して下さい」とアドバイスするとお客さまも安心して使用できます。
どちらもメリットとデメリットが存在しますし、コスト面でも大きな差が出る場合があります。
咳止めはトローチなどで代替できる場合も多いので、お客さまの生活様式にあわせて提案をおこなってください。
デメリットを含めた選択肢を提示しお客さまに最終判断していただくことで納得して購入していただけますし、万が一の時のクレームも起こりにくくなります。
市販薬を安全に販売するための基本的な思考法

では登録販売者が常に持ち続けるべき思考法をまとめていきましょう。
皆さんも自身の考えのもとは何かを考えてみてください。
完璧は存在しない
OTC(一般用医薬品)や体の構造を学んだ登録販売者の中には思考が完璧主義に近い方もいると思います。
わたしもそれに近いのでわかるのですが、この思考にもメリットとデメリットがあるので自覚できる方は注意してください。
そもそもOTC(一般用医薬品)は消費者自身が選択し購入、使用できるよう販売されている医薬品です。
ここで過度に登録販売者が販売をおこなわない判断をしてしまうとセルフメディケーションの流れもせき止めてしまいます。
最終的な使用の可否はお客さまにお任せし、デメリットをお伝えしたうえでアドバイスをおこなうのが理想です。
この「使用の可否」が今までお話してきた内容なのですが、中には完全に禁忌の内容なのに購入を迫ってくるお客さまもいらっしゃいます。
シチュエーションはさまざまなので必要に応じて販売拒否することも選択肢の一つですが、やみくもにお断りするのではなくデメリットをお伝えしたうえで販売する場合もあります。
使用者が明らかに禁忌に当てはまるのなら販売拒否すべきですが、ある程度の説明をおこなったあとで販売することでお客さまのQOLが向上することがあります。
(例)
- 就寝前のみ使用
- 休日のみ使用
- 使用時は公共交通機関をつかう
お客さまが理解、納得したうえで販売をおこなうことで健康被害を防ぐことができます。
接客の重要性
なぜ「接客」が必要なのでしょう。
それはお客さまにOTC(一般用医薬品)のメリットとデメリットを説明する必要があるからです。
「説明」が必要なのは専門知識が不足しているお客さまがOTC(一般用医薬品)のデメリットを把握しきれていないからであり、「デメリット」が把握されていないのはデメリットを知る機会が少なすぎるからです。
つまりCMや広告を見たり症状が現れて店頭で商品を手に取りパッケージを手にする過程で、デメリットについてほとんど触れることがないからなのです。
外箱の注意欄や添付文書に記載はありますが意識して読んでいる方はわずかです。
つまり接客なしのセルフ販売だと「濫用のおそれのある医薬品」以外は禁忌の医薬品をお客さまが知らず知らずのうちに使用している可能性が高いのです。
接客を重点的におこなっているといかに禁忌事項を知らずにOTC(一般用医薬品)を使用しているお客さまが多いかわかります。
これは接客を重ねてきて感じた個人的な意見ですが、「濫用等のおそれのある医薬品」の依存リスクよりも接客を介さずに禁忌事項を犯すリスクの方が絶対数としては圧倒的に多いと感じます。
このことからも、シンプルな配合のOTC(一般用医薬品)の方がリスクは少ないうえに登録販売者側としてもシンプルな思考で接客をおこなうことができるのです。
理想的な店舗とは
では理想的な店舗とはどんな店舗なのでしょうか。
ドラッグストアは企業なので利益を生み出すことが目的なのは当然のことです。
しかしその目標を達成させる手段を間違うと売り手主体の店舗になってしまいます。
理想的な店舗とは、お客さまと店舗が「WIN - WINの関係」になる店舗です。
登録販売者が広い知識を持ち、そのお客さまにとってメリットが大きくデメリットが小さいOTC(一般用医薬品)を提供することです。
そこを目標とするならば、ステップとしては「シンプルな処方のOTC(一般用医薬品)から学んでいく」ことが最適解だと考えています。
わたしの店舗でも登録販売者1年生が数名誕生し、教育を始めています。
このコラムをお読みの登録販売者1年生の皆さん、該当店舗に所属の皆さんもシンプルに考えてみませんか?

執筆者:ケイタ店長(登録販売者)
ドラッグストア勤務歴20年、一部上場企業2社で合計15年の店長経験を活かし、X(旧Twitter)などで登録販売者へのアドバイスや一般の方への生活改善情報の発信を行っている。X(旧Twitter)フォロワー数約5,000人。
【新着】登録販売者のための業界コラム
- 2025年12月03日 【現役ドラッグストア店長直伝】冬商品で接客スキルを劇的に磨く3つのコツ
- 2025年11月21日 現役薬剤師が教える。登録販売者の新人教育マニュアル|OJTの進め方と後輩指導のコツ
- 2025年11月21日 現役薬剤師が伝授|インフルエンザ時に使える解熱剤の見分け方と登録販売者の声かけ技術
- 2025年11月06日 【2026年法改正で必須!】現役店長が教える「OD対策」現場対応完全ガイド 〜登録販売者が押さえるべき「3大変更点」と心構え〜<登録販売者のキャリア>
- 2025年10月30日 登録販売者はブランク後も復職できる!管理者要件と安心して働くためのポイント