【完全ガイド】登録販売者が独立開業するには?手順と必要条件を解説

こんにちは、登録販売者転職のアポプラス登販ナビライターチームです。
登録販売者は、第二類と第三類のOTC(一般用医薬品)を販売できる専門資格であり、独立開業を目指す方にとって大きなチャンスを広げてくれるものです。本記事では、登録販売者が独立開業するために必要な資格、実務経験、手続きの流れについてわかりやすく解説します。
登録販売者として独立開業したいけれど何から始めればよいのかわからずお悩みの方は、この記事を読めば、店舗を構えるまでの具体的な準備や条件を把握し、開業に向けた第一歩を踏み出せるようになります。ぜひ不安の解消とビジョンの明確化に、本記事をご活用ください。
【この記事で得られること】
- 登録販売者の独立開業は準備のハードルが高い一方、自由な働き方と店舗運営が実現可能
- 登録販売者の独立開業は、個人とフランチャイズの2パターン
- 独立開業のステップは「店舗管理者の設置」→「独立開業に必要な手続き」
- 登録販売者資格でネット販売のみの独立開業はできない
- 登録販売者の独立開業には、資格と一定の実務経験が必要
目次
- ・登録販売者が独立開業するには?
- ・登録販売者として開業するメリット
- ・登録販売者として開業するデメリット
- ・登録販売者が独立開業する2つのパターン
- ・独立に向けての手順
- ・独立開業に向いている人の特徴
- ・成功するための方法
- ・登録販売者資格でネット販売のみの独立開業はできない
- ・独立開業には資格や業務経験が必要
- ・まとめ|登録販売者の独立開業は正しい準備が成功の鍵
登録販売者が独立開業するには?

登録販売者として独立開業するためには、まず資格を取得し、一定の実務経験を積まなければなりません。そのうえで、店舗の準備や開業に必要な手続きをおこないましょう。
登録販売者の資格は、OTC(一般用医薬品)を取り扱える資格であるため、独立を目指す方にとって非常に価値が高いといえます。ただし、すべてのOTC(一般用医薬品)を販売できる薬剤師とは異なり、登録販売者が取り扱えるのは第二類と第三類のOTC(一般用医薬品)のみです。
とはいえ、OTC(一般用医薬品)の種類は豊富であるため、ドラッグストアや薬局で見かける身近な商品はほとんど販売できるでしょう。
調剤薬局の独立開業をするには「保険薬局の指定」や「薬局開設許可」を取得しなければなりません。さらに、店舗には調剤室を設ける必要があります。開業にあたっては、事前に医薬安全課や保健所へ相談し、必要な手続きを確認しておきましょう。
登録販売者として開業するメリット

独立開業する場合の大きなメリットは、収入アップや自分の理想に沿った店舗づくり、自由度の高い働き方を実現できることです。
店舗運営が軌道に乗れば、企業に雇用されて従業員として働く場合の給料の、何倍もの収入を得ることが可能になります。
また店の造りや、取り扱う商品なども自分自身で決めることができ、自分が思い描くコンセプト通りの店を作れるのも魅力的なポイントといえます。さらに、接客スタイルや営業時間など、働き方もすべて決められる点が独立開業ならではの特徴です。
登録販売者として開業するデメリット

独立開業するデメリットとしてもっとも大きいのは、準備や手続き、資金調達のハードルが高い点があげられます。
店舗の確保や仕入れなどの開業準備として、開業資金は数千万円程度必要になることも多く、事業計画を立てたうえで銀行に融資の相談をすることになります。
扱う医薬品の仕入れ先や価格交渉など、それまでおこなったことがないであろう初めての取り組みも多く、開業にこぎつけるまではかなりの負担になります。
登録販売者が独立開業する2つのパターン

登録販売者が独立開業するパターンは「個人で独立開業」と「フランチャイズで独立開業」の2つに分類されます。それぞれの特徴を解説します。
個人で独立開業する
登録販売者が個人で独立開業を目指す場合、開業に向けて必要な準備を段階的におこなうことが大切です。個人で店舗を開業するときは、主にドラッグストアやOTC(一般用医薬品)を扱う小規模な薬局を選ぶケースがほとんどです。
開業までの流れは「資金の準備」→「出店場所の確保」→「従業員の採用」→「仕入れ先の確保」→「販売設備の準備」→「出店に必要な各種手続き」の順で進めましょう。一つひとつの準備を丁寧におこなうことが、スムーズな独立につながります。
資金の準備
店舗を出店するためには、物件の確保や商品の仕入れなどに使用する、まとまった資金が必要となります。開業資金は物件取得費を除くと、1,000万円〜2,000万円前後の費用が必要といわれています。
出店場所の確保
店舗を出店する場所を確保します。また新しく店舗を建てる場合は、物件面積や駐車場のスペースを決めることも必要です。
従業員の採用
店舗経営にあたり、正社員やアルバイト、パートの従業員を採用します。
仕入れ先の確保
登録販売者として販売できる、OTC(一般用医薬品)の仕入れ先を見つけます。
販売設備の準備
陳列棚やカゴ、各種備品など、店舗運営に必要なものを揃えていきます。
出店に必要な各種手続き
その他、出店に必要な営業許可証の手配など、手続きを進めていきます。
フランチャイズに参加して開業する
もう1つの独立開業の方法は「フランチャイズに参加して開業する」方法です。フランチャイズとは、大手企業などが培ってきたノウハウを借りて、独立開業できる方法のこと。個人で独立開業するよりもリスクを抑えることが可能です。
フランチャイズを展開している企業に対して加盟金を支払い、運営している期間は売上の一部を納めることで、大手のノウハウ等を借りて独立開業できます。 この方法で独立する際には「コンビニ・ドラッグストア・薬局」などで、フランチャイズを募集している企業があるのでチェックしてみましょう。
フランチャイズの事例
例えば大手コンビニエンスストアのローソンでは、インターン制度として、登録販売者の独立開業に向けたフランチャイズを設置しています。コンビニなどのフランチャイズ制度を使えば、大手が培ったノウハウをもとに、リスクを抑えて独立開業することができます。
フランチャイズの開業費用
小規模であればおおよそ数百万円、規模が大きくなると3,000万円前後までになります。少ない資金で始められるのは、フランチャイズのメリットです。開業費用には以下のようなものが含まれます。
- フランチャイズ加盟金
- フランチャイズ保証金
- 店舗関連費
- 調剤機器・医薬品の購入費
- 広告宣伝費など
これはあくまでも目安で、規模の小さい薬局やドラッグストアであれば、必要な開業費用はもっと少なくなります。
独立に向けての手順
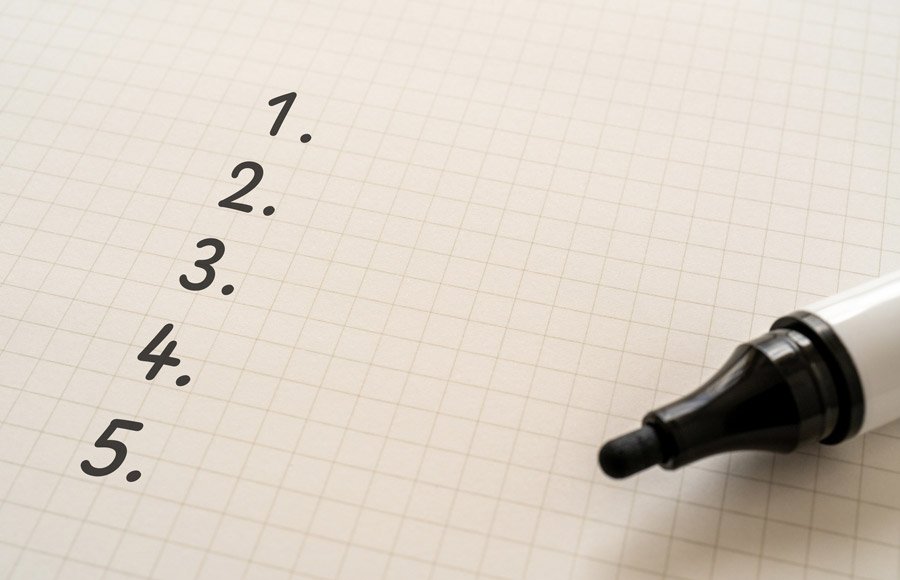
登録販売者として独立開業するには、正しい手順を踏まなければなりません。具体的な流れは「店舗管理者を設置する」→「独立開業に必要な手続きをおこなう」の2ステップです。ここでは独立に向けての手順について詳しく解説します。
店舗管理者を設置する
まず、登録販売者として店舗を独立開業する場合、店舗管理者を必ず設置しなくてはなりません。店舗管理者になるには、下記条件を満たす必要があります。
- 過去5年間のうち、薬局等における従事期間の合計が通算して2年以上である
- 過去5年間のうち、従事期間の合計が通算して1年以上の者であって、継続的研修・追加的研修を修了している
- 従事期間が通算して1年以上であり、過去に店舗管理者又は区域管理者として業務に従事した経験がある
もし自分自身で店舗管理者の要件を満たしている場合、この手順はスキップ可能です。一方、自分自身が条件を満たしていない場合、店舗管理者の要件を満たす薬剤師または登録販売者を雇用しましょう。
このように、独立開業するには自分自身が店舗管理者になるか、店舗管理者の人を雇用するかのどちらかが必要です。どちらでも問題はありませんが、独立開業する場合は自分自身を店舗管理者として登録するのがおすすめです。
独立開業に必要な手続きをおこなう
店舗管理者の要件を満たしたら、次は独立開業に向けた必要な手続きをおこないます。
フランチャイズに加盟する場合は、フランチャイズ企業に確認すればやるべきことをすべて教わることができます。一方、自分自身で店舗を独立開業する場合、必要な資金等を準備したうえで、以下2つの手続きをおこないます。
- 保険薬局指定と薬局開設許可を取る
- 店舗に調剤室を設ける
これらの手続きを実施したうえで、店舗をオープンすることができます。
以上が具体的な手順です。必要な資金や人材を準備できれば、あとはお店が繁盛するように、経営者として事業を進めていくやりがいのある日々がスタートします。
独立開業に向いている人の特徴

独立開業は決して簡単なものではありません。当然、登録販売者によって向き不向きもあります。それでは、独立開業に向いている人には、どのような特徴があるのでしょうか。
新しいことへの挑戦・研究意欲がある
初めての独立開業では、手続きや仕入れなど、初めて取り組むことがたくさんあります。店舗の従業員として働いているとき以上に、より一層の研究意欲が求められることになります。
初めてのことに興味があり、勉強することが苦にならない方は、独立開業に向いているといえるでしょう。
マネジメント能力がある
開業する店舗の規模にもよりますが、接客や品出し、仕入れなど自分1人で運営するのは現実的ではありません。
基本的にはアルバイトや社員を雇用して、店舗を運営することになりますので、オーナーであると同時に店長としてのマネジメント能力が求められます。
面接・マニュアルの作成・スタッフの教育など、スムーズな店舗運営のために必要な運営業務がたくさんあります。他の仕事で店長やマネージャー職を経験したことがある方は、独立開業に向いているといえるでしょう。
交渉能力がある
独立開業は、交渉能力も必要になるでしょう。自らの店舗を開業するまでには、資金調達や仕入れなど、多くの関係先との交渉が必要となります。交渉の内容を把握し、不利な条件を回避してしっかり利益を出すための交渉能力は不可欠です。
豊富な人脈を持つ
人脈があれば商品の仕入れが非常におこないやすくなります。また、場合によっては様々な融通を利かせてくれることもあります。豊富な人脈があるのであれば、独立開業に向けた準備もしやすくなるでしょう。
成功するための方法

登録販売者が独立開業で成功するポイントを2つご紹介します。
地域の人に愛された店舗づくりをおこなう
ドラッグストアや薬局を開業する場合は、基本的には地域の方がお客さまとなります。そのため、地域の人に愛され、何度でも繰り返し利用してもらえるような店舗づくりをすることが、長期的に成功し続けるためのポイントです。
例えば、お客さまがご来店されたらしっかり挨拶をする、丁寧な接客を心がける、店舗内を隅々まで常に清潔にするなど、そのような些細で当たり前なことも必要になるでしょう。このような基本事項を実施できていない店舗も多いので、他の店舗との差をつけるためにも、しっかりおこなうようにしましょう。
また、フランチャイズの場合は、他の加盟店での成功例を共有してもらうこともできます。他店舗でうまくいっている事例を取り入れることで、より成功に近づきやすくなるのです。
他業態と組み合わせた事業をおこなう
他業態と組み合わせた事業をおこなうことも、登録販売者が独立開業で成功するポイントの1つです。最近では薬局やドラッグストア以外にも、登録販売者の資格を必要としている業種形態もあります。
例えばエステサロンやスポーツジムなどは、近年の健康ブームもあり、健康によい商品を店舗で販売したい、また利用者も購入したいというお互いのニーズがあります。
そういったエステサロンやスポーツジムを自身で経営しつつ、登録販売者の資格で販売できる商品を売る、あるいはそれらを運営している企業や個人と提携し、売れた商品の売上金の一部を受け取るなど、いろいろな方法があります。
登録販売者資格でネット販売のみの独立開業はできない

登録販売者の資格を活かして独立を考える場合、インターネット販売だけで事業はできません。なぜなら、OTC(一般用医薬品)の販売は、店舗を設置し、店舗管理者を常駐させることが法律で義務付けられているためです。
たとえネット販売をする場合でも、必ず実店舗を持つことが前提となり、インターネット販売を単独でおこなうことは認められていません。さらに、原則として、営業時間中は店舗に店舗管理者が常にいる必要があります。
独立開業には資格や業務経験が必要
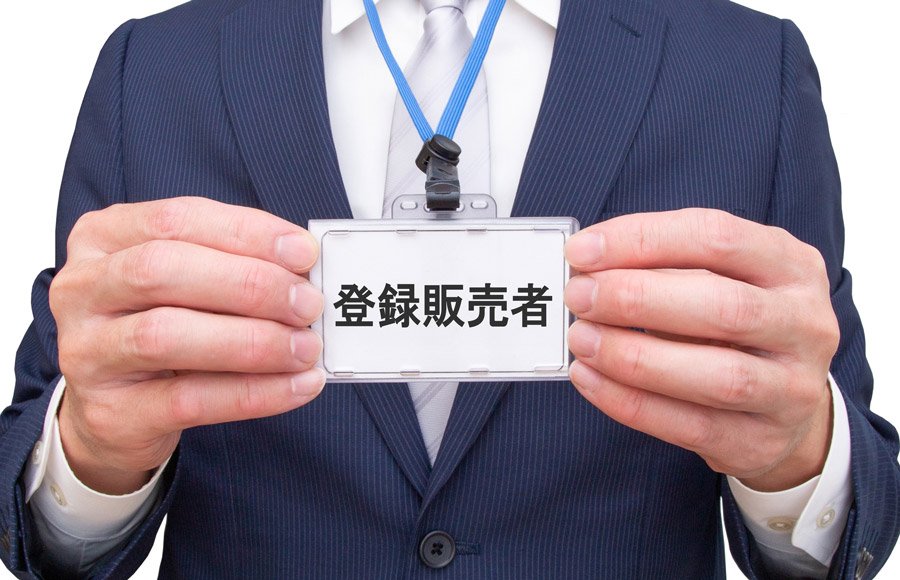
独立開業といっても誰でもできるわけではありません。ここでは、必要な資格や業務経験など基本的なことについて解説していきます。
登録販売者試験について
2014年までは、登録販売者の試験を受けるためには「大学などで薬学課程を卒業した者・高卒以上で1年以上の実務経験のある者」など、4つの条件がありましたが、2015年の登録販売者制度の改正によって、学歴や経験、年齢といった一切の条件がなくなり、誰でも登録販売者の試験を受けることができるようになりました。
資格試験は毎年8〜12月におこなわれます。出題される内容をまとめると以下の通りです。
【試験項目】
- 医薬品に共通する特性と基本的な知識
- 人体の働きと医薬品
- 主な医薬品とその作用
- 薬事関連法規・制度
- 医薬品の適正使用・安全対策
【合格基準】
総出題数に対して7割程度の正答の場合であって、各試験項目ごとに、都道府県知事が定める一定割合以上の正答のときに合格とすること。
上記5つの項目で、合計120問の問題が出題されます。合格するためには、正答率で70%以上、また5項目すべてで30〜40%程度正解することも条件となります。一見すると「すごく難しそう」と感じてしまう方もいるかもしれませんが、試験の難易度は中程度から易しめです。
登録販売者の試験は年1回、合格率は40〜50%と、他の国家資格と比べてもかなり高い合格率です。医薬品の問題も、勉強すれば未経験でもできる問題ばかりなので、未経験でも合格は十分できます。
登録販売者試験の難易度や勉強法、失敗しないための対策について知りたい方は、ぜひこちらのコラムも参考にしてください。
登録販売者試験は難しいってホント?難易度からおすすめの勉強方法までを解説
必要な実務経験を1年間積む
登録販売者として独立開業する場合、自らが店舗管理者となることが一般的です。なぜなら店舗管理者は、OTC(一般用医薬品)を安全に販売する責任者であり、法律で必ず設置しなければならない存在であるためです。
店舗管理者となるためには、少なくとも過去5年以内に通算で1年以上かつ累計1,920時間の実務経験が必要です。この実務経験には、OTC(一般用医薬品)販売の管理業務に携わった期間が含まれます。独立開業を目指すのであれば、まずは十分な実務経験を積みましょう。
登録販売者の実務経験を積める就職先
実務経験を積める就職先はいろいろとありますが、薬剤師や登録販売者がいる職場である必要があります。
一般的にはドラッグストアや調剤薬局、コンビニエンスストアなどで実務経験を積む方が多いです。実務経験を積める環境に就職していない方は、まずは、実務経験を積める環境へ転職し、最終的に独立するのに必要な「実務従事証明書」の取得を目指すこととなります。
資格を取得し、薬剤師や登録販売者がいる職場で実務経験を積み、初めて登録販売者として独立開業を視野に入れることができます。ひとまずドラッグストアなどで実務経験を積みたいときは、ぜひ一度ご相談ください。
「アポプラス登販ナビ」無料転職サポートまとめ|登録販売者の独立開業は正しい準備が成功の鍵
登録販売者が独立開業を目指すためには、資格の取得だけでなく、実務経験や店舗運営に必要な準備を確実におこなうことが重要です。さらに、資金の確保や出店場所の選定、仕入れ先の確保、従業員の採用、販売設備の準備など、段階的に手続きを進めていく必要があります。
もし、独立開業に向けてまずは店舗管理者としての実務経験を積みたいと考えている方は、登録販売者向けの転職サービスを活用するのもおすすめです。「アポプラス登販ナビ」では豊富な求人情報から、自分に合った店舗で経験を積めるため、将来の独立を目指す方にとって心強いサポートとなるでしょう。
ぜひ「アポプラス登販ナビ」を活用して理想の働き方やキャリアアップを目指しながら、着実に独立への準備を進めてください。
【新着】登録販売者のための業界コラム
- 2026年01月30日 登録販売者になるために必要な勉強時間は?働きながら合格できるスケジュールと効率化のコツ
- 2026年01月30日 ドラッグストアの人手不足?ドラッグストアで働く人が知っておくべき現場の実態と対策
- 2026年01月27日 登録販売者必見!疲労を感じるお客さまへのサプリの接客と受診勧奨
- 2026年01月09日 【現役ドラッグストア店長直伝】登録販売者が「辞めたい」と思わない3つのメンタル維持法(2026年対策付き)
- 2026年01月07日 2026年ドラッグストア業界の未来図|市場動向・M&A・登録販売者のキャリアと転職のポイント







