【現役ドラッグストア店長直伝】お客さまのQOL向上に向けた登録販売者の本質とは<登録販売者のキャリア>

登録販売者の皆さんは売場でどんなことを考えて働いていますか?
登録販売者としての使命感に燃える方、会社の一員として売上アップのための手段として資格を持っている方、人それぞれだと思います。
しかし思惑は何であれ「登録販売者としての責務」を負う義務はあります。
その責務は「お客さまのQOLの向上」です。
今回は「お客さまのQOL向上」に向けての具体的な思考を掘り下げてみましょう。
目次
お客さまの来店動機を考えてみよう

お客さまが来店する動機は「購入」と「相談」にわけられます。
そして相談から購入に至ることも多々あるわけです。
そしてわたし達が直接対応するのは主に「相談」となります。
まずは「相談」から接客に入るパターンを考えてみましょう。
悩みの本質を理解する努力をしていますか?
お客さまとの接客で表面的な症状のみ聞いていませんか?
表面的な症状のみ聞いているとQOL向上どころか、全く効果がなくお客さまに金銭的な負担だけ負わせてしまう場合もあります。
もしかしたら想定外の健康被害を起こす可能性もあります。
例をあげて考えてみましょう。
- 「疲れ」に対して理由を聞かずに推奨品のドリンク剤やビタミン剤をお勧めしてしまう
疲れの原因も種類があり、それによって対応する医薬品も異なってきます。
長期的な疲れか短期的な疲れか、肉体疲労か内臓疲労か精神疲労か。
症状は表面的であり、原因を聞かずに判断するのは危険です。
もし睡眠障害を伴う「精神疲労」に対してドリンク剤をお勧めした場合、配合されているカフェインの影響で更に睡眠が妨げられる可能性もあります。
- 「じんましん」に対してステロイドの皮膚薬をお勧め
お客さまが患部を見せてくることがありますが、その部位だけとは限りません。
お客さまは症状の程度を主張しているのに、それを「範囲」と受け取ってしまい不適切な販売をしてしまうパターンです。
ではこれらの失敗をしないためにはどうしたらいいのでしょう?
ヒアリング力と想像力の鍛え方
結論「聞くに徹する」に尽きます。
ただ人間には「心のテリトリー」というものが存在し、何でも話していただけるお客さまと、資格者への相談であっても赤の他人に自分の事情を話すことに抵抗感があるお客さまがいらっしゃいます。
もちろん時間がなかったり、ただ面倒なだけ...といったお客さまも存在するため一筋縄にはいきません。
ここで肝心なのは「簡単に答えていただく質問」ができるかどうか、なのです。
例えば先ほどの例でいえば「疲れが取れるビタミン剤やドリンクはありますか?」というお客さまに対して、売りたい商品のポイントを演説してしまう登録販売者も見かけますが
「いつから疲れが取れませんか?」
「昨日何かされました?」
という「心配」から原因を探っていくのが正解です。
皮膚薬なら同様に
「他にも症状が出ている箇所はありませんか?」
「何かいつもと違うものを食べたり、違うことをおこなったりしていませんか?」
と聞くと正解を導きやすくなりますしお客さまとの齟齬も発生しにくくなります。
共感できない場合は「なぜ?」を使おう
この「心配」や共感を引き出せる「質問」ができるとお客さまの立場から思考できるため、原因へたどり着くショートカットとなります。
そのためここでの質問は想像力や発想力が必要となります。
経験が何よりの鍛錬なのですが、鍛え方はひとつひとつのお客さまとの接客で「なぜ?」と思考を巡らせることに尽きます。
「売れたからよかった」のではなく「なぜ売れたのか?」
「お客さまの悩みが解決できた」のではなく「本当に解決できたと、なぜ言えるのか?」
そして「こんな原因で症状がおきるんだ」という事例の積み重ねが大切なのです。
この積み重ねがお客さまの悩みの原因に近づく鍵となるのです。
「普段と同じようにしているのに疲れるのはなぜだろう?」
「食べられて睡眠も取れるのに疲れるのはなぜだろう?」
ひとつの接客機会から複数の「なぜ?」を引き出し、お客さまに問いかけることで原因に近づくことができます。
「そういえば最近食欲がなくて...」
「忙しくてインスタント食が増えた気が...」
こんな答えを引き出すことがお客さまのQOLを向上させることにつながるのです。
会社主体で考えるか資格主体で考えるか
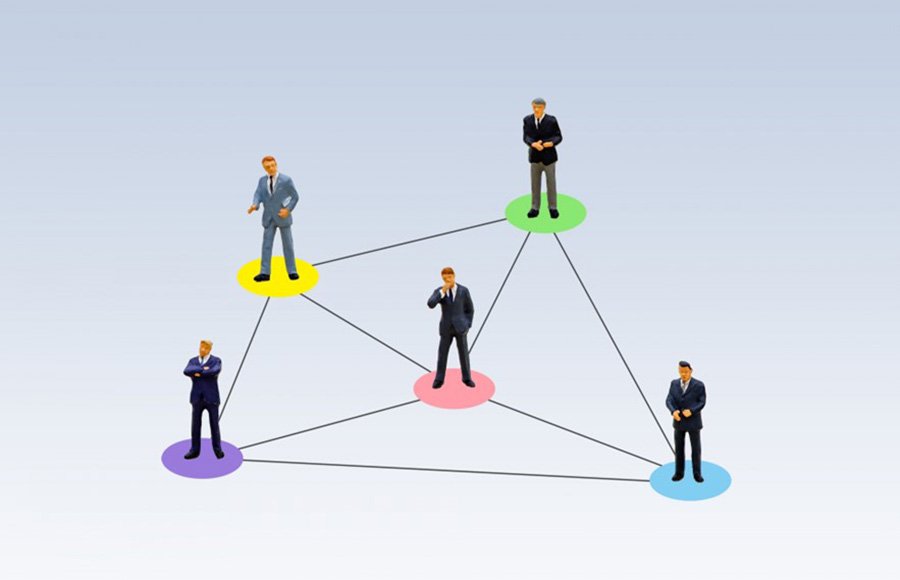
とくに業界に入り数年経験を積んだ方が陥りがちなのが「会社主体で考えるか資格主体で考えるか」というジレンマです。
ここで思考が泥沼にはまると行動もできなくなってくるので一度整理して考えましょう。
組織の一員としての使命とは
わたし達の仕事は地域のライフラインとしての役割やQOL向上に向けた社会的な責務を負いながらも、相反するようにみえる「ビジネス」という側面を持っています。
「お客さまのため」「地域のため」という名目を持ちつつ、利益を得るために販売し続けるという義務も負っているのです。
これは企業に属する限りどの業界にも共通することですが、とくにわたし達の業界はお客さまの健康状態に直結する問題なだけに慎重に考える必要があります。
お客さまの要望に応じたり、相談応需「だけ」だったなら利益は上がりません。
そしてそれはわたし達の雇用問題にも関係しますし、店舗が無くなれば地域の住民にとってもダメージです。
わたし達は「利益を得ながらお客さま満足度を上げていく」必要があります。
そのために推奨品販売などが存在するのですが、その販売に躍起になっていると顧客離れにつながってしまうのです。
資格者としての責務とは
一方で「登録販売者」としての責務で考えると、お客さま一人ひとりと真摯に向き合い、アドバイスをおこなったうえで適正な商品を販売するべきです。
- 接客を望まないお客さまに対しては「濫用等のおそれのある医薬品」の注意喚起をしっかりとおこない、それ以外の医薬品購入時はレジで「添付文書をよくお読みください」とお声掛けをおこなう
- 接客の際はしっかりとヒアリングをおこない極力リスクが低い商品を提案し、健康に関するアドバイスと共に商品提案をおこなう
- 店舗や会社の理由で商品選別をせずお客さまに合った商品を提案し、場合によっては販売せずにアドバイスのみで完結することもある
これが理想で、もし顧客の立場でこんな店舗で接客されたら安心して買い物ができそうですよね。
もちろんこんな店舗があったら地域のQOLは格段に向上しそうです。
そしてこれは「理想」でもあります。
ジレンマに陥っている方へ
この「会社の一員として実績を残す」ことと「登録販売者として適正販売をおこなう」というふたつの相反する義務感に板挟みになっている登録販売者を多くみかけます。
お客さまに適正販売をしつつ、会社予算などに追われて息苦しい方も多いはずです。
会社予算を追いながらお客さまに満足していただくには裏技などはなく、正攻法がお勧めです。
売らなければいけない商品の販売確率が10%なら、その確率を上げるのではなく試行回数を増やしましょう。
一日10回接客して1個販売できるのなら、20回接客して2個販売しましょう。
「お客さまのために」という観点で販売しているのであれば、その回数が増えるので顧客満足度も上がりますし推奨品の販売数も増えます。
わたしは販売の悩みを抱えた店舗のスタッフには「悩んでいるお客さまにお声掛けしてください」とお願いしています。
これだけでもある程度の実績はアップするのです。
お声掛けの基準は店舗の状況によっても違うでしょうが「1分以上定番で悩んでいる」などと基準を決めておくと声掛けをしやすくなるのでぜひ実践してください。
具体的な事例を自分の中で積み上げてみよう

ではここからは「お客さまのQOL向上」に向けた具体的なアクションについて考えてみましょう。
自分のできそうなことから実践してみてください。
お客さまに合わせて臨機応変に対応するには
医薬品販売は季節性のあるジャンルが多いのでどうしても固定観念にとらわれがちですが、お客さまの状況はそれぞれ違うので臨機応変に対応する必要があります。
夏の商品で例えるなら「虫よけ剤」があります。
- 日常での使用か、レジャーでの使用か
- 誰が使用するのか
- 外出時間はどの程度か
これらを聞くだけでもある程度商品は絞れます。
虫よけ剤の質問を受けた時に最も高濃度のものを勧めておけば間違いない...といった考え方は危険です。
使用感や形状もお客さまに合ったものかどうか、よく聞いてみると案外違うものが提案できることが多いのです。
医薬品か非医薬品か、ガスタイプスプレーかポンプタイプスプレーか、イカリジンかディートか...
例えばこの選択肢だけでも「非医薬品ガスタイプのディート」のように8パターン存在します。
この場合は「商品の知識」がなくても「選択肢」を覚えておけば定番売場の前で商品を選べるので選択肢を覚えておきましょう。
ひとつの症状に少なくとも2パターンの商品を準備する
症状に対応する商品は少なくとも2パターンは覚えておきましょう。
こうすることでお客さま自身に選んでいただけます。
お客さま自身に選んでいただくメリットは3つあります。
- 成分や価格など商品の差を提示できる
- 自身に合った形状をお客さまに選んでいただける
- 納得し購入していただける
例をあげておきます。
- 食べすぎの胃薬に「消化系胃薬」と「胃を動かす胃薬」
- 頭痛に「鎮痛剤」と「漢方薬」
- 保湿に「皮膚薬」と「保湿剤」
これを知っている方は多いはずですが、実践できていますか?
知らない方はひとつでも多くのパターンを覚えてみましょう。
知っている方は接客に入る前に「ふたつ紹介しますね」というだけでスムーズに紹介できます。
場合によっては複数の商品を販売できますし、お客さまの満足度も上げることができます。
しかし、選択肢は多くても3種類程度に留めておかないと逆効果となるのでほどほどにしておきましょう。
わたしの経験からいえば、ベストは2パターンです。
「どちらがいいか」という単純な選択の方が選びやすいのです。
この「二者択一」の時のテクニックもお伝えしておきましょう。
もし「売りたい商品」「お勧めしたい商品」があるのなら、以下のテクニックを使ってください。
・アンカリング効果
まず高価な商品を提案しその後に安価な商品を提案することで「安い」という意識付けを行える効果です。
また、効能効果が弱かったり少なかったりする商品を先に提案し、その後に効果が高い商品を提案することもできます。
お客さまが金額か効果か、どちらを重要視しているかを確認しつつ使うと効果的な手法です。
・ウィンザー効果
第三者からの評価を信じてしまう効果で、「口コミ」を信じてしまうのもこの効果です。
「常連のお客さまもリピートしています」「さっきもこの商品が売れたんですよ」のように、自分以外も使っているんだ...という安心感を使うのも効果的です。
このふたつを合わせて使うとかなり効果があります。
ヒアリングをおこない「このお客さまにはこの商品を使ってほしい!」という商品があったら、ぜひ合わせ技で使ってみてください。
「ふたつ紹介しますね。この『A』がまずお勧めです。でもこちらの『B』の方が効果が高くて、この前紹介したお客さまもよく効いたとおっしゃっていましたし、わたしもこの症状の時はこれを使っています!」
すべて自分で解決しようとしない
そしてお客さまの信頼やQOL向上のために最も必要なのは「自分だけで解決しない」ということです。
お客さまは「あなた」に問題解決してほしいわけではなく、問題が解決できれば誰でもいいのです。
むしろあやふやな対応をされるよりも、店舗内でわかる人にバトンタッチされた方が安心して購入していただけます。
そのような時はお客さまに「もっと勉強しておきます(勉強になりました、ありがとうございます)」とお伝えすればおおきな問題にはなりません。
資格者が他にいない時は会社のシステムを利用したり、本やネットで調べたりしたうえでお客さまに対応しましょう。
わからなかったら無理やり答えを出さず、「わかりかねます」とお詫びした方が誠実です。
誰もが通る道ですので、不勉強を恥じるようなことはありません。
そして自分の中の「なぜ?」を細分化してみましょう。
- 提案する候補を選べなかった「なぜ?」
- 説明が上手く伝わらなかった「なぜ?」
- 同僚が別の商品を勧めている「なぜ?」
この「なぜ?」のバリエーションをひとつでも多く増やすことがスキル向上につながり、多くのお客さまのQOL向上に寄与できるのです。
毎日「なぜ?」をひとつでも積み重ねていきましょう!

執筆者:ケイタ店長(登録販売者)
ドラッグストア勤務歴20年、一部上場企業2社で合計15年の店長経験を活かし、X(旧Twitter)などで登録販売者へのアドバイスや一般の方への生活改善情報の発信を行っている。X(旧Twitter)フォロワー数約5,000人。
【新着】登録販売者のための業界コラム
- 2025年12月03日 【現役ドラッグストア店長直伝】冬商品で接客スキルを劇的に磨く3つのコツ
- 2025年11月21日 現役薬剤師が教える。登録販売者の新人教育マニュアル|OJTの進め方と後輩指導のコツ
- 2025年11月21日 現役薬剤師が伝授|インフルエンザ時に使える解熱剤の見分け方と登録販売者の声かけ技術
- 2025年11月06日 【2026年法改正で必須!】現役店長が教える「OD対策」現場対応完全ガイド 〜登録販売者が押さえるべき「3大変更点」と心構え〜<登録販売者のキャリア>
- 2025年10月30日 登録販売者はブランク後も復職できる!管理者要件と安心して働くためのポイント




