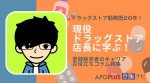【現役ドラッグストア店長直伝】初めての花粉症接客のコツ<登録販売者のキャリア>

登録販売者の皆さま、年末年始商戦お疲れさまでした。
とくに今年は風邪の流行もあり接客業務が多忙を極めた地域もあるはずです。
新年を迎えて最初のヤマとなるのが「花粉症」ですが、とくに初めて登録販売者として春を迎える方には大きな試練となります。
この最初のヤマの高さを自身で設定してそれを乗り越えることで登録販売者として大きく成長することができるため、この花粉症シーズンは大切なのです。
今回は「初めての花粉症接客のコツ」を解説していきましょう。
目次
花粉症関連商品の現状とは

花粉症はもはや国民病ともいわれ、日本人の3人に1人は花粉症とされています。
数字だけで判断すると現在の日本の平均世帯人数は2.5人なので、来店されるお客さまのほとんどがターゲットとなり得る状況となり、医薬品販売において一大マーケットとなっています。
登録販売者としてこの機会を「お客さまのQOL向上」の好機と捉え、接客をおこなう必要があります。
では現状の花粉症治療薬や対策商品の状況から、今後登録販売者がとるべき行動を考えていきましょう。
10年前とは大きく異なる商品群
代表的な第2世代抗ヒスタミン薬である「フェキソフェナジン」が第2類医薬品に区分変更となったのが2016年でした。
それまでは効果も副作用も大きい第1世代抗ヒスタミン薬しか店頭で自由に購入できなかったため、10年前と比較して大きく様変わりしている状況です。
しかし店頭ではいまだに第1世代抗ヒスタミン薬が販売され、それを求めるお客さまも多いのが現状です。
実際に接客してお客さまの声を聞くと大きく2つの意見に分かれます。
- 新しい薬は使ったけど効かない
- 昔から使っている薬で満足している
この2パターンは別の対応が必要に見えますが、本質は「第2世代抗ヒスタミン薬など新商品の良さ」を伝えることになるので難しく考える必要はありません。
最終判断はお客さまとなりますが、その一助となるように第1世代と第2世代のメリットとデメリットをわかりやすくお伝えするのが登録販売者としての使命となります。
しかし「第1世代抗ヒスタミン薬」を購入されるお客さまの多くは2025年現在で中高年層が圧倒的に高いのが特徴であり、ここに大きなリスクが潜んでいます。
ではそのリスクと接客の必要性を解説していきます。
古いタイプの花粉症治療薬を購入する人の特徴
花粉症治療薬の接客でもっともスムーズなのは「受診していたが同じ薬を市販薬で購入する」というお客さまです。
このパターンは100%「第2世代抗ヒスタミン薬」を購入されるため、リスクや禁忌の説明はほぼ不要で追加で点鼻薬や鼻うがいなどの「プラス1品」の接客をおこないやすくなります。
もっとも難しいのは「第1世代抗ヒスタミン薬」を購入されるお客さまで、その中でも「デメリットを把握していない」もしくは「デメリットを把握しているつもり」というお客さまです。
ご本人が自覚されていないデメリットはある日突然牙をむく可能性が高いため、よく説明をする必要があります。
このデメリットの説明で多く発生するのが以下の2つです。
- 今まで大丈夫だった(からこれからも大丈夫にちがいない)
- 自分に合っている(が他の薬は試していない)
わたしは自店の登録販売者に教育する際にとくに注意するよう伝えていますが、「効果よりデメリットを排除する」ために登録販売者が各店舗に配置されているのです。
効果は各メーカーのCMやパッケージなどで充分に認知されていますが、デメリットは小さな文字で記載されているだけなのでほとんどのお客さまが読んでいないのが現状です。
市販薬に限らず消費者はメリットを求めるのでこれは仕方がないのですが、医薬品は健康に直結するものなので必ず伝えなければいけないのです。
では具体的によくある例と対策を考えてみましょう。
もっとも大きなリスクとは
もっとも大きな「第1世代抗ヒスタミン薬」の問題は3つです。
- 依存問題
- 持病との関係
- 自動車運転(機械類の運転操作)禁忌
順に解説していきます。
- 依存問題
登録販売者として勤務する以上、もっとも出番が多いのが「濫用のおそれのある医薬品」対応です。
風邪薬の場合は1週間程度で治るため依存になりにくいのですが、アレルギー症状は基本的に長いため知らず知らずのうちに市販薬依存につながる可能性があります。
とくに若年層の使用には注意が必要で、小児に使用できる「第1世代抗ヒスタミン薬」もありますができれば小児用のフェキソフェナジンに切り替えるべきです。
小児は薬の選択を自身でできないため、保護者にしっかりとデメリットを伝えてください。
- 持病との関係
「第1世代抗ヒスタミン薬」の中には鼻詰まり解消を目的として「プソイドエフェドリン」などが配合されているものが多く、これらは高血圧や糖尿病の方は禁忌となります。
問題はこれらの薬を数年、十数年と長期にわたって使用している方です。
長期的に使用することで薬の使用に対して抵抗がなくなっている他にも、その期間で持病が悪化していたり発病している可能性が大きいのです。
例えば「第1世代抗ヒスタミン薬」を使用し始めた時は持病がなかったため大きな問題は起きていなかったものの、途中で持病が発症してしまい本来なら使ってはいけない薬を漫然と使用し続けるパターンです。
先に書いた「今まで大丈夫だったから」という反応の中にこのパターンも入るため、とくに注意が必要です。
「今まで大丈夫だった」と言われても持病の確認は必ずおこなってください。
- 自動車運転(機械類の運転操作)禁忌
もっとも注意すべきは「機械類の運転操作」です。
この中に自動車運転はもちろん、自転車運転も入ります。
一部の「第2世代抗ヒスタミン薬」でも「機械類の運転操作」は禁忌となるため、運転をする必要があるお客さまには「フェキソフェナジン」「ロラタジン」をお勧めすべきです。 もちろん「第1世代抗ヒスタミン薬」はすべて、運転操作は禁忌となります。
先に挙げた「依存」「持病」は万が一、禁忌を犯したとしても健康被害に遭うのはご自身のみですが、運転操作に関しては第三者を大きな被害に遭わせてしまう可能性がある(道路交通法第66条違反)ため個人的にはもっとも大きい「副作用」と考えています。
最新の治療薬を把握しておく理由

花粉症治療薬の販売に携わる者として、登録販売者が最重要視しなければいけないのは「最新の情報を把握すること」です。
その理由を考えていきましょう。
毎年新成分が第2類に変更されている
2016年に「第2世代抗ヒスタミン薬」が第2類医薬品に区分変更されてから次々と新成分がスイッチOTCとして市販化されています。
登録販売者としてこれを抑えておくべき理由は2つあります。
まずはもちろんお客さまのため、そして登録販売者自身のためでもあります。
定期的なインプットをおこなうことを習慣付けることで、登録販売者としてのスキルアップにつなげることができるのです。
毎年これだけ新しい成分が市販化されたり区分変更されたりするジャンルはありません。
そして「第2類抗ヒスタミン薬」はほぼ成分が1種類の単剤なので経験が浅い登録販売者でも充分理解ができるのです。
- 「今年の成分は何だろう」
- 「どうお客さまにアプローチできるんだろう」
こう考えることでお客さまにも自身にもメリットが多いのです。
受診していない人が多い
登録販売者がインプットしなければいけない理由の一つに「受診していないお客さまが多い」というものもあります。
花粉症は症状が人それぞれのため軽症の方はとくに受診している方は少ないのです。
受診しないということは「第2世代抗ヒスタミン薬」に触れる機会は店頭だけとなります。
第2世代薬も毎年新しい成分が市場に投入されるため、登録販売者が紹介しないとお客さまの知識や経験がアップデートされないのです。
そして店頭の資格者のアドバイスを受けずに市販薬を使おうとすると、判断基準がメリット重視となってしまうなど選びかたも自己流となってしまう問題があります。
受診していないお客さまには最新情報をお伝えし、QOL向上となるようアドバイスをおこないたいところです。
自己流花粉症対策の危険性
一定数のお客さまは自己流の対策をおこなっていています。
本来、市販薬は使用者が自身で選択し使用するための医薬品なのですが、鼻炎薬に関しては自身で選択して使用すると危険なものも存在します。
現状だと「第1世代抗ヒスタミン薬」「血管収縮剤配合点鼻薬」で、前者はここまでで取り上げた通りですが、後者にも「薬剤性鼻炎」を引き起こす可能性があります。
繰り返しますが風邪と違い花粉症は1カ月以上の長期に及ぶ症状なので、市販薬で対策する場合は長期連用が必須となります。
このため長期連用リスクが高い商品は避け、できるだけ安全性の高い商品をお勧めすべきなのです。
「血管収縮剤配合点鼻薬」は安価であり即効性もあるため手を出しやすく、一度に複数個を購入される方も多いのです。
「血管収縮剤配合点鼻薬」が原因の「薬剤性鼻炎」は長期連用することで発症し、治療方法は断薬しかないため非常に辛い症状です。
迷うことなく血管収縮剤配合点鼻薬を購入されるお客さまは薬剤性鼻炎の確率も高いため、ぜひお声がけをおこなってください。
ちなみに「ステロイド点鼻薬」は薬剤性鼻炎にならず、経済的にも1日当たり数十円のためお勧めしやすく効果も高いためぜひ接客に取り入れてください。
行動を変えてスムーズな接客をするためには
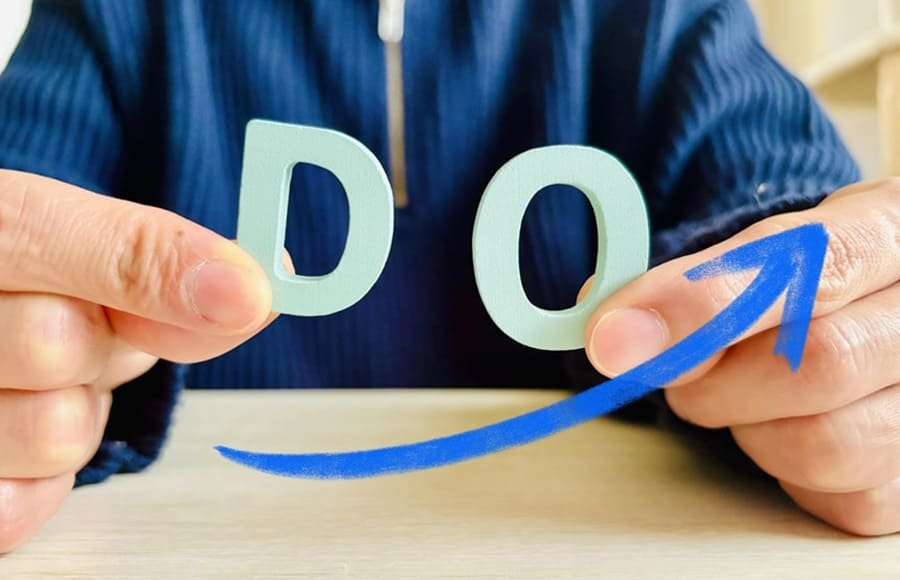
登録販売者が接客するシチュエーションは主に「レジ」「売場」の2カ所です。
それぞれの接客のコツと要点をお伝えしますので実践の参考にして下さい。
「機械類操作禁忌」を年間で意識する
とくにレジは必ず接触する場所なので対応方法を覚えておきましょう。
1日に数回「濫用等のおそれのある医薬品」対応でレジに呼ばれると思いますが、この回数が花粉症シーズンに入ると地域によっては大きく伸長します。
人によっては「濫用対応」は苦手だと感じていると思いますが、逆にチャンスでもあります。
濫用対応は依存の確認と聞いても持病までの登録販売者が多いですが、ここでは機械操作の禁忌にまで踏み込むべきです。
これを年間でおこなっていると花粉症シーズンでの濫用対応で「第1世代」から「第2世代」への切り替えがスムーズに進みます。
あくまで体感ですが、運転操作の禁忌に関してはレジでの声掛けの方が切り替えやすく感じます。
「持病⇒機械操作⇒依存」の順に聞き、それでもお客さまが第1世代に購入の意志を示したらこれらのデメリットがかなり抑えられた薬もある...と、第2世代をお勧めするとスムーズです。
「鼻炎薬=飲み薬」の意識を変える
お客さまや登録販売者の中には「鼻炎薬=飲み薬」という固定観念がある方が多いのですが、そうではありません。
医薬品の飲み薬以外で鼻炎を解消する商品は複数存在します。
市販薬では「ステロイド点鼻薬」もありますし、非医薬品でも「鼻うがい」をすることで予防も可能です。
また難しい鼻詰まりの解消でも「鼻腔拡張テープ」や、小児用の医薬部外品である胸部へのメントール含有塗布剤などを使用することで「プソイドエフェドリン」なしでも対応は可能です。
副作用が多い飲み薬を使用するよりもQOLが低下しないため、有効活用することでお客さまに喜ばれます。
また鼻炎薬との併用も可能なので「プラス1品」の商材としても優秀で売上にも貢献できるため、ぜひ覚えておいてください。
花粉症接客の有効トーク術
では「今年から使える花粉症接客話法」を紹介します。
デメリットはたとえ話を使うことでソフトに伝えることが可能です。
・第2世代抗ヒスタミン薬に切り替え
「この鼻炎薬は古いタイプのお薬なのでお客さまがお持ちの持病だと赤信号です。青信号のこちらの鼻炎薬は新しい成分なのでお勧めです。」
「この薬は昭和時代の薬で副作用が強いですよ。もう21世紀なので新しい薬も市販化されているので試されてはいかがですか?」
・ステロイド点鼻薬
「飲み薬だと副作用で自動車運転ができなくなってしまうので新しいステロイド点鼻薬がお勧めです。かなり効果的でリピーターのお客さまも多いですよ。」
・医薬品以外で対応
「鼻詰まりを解消する成分は副作用が多く依存の問題もあるんです。鼻炎薬は使う期間も長いので飲み薬以外で対応するのがお勧めです。もちろん併用もできますよ。」
これらを組み合わせることでお客さまのQOLを向上させつつ、プラス1品も可能となります。
ぜひ積極的にお客さまへのお声がけをおこなってください!

執筆者:ケイタ店長(登録販売者)
ドラッグストア勤務歴20年、一部上場企業2社で合計15年の店長経験を活かし、X(旧Twitter)などで登録販売者へのアドバイスや一般の方への生活改善情報の発信を行っている。X(旧Twitter)フォロワー数約5,000人。
【新着】登録販売者のための業界コラム
- 2025年12月03日 【現役ドラッグストア店長直伝】冬商品で接客スキルを劇的に磨く3つのコツ
- 2025年11月21日 現役薬剤師が教える。登録販売者の新人教育マニュアル|OJTの進め方と後輩指導のコツ
- 2025年11月21日 現役薬剤師が伝授|インフルエンザ時に使える解熱剤の見分け方と登録販売者の声かけ技術
- 2025年11月06日 【2026年法改正で必須!】現役店長が教える「OD対策」現場対応完全ガイド 〜登録販売者が押さえるべき「3大変更点」と心構え〜<登録販売者のキャリア>
- 2025年10月30日 登録販売者はブランク後も復職できる!管理者要件と安心して働くためのポイント