【現役ドラッグストア店長直伝】登録販売者のモチベーション維持方法<登録販売者のキャリア>

今年も暑くなり勤務中に疲弊してしまう登録販売者も多いと思いますが、モチベーションが落ちていないでしょうか?
今回はわたしが店舗の従業員に対しておこなっているモチベーションアップ方法を考えながら、前向きに仕事をしつつスキルアップする方法を考えましょう!
目次
社内や公的な勉強会を活かすには

先日わたしの店舗の登録販売者も目指す方からこんな声をいただきました。
「店長のような知識を身につける自信がありません。」
「どうして商品知識が豊富なんですか?登録販売者になれても店長のように知識を身につける自信がないです。」
わたしは記憶力がかなり悪く登録販売者試験もよい点数ではありませんでしたが、ほとんどの店舗で商品知識が多いと言われます。
では記憶力がよくなくても商品知識が身についていく行動を紹介していきます。
まずは「勉強会」の活用法をみていきましょう。
文字だけで覚えられますか?
皆さんの会社にも資料やe-ラーニングなどのスキルアップツールがあると思います。
そして公的な義務としての研修もありますよね。
これは人によっては苦痛に感じるはずです。
実はわたしもそのひとりです。
中学や高校の歴史や科学のような「暗記」が苦手な方にとっては苦労してしまうのが「学習」でしょう。
わたしもこうしたツールの問題で商品名と成分名を結び付けたりする問題は苦労します。
できる方もいるでしょうが、しかしこれは当たり前のこと。
人間の記憶は「五感」を使わないと定着しないので、勉強をおこなう際は必ず実物を使って覚えて下さい。
店舗で学習する時は「商品」を手に取って問題を解く。
自宅などで学習する時はメーカーサイトを閲覧しながら問題を解く。
可能であれば自身で服用や使用したうえでの「感覚」で覚えてください。
「五感」の力は非常に大きく、記憶の定着に役立ちます。
これを理解している方は多いですが、実施している方はなかなか見掛けません。
実際に手にして視界に入れたうえで知識を吸収してください。
武器を持っただけでは戦えない
昔のロールプレイングゲーム(RPG)では強い武器を入手しても「装備」しないと攻撃力は上がりませんでした。
登録販売者も同じことで、知識を吸収しただけではスキルアップにはなりません。
吸収した知識を「実戦」で使えるよう自身の中で消化する必要があります。
素直な方に多いのですが、お客さまとの接客の中で勉強した単語などをそのまま使ってしまう方は注意が必要です。
そう思っていなくても、その他の業務で用語を使ってしまう方は注意しましょう。
- 「申し訳ありません、発注停止です」
- 「ストコン上では発注可です」
- 「NB品よりPB品の方が...」
どんな単語もお客さまにとっては専門外と思って接してください。
すべての成分の働きを「自身の言葉で言い換える」ことでお客さまに伝わりやすく自身の記憶の定着につながります。
- 身体の過剰な反応をなだめる働き
- 筋肉をモミモミする働き
- 信号を止めちゃう働き
口語や幼児語を使うとインパクトがあって覚えやすいのでお勧めです。
武器は必ず装備し、知識を使える状態にしましょう。
勉強は必ずセットでおこなう
このように知識を吸収するにもセットでおこなうことが重要ですが、それを使える状態にすることも忘れてはいけません。
そして勉強もひとりでおこなうのではなく、従業員仲間とセットでおこなうのがお勧めです。
お互いに質問を出し合ったり、進捗を確認したりして切磋琢磨することでスキルが上がります。
わたしは今まで在籍した店舗では極力2名で登録販売者を目指してもらっています。
実施は2名が最適です。
3名以上だと順列ができたり共倒れになりやすく、バランスが崩れるからです。
現にわたしが経験した中で3人で登録販売者に挑戦したことがありましたが全員不合格でした。
これは3人以上だと学習の進捗確認がしにくいうえに熱意の強弱に差が付く場合があり、性格にもよりますがそれが原因で熱意の弱い方に基準を合わせてしまったことが原因でした。
このような過去の経験から登録販売者を目指す時は2名に声掛けを行い、その2名で切磋琢磨を行わせています。
具体的には「学習進捗」と「熱量」を同一にするため、学習量(テキストの進捗、過去問を解く量や正答数)を均一にし、わたしが壁打ちのコーチのような役割を行っています。
進捗確認のため業務中に基本的な知識の質問を出したり、モチベーションアップのために接客を見せたり、また受験者2名での進捗確認や、クイズ形式で問題を出し合ったり...と、主体的に学び合う空気を作っています。
薬局併設店舗なら薬剤師も巻き込んでおくと受験者も不明点を質問しやすくなるので、日頃からの人間関係も構築しやすいように薬局側とのパイプを太くするよう心がけています。
こうした土台を固めておくと受験者も前向きに勉強ができるので管理者の方はぜひ実施してみてください。
お客さまの声に耳を傾ける
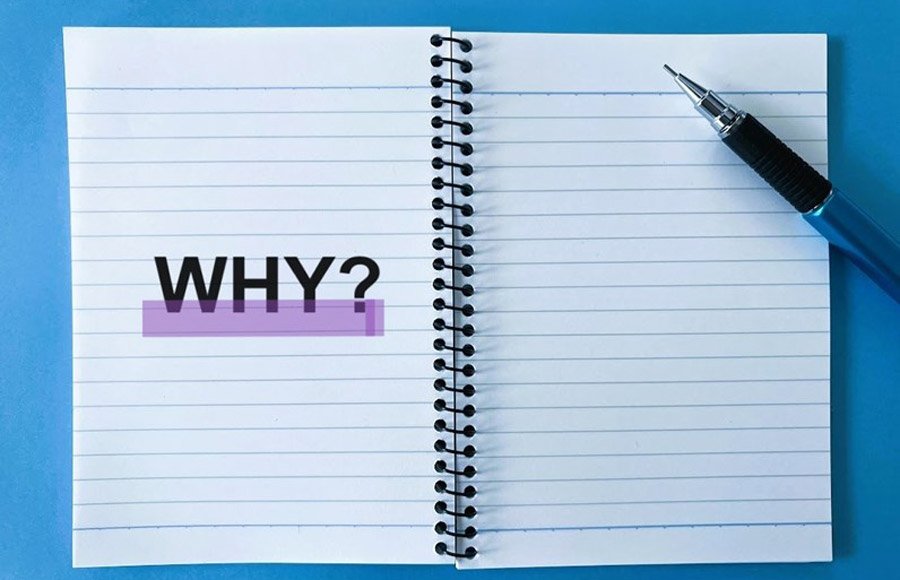
学習ができたらぜひ接客に活かしてください。
お客さまへの接客に活かせる学習方法を考えていきましょう。
生の声と接客ノート
もっとも学習できるのは「お客さまの生の声」です。
ある意味勉強のスタートでもありゴールでもあるからです。
店舗にもよりますが、お客さまとの接客は1日のうち数回は発生するはずです。
このときの「お客さまの声」は生きたお悩みでもあり、そこから導き出された答えこそが「真の正解」であることも多いからです。
接客の末にお客さまの選んだ商品は、そのお客さまがわたし達のアドバイスを元に導いた「答え」です。
そのお悩みと答えの蓄積こそが登録販売者のスキルでもあります。
この記事でも解説しましたが「接客ノート」を作成してください。
【現役登録販売者のリアルな接客ノートを大公開】接客力アップに秘訣とは
接客ノートはぜひ自分自身で使いやすいようアレンジしてください。
頭でその時にわかっていても、時間の経過で忘れてしまうものです。
実際にノートを作成し、数カ月後に読み返すときっと光景が蘇ってくるはずです。
後から改善点などあったら追記し、読み返すことで提案力が上がっていくのが実感できます。
相談内容とセットで覚えよう
接客ノートを作成することの主な目的は「症状と商品を結びつけること」です。
そんなのは当たり前...と思われるでしょうが「症状」を掘り下げて悩みの元を把握することが目的のひとつでもあります。
ここではそのお客さまがなぜお悩みなのかを考えて記載します。
考え方は以前のコラムで解説していますので参考にしてください。
【現役ドラッグストア店長直伝】会社指示とお客さまの要望の両立<登録販売者のキャリア>
相談は表面的な内容を聞くだけではなく、必ず要因も聞いてください。
そしてその要因別に症状を列記することで、ひとつの症状から様々な商品が提案できる「リスト」が作られていきます。
このリストは本や勉強会などでは得ることのできない「生きた知識」であり、あなただけの財産となります。
接客メモを作成したことがない方は、ぜひ習慣にしてください。
アウトプットしてみよう
お客さまから感謝された内容を覚えている方も多いはずです。
人は知識を広げることに本能的な喜びを持っているので成功体験をプラスして好循環を生み出していきましょう。
そしてもちろん、蓄積された知識は再度活用することで血となり肉となっていきます。
リピーターを生み出しやすくなりますし、お客さまは固定客になっていただくと信頼した登録販売者にはお悩みを伝えやすくなります。
好循環を生み出すにはアウトプットが最大のチャンスですが、アウトプットの相手はお客さまだけではありません。
店内の従業員や登録販売者、家族や友人などできる限りアウトプットしてみましょう。
アウトプット時には不安があるかもしれませんが、自信を持って接客してください。
ポイントとしては「~と思います」などを使わない、というものがあります。
- 「〇〇なら効くと思います」
- 「〇〇が効くはずです」
- 「〇〇が効きます」
どれが説得力があるでしょう。
言葉尻までしっかりと意識してください。
インターネットからは学べるのか?

お客さまからの問い合わせでしかメーカーホームページ(HP)を開いたことがない方は、非常にもったいないです。
メーカーHPは知識の宝庫なので逐一チェックしてください。
メーカーホームページはわかりやすい
経験の少ない登録販売者や登録販売者試験の勉強中の方はとくにメーカーHPはお勧めです。
基本的にメーカーHPは消費者への広告の役割も兼ねているため、誰にでもわかりやすいように作成されています。
消費者向けにわかりやすく理解しやすい内容のため、お客さまの求めるポイントにも一致します。
商品案内ページ以外のコラムなどは有益な内容で、理解しやすくそのままアウトプットにも使えるのです。
添付文書も要点が絞られていて理解しやすいのですが、メーカーHPは症状の要因や薬の効能効果以外にも生活上の予防法や改善方法にも触れているのがポイントです。
とくに漢方薬のメーカーHPはわかりやすいので漢方薬が苦手な方はぜひ閲覧してみてください。
もうひとつ参考にしてほしいのが「Q&A」のページです。
ここにはお客さまからの代表的な疑問や見落としやすいポイントなどが書かれています。
素朴な疑問や薬の知識としては当り前のもが多いですが、お客さまから聞かれやすい疑問が勢ぞろいしているのでトリビア的に楽しみながら読むことができます。
必ず有名メーカーのQ&A欄は参考にしてください。
注意しなければいけないこと
インターネットでの情報収集が主流になりつつありますが、ネット情報は真偽が不確かなものも多いため注意してください。
基本的に「メーカーHP」「添付文書」以外は参考に留めておくべきです。
とくにSNS関係、X・YouTobe・Instagram・TikTokなどは不確かな情報も多いため発信源を確認しましょう。
発信源が医師などでも誇張や誤情報もあるので基本的には参考にしないのがお勧めです。
これはお客さまとの会話でも同様に注意が必要です。
指定買いの動機には、SNSから得たインフルエンサーの情報や中途半端に聞きかじった情報に基づいている場合もあります。
接客を通じて、お客さまが不正確な情報元をもとに指定買いをしようとしていることがわかったら、慎重に対応しなければなりません。
その時に頭ごなしの否定から入るとお客さまも態度を硬化してしまうので、全否定せずに共感から入り、可能であれば信頼できるソース(公的機関HPや消費者センターHPなど)を提示したうえでお客さまの軌道修正をおこなってください。
勉強のコツ

最後に勉強のコツを書いておきます。
わたしのもっとも苦手なものは「暗記」です。
ドラッグストア業界に入った当初は成分名も覚えられず四苦八苦しました。
「フェルビナク」を「フェルナビク」と勘違いして覚えていたりしました。
「ビタミンB群」の違いもさっぱり理解できませんでした。
そんなわたしの転機は「接客ノート」でした。
所属していた店舗の近隣の店長が「地区勉強会」をおこなっていて、そこで勧められたのです。
もちろん勤務外での勉強でしたが、接客ノートを活用するようになり辿り着いた結論は「座学より実戦」です。
もちろん基本的な勉強は必須ですが、お客さまに求められ、店舗に必要とされ、会社にとって利益をもたらすのは「実戦で必要とされる登録販売者」なのです。
「接客ノート」を活用しはじめ、お客さまから感謝されることが次第に増えていきました。
人間は誰もが承認欲求を持っています。喜ばれることでさらに意欲が増すのです。
しかしその手段は「接客ノート」だけではありません。
わたしは接客ノートを活用できましたが、もちろん店舗でのロールプレイングでもいいでしょうし、共感力があれば座学をきわめて理論武装したうえで接客に望むのも、ある意味でありだと思います。
店頭で活躍する登録販売者の数だけ、成長パターンがあって然るべきだと考えています。
勉強方法を周囲の登録販売者や受験者に共有するのもアウトプットの練習になるのでぜひやってみましょう。
いまわたしの店舗では2名の従業員が登録販売者試験に向けて勉強中ですが、今回はとにかく過去問を解きまくるというチャレンジで合格を狙っています。
もちろん合格後は「接客ノート」を作成してもらい、店頭で研鑽を積んでもらう予定です。
今活躍中の登録販売者の方、合格に向けて勉強中の方、皆さんお客さまのQOLを向上させ、自身のスキルをアップさせるためにも頑張ってください!

執筆者:ケイタ店長(登録販売者)
ドラッグストア勤務歴20年、一部上場企業2社で合計15年の店長経験を活かし、X(旧Twitter)などで登録販売者へのアドバイスや一般の方への生活改善情報の発信を行っている。X(旧Twitter)フォロワー数約5,000人。
あわせて読みたい関連コラム
【新着】登録販売者のための業界コラム
- 2026年02月04日 【専門家監修】正月太りの原因&最短リセット法|食事・サプリ・漢方で無理なく解消するコツ
- 2026年02月04日 【専門家監修】胃腸炎に効くドラッグストアの市販薬5選!症状や原因別の選び方のポイントもあわせて解説
- 2026年02月03日 登録販売者に年齢制限はあるの?正社員・パートなど働き方別に解説
- 2026年02月02日 登録販売者試験に受かったら。合格後の手続きや流れを分かりやすく解説!
- 2026年01月30日 登録販売者になるために必要な勉強時間は?働きながら合格できるスケジュールと効率化のコツ







