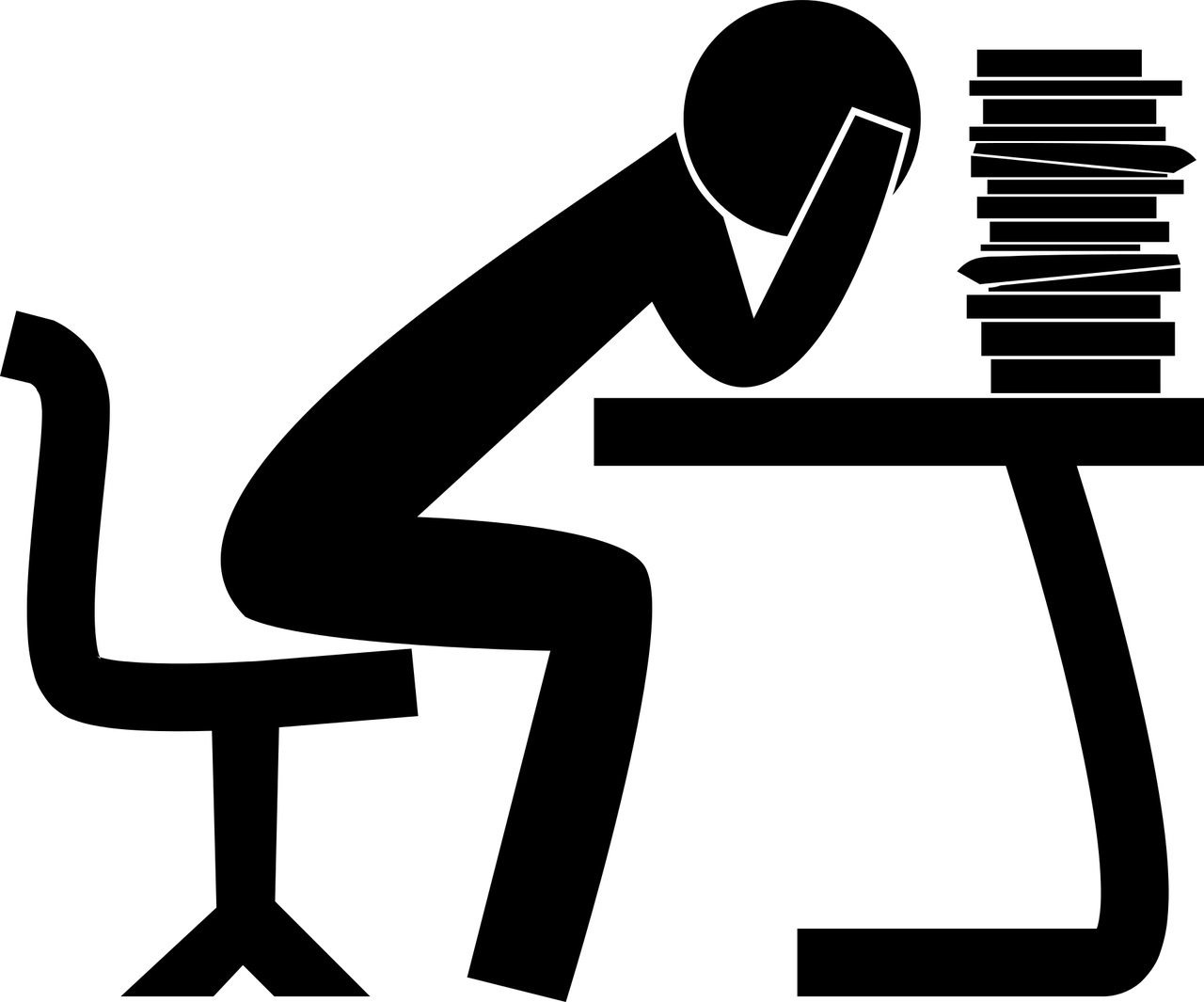ドラッグストアでの店舗マネジメントはどうやる?登録販売者に聞く店舗管理者業務

こんにちは、登録販売者転職のアポプラス登販ナビライターチームです。
登録販売者としてドラッグストアで働いていると、ゆくゆくは店長や店舗管理者を目指す人が多く見られます。
今回はドラッグストアで店舗マネジメントを担う店長、そして今後店長や店舗管理者を目指す方向けに、知っておきたい情報を紹介します。後半では登録販売者として20年以上の経験を持つケイタ店長へのインタビューを実施し、責任者としての働き方や転職時のポイントをお聞きしました。
目次
- ・店舗管理者になるには要件をチェック
- ・店舗管理者と店長の違いとは?
- ・実際におこなっていた店舗マネジメントの取り組み
- ・【登販】店舗管理者の経験を活かす転職のコツ
- ・ケイタ店長から管理者を目指す方へのアドバイス
- ・まとめ|店舗マネジメントは「対話」を意識
店舗管理者になるには要件をチェック

店舗管理者は店長と混同されることがありますが、厳密には異なるポジションです。店長は各ドラッグストアにおいて企業から任命されその職につきます。一方で、店舗管理者は登録販売者の中でも要件を満たすことでなれるポジションです。
ここでは店舗管理者になるための要件を紹介します。店舗管理者は登録販売者の資格を持っているだけでなく、実務経験も求められます。
管理者要件を満たす
店舗管理者になるには下記の管理者要件を満たす必要があります。
- 過去5年間に通算2年以上(1,920時間)の登録販売者としての実務経験がある
- 過去5年間のうち通算1年以上(1,920時間)の実務経験があり、かつ継続研修並びに追加の研修を終了している
- 通算1年以上(1,920時間)の実務経験があり、過去に管理者として業務に従事した経験がある
なお、上記で指す「実務」は以下の3つを満たす必要があります。
- 一般従事者として薬剤師・登録販売者の管理および指導のもとで実務に従事すること
- 登録販売者(研修中)として薬剤師・登録販売者の管理および指導のもとで実務に従事すること
- 登録販売者として業務に従事すること(店舗管理者または区域管理者としての業務を含む)
ここで指す「店舗責任者」はドラッグストアや薬局においての責任者としての立場です。一方で、区域管理者は配置販売業という販売形態において、責任者として薬の販売やカウンセリングをおこないます。業種には若干の違いが見られるものの、いずれも責任ある立場のため経験やスキルが求められるでしょう。
必要書類の提出が必要
店舗管理者になるには上記で紹介した実務経験のほか「実務(業務)従事証明書」の提出が必要です。これまで勤務したドラッグストアで書類を記入してもらいましょう。この書類を企業に提出することで店舗管理者として働けるようになります。
過去5年間において複数の企業で勤務していた場合は、それぞれの企業に実務(業務)従事証明書を記入してもらいます。
続いては実際に店舗勤務をおこなうケイタ店長へのインタビューを基に、店舗管理者や店長にまつわる疑問を解決していきましょう。
店舗管理者と店長の違いとは?

はじめに、ケイタ店長に店舗管理者と店長の違いについてお聞きしました。
――― 一つの店舗で、店舗管理者と店長を異なる人が担当することはあるのですか?
ケイタ店長「店舗管理者と店長は一般的に兼任するドラッグストアが多い傾向にあります。業務内容も同様ですが、少しずつ違いが見られます。店舗管理者は法律を遵守し業務を遂行する見方や取り組みが必要です。一方で、店長はさらに会社の決まりや店舗内の管理も同時に求められます。
店舗、企業の存続にはパートさんの力が不可欠です。店長は各店舗のパートやアルバイトの雇用を守ることが欠かせません。その方々の雇用を守り、日々話を聞きながら店舗運営を責任者として取りまとめていく必要があります。まれに店舗管理者と店長を異なる人が担当するケースも見られますが、ドラッグストアにおいてはほとんどが兼任していると考えてよいでしょう。」
実際におこなっていた店舗マネジメントの取り組み

次に、ケイタ店長に店舗管理者、そして店長として現場でおこなう業務や心がけについて質問しました。
――― 一般的に店長というとシフト管理や売上管理などヒト・モノ・カネの管理をおこなうイメージです。他に見えない仕事として店舗マネジメントにかかわる業務があれば教えてください。
ケイタ店長「会社の方針にしたがいながらシフト管理や売上管理を実施していくことはもちろん大切です。しかし、それと同時に一緒に働くパート・アルバイトとのコミュニケーションも店舗マネジメントにおいては重要です。」
今回のインタビューにおいて、店舗マネジメントにおける注意点は下記の2つとわかりました。
1.従業員の話は「すべて聞く」
店舗マネジメントにおいて、もっとも重要なポイントは「話を聞く」ことです。もちろん、従業員の中にはわかりあえない方もいます。しかし、店長の立場であれば得意不得意を抜きにして、人と関わり話を聞く姿勢が必要です。
自分から話を聞く姿勢を見せ、すべての従業員に声をかけ続けることで、信頼関係を構築できます。「この人はわかってくれない」と諦めるのでなく、根気強く対話する姿勢が大切です。
2.聞いた後は優先順位をつけて判断する
従業員から話を聞いた後は、優先順位をつけて判断していきます。人のリソースは有限であるため、すぐにすべての提案に対応できるわけではありません。その提案は本当に今すぐやらなければならないことか、本当に効果があるのかを考慮し、実行に移す優先順位をつける必要があります。
従業員から提案があがってくるのは望ましいことである一方、法律や社内の方針を詳しく知らなかったり、お客さまへ与える影響まで考えが及んでいなかったりすることもあります。そんな時には、ただ「できない」と突っぱねるのではなく、「こういう理由があって、そこをクリアしないと採用できない」と丁寧に説明しましょう。
店長は誠意を持って話を聞き、優先順位や守るべきものを意識して対応する力が求められます。
【登販】店舗管理者の経験を活かす転職のコツ

次に、転職のコツをお聞きしました。登録販売者の需要が高まる今だからこそ、ポイントを抑えて転職を成功させましょう。
1.経歴は数字で記載
――― 内定を目指すには、どのような数値をアピールしたらよいのでしょうか?
ケイタ店長「あくまで客観的に見て『自社に貢献してもらえそうな人材だ』と判断できる数値の記載が必要です。ここでは売上だけでなく単純な費用対効果では表現できないものへの対策や人を育てた具体的な実績などを数値で記載します。
一般的に履歴書においては自分が担当した店舗の売上について記載する方が多く見られます。しかし、売上は店長である自分の功績ではありません。会社が販促をおこなった、コロナウイルスが流行した、など様々な要因が絡み合って売上に反映されています。
選考においては、『対応の質を高めるために、パートさんの登録販売者を◯人増やした』『費用対効果が見られなかったチラシ配布を止め、Webでの販促をおこなった結果、コストを◯%削減できた』など売上以外の数値アピールが大切です。」
2.「会社」でなく「店長としての自分」が主語
ケイタ店長「売上は会社や携わる従業員全員の取り組みが反映されます。しかし、転職では企業のことを聞かれているのではなく『あなた自身』のことを聞かれています。店長として自分はどうしたかを意識して数字や実績を伝えましょう。もしも転職を検討しているのなら業務中にアピールできる数値をメモしておくのもよいですね。」
3.貢献できる強みをアピール
ケイタ店長「登録販売者のみならず、転職において各企業は『自社に貢献してくれる人材』を探しています。あなたが応募先企業に入ることでどのようなメリットがあるかを考えながら強みをアピールしましょう。
『自分が店長として会社や店舗のために何をしたか』『どのような数値で成果が出たか』を選考時に伝えると、即戦力として採用される可能性が高まります。」
ケイタ店長から管理者を目指す方へのアドバイス

最後に、これから店長や店舗管理者として活躍を目指す方に対して、アドバイスをいただきました。
ケイタ店長「店長や管理者を目指す場合、一緒に働いてくれる人との対話が欠かせません。昔は力でねじ伏せるといった教育や育成が当たり前でした。しかし、近年その流れは消えつつあり、パワハラと呼ばれてしまうこともあります。
会話を通して信頼を積み重ね、円滑な店舗運営を目指すことが店長や管理者に求められます。たとえば、出勤している人と笑顔で話す、忙しかったとしてもイライラした様子は見せないといったことが大切です。そして、パートさんには『困ったことはない?』と声かけをすることもおすすめです。
登録販売者として、店長として働く中で会社からの方針とパートさんからの意見、双方の立場に挟まれて潰れそうになることもあります。そんな時は切迫度と効果を考慮して、すぐにやることと後でやることを整理しましょう。優先順位をつけて一つずつ解決していくことでやがてよい店舗環境が実現し、従業員同士も円滑なコミュニケーションが取れるようになるでしょう。」
まとめ|店舗マネジメントは「対話」を意識
今回はケイタ店長のお話を基に、店舗管理者の仕事や転職時に注意したいポイントを解説しました。店舗管理者は店長と兼任するケースが多く、法律や会社の規則を守りながらも現場の従業員に寄り添う姿勢が欠かせません。
店舗管理者はお客さまのために店舗を運営していくという姿勢を大切にし、自ら率先し従業員やお客さまとの対話をおこない、よりよい店舗づくりを目指す必要があるでしょう。
【新着】登録販売者のための業界コラム
- 2026年01月09日 【現役ドラッグストア店長直伝】登録販売者が「辞めたい」と思わない3つのメンタル維持法(2026年対策付き)
- 2026年01月07日 2026年ドラッグストア業界の未来図|市場動向・M&A・登録販売者のキャリアと転職のポイント
- 2026年01月07日 登録販売者の年収は低い?現場にインタビューしてリアルな声をお届け!平均給料を調査
- 2026年01月07日 ドラッグストア店長の年収はいくら?平均額の内訳と600万円を目指す昇給のコツ
- 2025年12月03日 【現役ドラッグストア店長直伝】冬商品で接客スキルを劇的に磨く3つのコツ