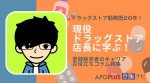【現役ドラッグストア店長直伝】頭痛の接客スキルを磨こう<登録販売者のキャリア>

花粉症商材は春先に嵐のように需要が高まり、花粉の飛散が収束するにつれて需要も徐々に低くなっていきます。
これに対して年間を通じて一定の需要があるのが「鎮痛剤」です。
頭痛に悩むお客さまからの相談は日々の業務で頻繁に発生します。そのため、お客さまから信頼を得られやすいのです。
今回は新人登録販売者の皆さんが頭痛薬の選び方や効果的な接客方法を身につけ、自信を持ってお客さまの相談に応じるためのポイントを解説します。「片頭痛」と「緊張型頭痛」の違いや、市販薬と漢方薬の使い分け、さらにお勧めの接客トーク例まで、頭痛に関する接客スキルを総合的に学べます。
実は「頭痛」の接客と「鎮痛剤」を選ぶ方法は早いうちに覚えておくと登録販売者としてのスキルを伸ばしやすくなるのです。
それでは鎮痛剤と頭痛の知識を学んでいきましょう。
目次
頭痛の基本をおさえておこう

実はOTC(一般用医薬品)の中でも「鎮痛剤」は年間通してもっとも需要が一定で、リピーターが多く、そして悩まれている方も多いジャンルなのです。
さらに薬の基本でもある「単剤」が多くシンプルな構成のため、登録販売者としてのスキルを活かしやすい面があります。お客さまから感謝される機会の多いので「やりがい」が得られやすいジャンルでもあります。
頭痛に悩んでいる人はどれだけいるのか
そもそも「頭痛」は約5000年前のシュメール文明の壁画などにも遺されていて、そこから約3000年もの間は祈祷や薬草などが主な対応方法でした。
そして、ヒポクラテスやベートーベン、ピカソなどの著名人も頭痛に悩まされていたと伝えられています。
太古から人々の悩みでもあった頭痛を緩和させるのが「鎮痛剤」で、人類が史上初めて合成に成功した医薬品も今も主力のひとつである鎮痛剤「アスピリン」でした。
そして現代日本においても「1週間に1回以上頭痛に悩まされている」という人は「3,000万人~4,000万人」とされていて、これは花粉症患者数と近いのです。
つまり核家族の中の1人は頭痛に悩まされている...という計算になります。
さらに、ひとくくりに「頭痛」といっても多くの種類があります。
OTC(一般用医薬品)と親和性がある頭痛は「緊張型頭痛」「片頭痛」「薬物乱用頭痛」なので、この3種類の違いや原因は把握しておく必要があります。
お客さまが把握している場合もありますが、慢性的に使い続けている方に対してアドバイスができるように違いを覚えておきましょう。
片頭痛と緊張型頭痛の決定的な違い
頭痛は「片頭痛」と「緊張型頭痛」が大きなウエイトを占めます。
このふたつの頭痛は正反対といっていいほど原因や対処法が違うため覚えておきましょう。
- 片頭痛
- 原因
- 何らかの原因で脳の血管が拡張し、三叉神経を刺激する。
- 対処
- 拡張した血管を収縮させるために、安静にして冷やす。神経を刺激しないために暗くするのも有効。
- 緊張型頭痛
- 原因
- 主に肩こりからは発生する筋肉が原因の頭痛。
- 対処
- コリをほぐすために温め、軽い運動で血行を促進することで緩和する。
これを覚えておくだけでも接客に役立ちますし、この後に解説する対処法のアドバイスにつなげることができます。
頭痛が発生する時の状況をお聞きし、その後の判断につなげてください。
・片頭痛の特徴
突然発生し、人によってはイラストのような「閃輝暗点」という前兆をともなうことがあります。
これは視野の一部が欠損したり眩しさを感じたりする症状で片頭痛の1~2割の方に現れるため、視野の欠損や眩しさがあるか聞いてみましょう。
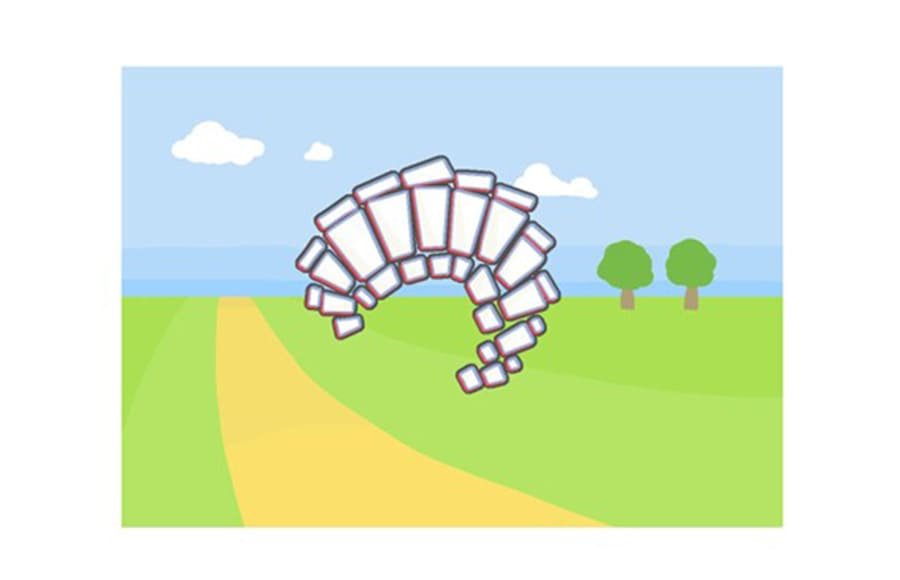
・緊張型頭痛の特徴
主に肩こりなどが原因のため、頭痛が主訴のお客さまに肩こりの有無を聞くのはマストです。
そして緊張型頭痛は温めることで緩和するので「入浴で楽になるかどうか」を聞いて判断しましょう。
片頭痛と緊張型頭痛を併発することも多いため、どちらかを決めつけてしまうのは危険です。
あくまでわたし達は目安をアドバイスすることに徹し、長年頭痛に悩まされていて鎮痛剤を使い続けているお客さまには受診勧奨をおこなうことも忘れないでください。
そしてOTC(一般用医薬品)を販売するにあたって注意すべきは「薬物乱用頭痛」です。
ここは特に注意して接客をおこなってください。
問題の薬物乱用頭痛とは
近年問題となっているのが「薬物乱用頭痛」です。
「薬物依存で起こる頭痛」と誤解しているお客さまもいらっしゃいますが、そうではなく「鎮痛剤の使いすぎで起こる頭痛」です。
【薬物乱用頭痛の基準】
- 1カ月に15日以上頭痛が発生する
- 3カ月以上、「合剤を10日」か「単剤を15日」使用している
- 鎮痛剤を使うことで頭痛が悪化している
この基準が薬物乱用頭痛の診断基準とされています。
わたし達は当然、診断はできないので、よく鎮痛剤を使われるお客さまには「使いすぎで頭痛が悪化する」と一言添えてください。
薬物乱用頭痛の治療は基本的に受診勧奨なのですが、自身でも「鎮痛剤の使用をコントロールする」という対応は可能です。
そのため、このようなお客さまには「頭痛メモ」をとる習慣付けをお勧めしています。
頭痛の発生と鎮痛剤の使用頻度を把握していない方が多いので、客観的にどれだけ使っているのかを把握することで受診の参考にしたり、自身の症状の重さを知ったりするための意識付けになるのです。
その際は単剤か合剤で鎮痛剤の使用基準に差があるので確認してください。
鎮痛剤は催眠鎮静剤が追加配合されているものが多いため、これを機にリスクが低い単剤をお勧めすべきです。
鎮痛剤を使う頻度がわからないお客さまでも、購入頻度からある程度の判断ができるので、購入履歴を調べることが可能なら調べてアドバイスしてみましょう。
それでは鎮痛剤以外での対処方法も考えていきましょう。
頭痛の原因から商品を選ぶコツ

ここまで見てきたように頭痛はさまざまな種類があり、対応方法もまちまちです。
しかしもっとも注意すべきなのは「薬物乱用頭痛」の併発なのです。
鎮痛剤はOTC(一般用医薬品)とはいえ使い方を誤ればデメリットがメリットを上回る可能性は充分にあります。
できるだけ回避し、お客さまのQOLを向上させる方法について考えていきましょう。
鎮痛剤の使い分け
鎮痛剤の使い分けは成分ではなく「単剤」をお勧めすべきです。
理由は先ほども書いたとおり、薬物乱用頭痛のリスクが軽減するためです。
ここで合剤を使うと、軽いとはいえ依存リスクがあることで鎮痛剤の使用頻度が上がります。
ただでさえ催眠鎮静剤はQOLを低下させる要素があるため、あえて選択するメリットはありません。
【接客トーク例】
合剤をお求めのお客さまに対して
「この鎮痛剤は依存性のある成分が配合されているので、鎮痛剤の使いすぎで起こる『薬物乱用頭痛』を併発する可能性がありますし、自動車の運転も法律で禁止されています。」
「デメリットが低く効果も高い商品も発売されているのでご紹介しましょうか?」
そして鎮痛剤を使うタイミングは「痛みが出たら早めに使うこと」です。
我慢ができなくなってから使う方も多いのですが、これでは痛みの伝達物質が多く出てしまい鎮痛剤で対応できなくなることも多いのです。
ここが難しいところなのですが、こうした接客をしているとジレンマが発生してしまいます。
- 鎮痛剤は早く使わないと効果が十分発揮されない
- 鎮痛剤を使いすぎると薬物乱用頭痛のリスクが上がる
そして鎮痛剤も単剤を使ったからとはいえ、使いすぎることで薬物乱用リスクが上がってしまいます。
とくに女性は生理痛で鎮痛剤を使う頻度が上がっているので、それを考慮に入れたうえで接客をおこなってください。
では鎮痛剤の使用頻度を下げる商品は何なのでしょうか。
代表的な漢方薬を覚えておこう
ここで出番なのが「漢方薬」と「鎮痛剤以外の商品」なので覚えていきましょう。
【漢方薬をご紹介する接客トーク】
「鎮痛剤は出てしまった痛みを抑えるだけですが、漢方薬なら体全体の流れを整えて頭痛を緩和できますよ。」
「鎮痛剤の使う頻度を下げると鎮痛剤依存からくる『薬物乱用頭痛』の発症を下げることにつながります。」
頭痛に有効な漢方薬はいくつかあるのですが、ここでは特に効果的なものを3つ紹介しておきます。
経験上、お客さまに喜ばれることが多い漢方薬なのでぜひ覚えてください。
【葛根湯】
葛根湯は体温を上げる漢方薬で風邪の初期症状に使われるお馴染みの漢方薬ですが、緊張型頭痛の症状にピッタリなのでお勧めです。
効能効果をみるとわかりますが「肩こり」「頭痛」が入っています。
つまり「緊張型頭痛」の症状に合うので、肩こりを伴う頭痛のお客さまにお勧めしてみましょう。
常備薬として備えてある方も多いため、鎮痛剤よりも優先して使うと薬物乱用頭痛のリスクを下げることができます。
なお「証」が合わないため「虚証」の方にはお勧めしにくく、高血圧など「注意すること」に記載の持病をお持ちのお客さまには注意してください。
【呉茱萸湯】
呉茱萸湯は片頭痛に効果がある漢方薬です。
効果はかなり高いとされているため、鎮痛剤より呉茱萸湯を優先してもよいかと思います。
呉茱萸湯の「証」は「体力中程度以下」となり「実証」に向かない漢方薬です。
なお呉茱萸湯は「緊張型頭痛」にも効果があるとされているため、虚証で葛根湯が使えない緊張型頭痛のお客さまにもお勧めできます。
【五苓散】
頭痛の分類では「天気頭痛(気象痛)」に向いている漢方薬ですが、片頭痛や緊張型頭痛にも効果的なうえに、すべての「証」に向いている漢方薬のため非常に汎用性が高くお勧めです。
頭痛以外にも「二日酔い」「吐き気」「下痢」「むくみ」などに効果が期待でき、小児も使用できるので登録販売者として漢方薬を勉強する入門としてもお勧めです。
【「証」の見分けかた接客トーク】
「食べ物やストレスなどでよく胃腸の不調がありますか?(虚証は胃腸が弱く、実証は胃腸が強い)」
「最近は暖かくなってきましたが、まだ寒さを感じますか?(虚証は寒がり、実証は暑がり)」
「レストランなどで店員さんを呼んだときに声は届いていますか?(虚証は声が小さく、実証は声が大きい)」
これらの漢方薬を使用し鎮痛剤の使用頻度を減らすことで薬物乱用頭痛のリスクを下げることができます。
もちろん頭痛の症状によっては鎮痛剤との併用も可能ですので接客ツールとして覚えておきましょう。
OTC(一般用医薬品)以外での対応方法
その他にもお勧めできるものは多く店頭に存在します。
【緊張型頭痛】
主に首筋の筋肉のコリからきていることが多いので、使い捨てや電子レンジで加熱するタイプの「温熱器具」がお勧めです。
季節によっては入浴剤もお勧めで「熱すぎない温度でゆっくり体を温めてください」などと一言添えるとよいでしょう。
【片頭痛】
冷やすと改善するため「アイス枕・氷のう」がお勧めです。
「冷却ジェルシート」は実際に冷ますことはできないのですが、お客さまが心地よいと感じるならお勧めしてもよいでしょう。
また明るいと悪化するため「アイマスク」もお勧めです。
最近人気の「温熱タイプのアイマスク」は温めてしまうので避け、トラベル用品のアイマスクをお勧めしてください。
他にも「温める」「冷やす」「暗くする」商品があれば積極的にお勧めしてみましょう。
頭痛の接客で気を付けなければいけないこと

頭痛に悩まされるお客さまはかなり多く、接客機会も年間通して一定のため、気を付けておきたいことも多く存在します。
最後に必ず覚えていないといけないポイントをあげていきます。
ほとんどのお客さまは受診経験がないという事実
頭痛の接客をおこなう時に「過去に頭痛で受診した経験」を聞いてみてください。
かなりの確率で受診していないお客さまが多いことがわかるはずです。
これにはさまざまな心理があります。
- OTC(一般用医薬品)を使って緩和するうえに症状が持続しない
- 病院に行くのが面倒だったり重大な病気が発覚したりするのが怖い
- 頭痛くらい我慢できる
どれもリスクを抱えてしまう心理なのですが、確かに頭痛は一過性であることが多く、市販鎮痛剤を一定期間使うと症状もおさまることから受診を見送りがちなのです。
市販鎮痛剤を我流で使い続けることで悪化の一途を辿り、我慢できなくなってから受診すると治療にも時間やかかるうえに対応しづらくなります。
その点から虫歯と同じといえますが、お客さまの接客の中で「受診」という提案はすべきだと感じます。
受診するとどうなるのか
そもそも受診するとどうなるのか、登録販売者の受験では勉強できていない人も多いので知識として持っておきましょう。
受診すると「二次性頭痛」の検査がおこなわれます。
二次性頭痛とは「病気や外傷によって起こる頭痛」のことです。場合によっては命の危険があるため、頭痛の原因が病気ではないかどうかを調べます。
通常の頭痛なら種類に応じて予防的な治療がおこなわれるので、市販鎮痛剤のような対症療法ではなく症状の頻度が少なくなる治療となります。
とくに片頭痛の治療薬は予防的な飲み薬や、近年は効果的な注射も開発されているので、受診という手段もあるとぜひアドバイスしてください。
受診勧奨すべきラインを覚えておく
最後に受診勧奨のラインと慢性頭痛の方にお勧めする要点をおさらいしておきましょう。
- めまいやふらつき、呼吸が荒いなどの頭痛以外の症状がある
- 1週間以上頭痛が続いている
- 痛みが強い
以上は通常の頭痛ではなく「二次性頭痛」の可能性が高い症状です。
受診勧奨はもちろんですが、救急車を要請してもいいほどの緊急性ですので覚えておきましょう。
これ以外の症状、通常の慢性頭痛の場合は以下のポイントをおさえて接客をおこないましょう。
・鎮痛剤
できるだけ「単剤」を選びましょう。
その際、1カ月に何日鎮痛剤を使用しているかお聞きし「単剤なら15日、合剤なら10日」以上使用しているのなら薬物乱用頭痛の可能性があるため漢方薬などを使用し鎮痛剤の使用頻度を下げるアドバイスをおこないます。
・漢方薬
緊張型頭痛なら「葛根湯」、片頭痛なら「呉茱萸湯」、証が合わなかったり天気頭痛だったりするなら「五苓散」を提案します。
・医薬品以外
緊張型頭痛なら「温熱器具」のような温める商品を、片頭痛なら「アイス枕」のような冷やす商品や暗くする「アイマスク」を提案します。
もちろん商品以外の知識をわかりやすくアドバイスすることで頭痛以外の症状でも相談しやすい登録販売者として認識していただくチャンスでもあります。
頭痛は年間通して接客機会があり、さまざまな商品提案をおこないやすい症状です。
ここで漢方薬や医薬品以外の商品を提案する経験を積むことで、他の症状でも提案する力を養うことができるのです。
まとめ
頭痛に悩む多くのお客さまにとって、ドラッグストアでのあなたの一言が大きな助けとなります。
このコラムで学んだことをもとに、皆さんが今日から実践できるポイントをリストアップしました。これらを参考に接客スキルを磨き、より多くのお客さまのお力になりましょう。
今日から試してみるべきこと
ポイントは4点ですので、しっかり把握しましょう。
頭痛の種類を聞き分ける:お客さまに「痛みの場所やシチュエーション」をお聞きして、片頭痛と緊張型頭痛を見極める。
適切な薬を提案する:鎮痛剤の単剤を基本に、場合によって漢方薬やOTC(一般用医薬品)以外の商品(温熱器具など)を紹介。
受診のアドバイス:重症化や薬物乱用頭痛の疑いがある場合には、積極的に医療機関での受診を進める。
会話を通じて信頼を築く:お客さまの話にしっかり耳を傾け、適切な質問で安心感を提供する。
鎮痛剤前で悩まれているお客さまは毎日いらっしゃいますので、一人でも多くのお客さまにお声がけしてみてください!

執筆者:ケイタ店長(登録販売者)
ドラッグストア勤務歴20年、一部上場企業2社で合計15年の店長経験を活かし、X(旧Twitter)などで登録販売者へのアドバイスや一般の方への生活改善情報の発信を行っている。X(旧Twitter)フォロワー数約5,000人。
【新着】登録販売者のための業界コラム
- 2025年12月03日 【現役ドラッグストア店長直伝】冬商品で接客スキルを劇的に磨く3つのコツ
- 2025年11月21日 現役薬剤師が教える。登録販売者の新人教育マニュアル|OJTの進め方と後輩指導のコツ
- 2025年11月21日 現役薬剤師が伝授|インフルエンザ時に使える解熱剤の見分け方と登録販売者の声かけ技術
- 2025年11月06日 【2026年法改正で必須!】現役店長が教える「OD対策」現場対応完全ガイド 〜登録販売者が押さえるべき「3大変更点」と心構え〜<登録販売者のキャリア>
- 2025年10月30日 登録販売者はブランク後も復職できる!管理者要件と安心して働くためのポイント