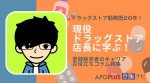【現役ドラッグストア店長直伝】試験勉強では習わないステロイドの歴史<登録販売者のキャリア>

あっという間に虫刺され治療薬の季節が到来しました。
皮膚薬でメインの商品は「ステロイド治療薬」ですが、接客に困る登録販売者も多いのが実情です。
というのも「ステロイド忌避」の方が多く、深く商品説明すると逆に不安になってしまうお客さまが多いのです。
登録販売者として「ステロイドの過去に何があったのか」を理解し、それを踏まえたうえで接客をおこなう必要があります。
今回は正しい知識を押し付けるのではなく「忌避感」の原因を理解し、ステロイド治療薬についての誤解や不安を取り除くための方法を詳しく紹介しています。
登録販売者としてステロイドに対するお客さまの不安を和らげ、安心して商品を選んでいただける接客スキルを身につけることができます。
この記事を読むことで、ステロイドの正しい使用法を理解し、適切な接客サービスを提供できるようになるでしょう。
目次
どうしてステロイドは怖いと思われてしまうのか

皮膚薬の接客をする時に「ステロイド」という単語でお客さまの表情が曇ってしまった...という経験はないでしょうか。
お客さまが抱くステロイドへの恐怖感や拒否反応の背景には、長い歴史と誤った情報の蓄積があることを認識し、接客に活かしましょう。
衝撃だったニュース報道の影響
ステロイドという言葉に対して、多くのお客さまが「なんとなく怖い」「強すぎる」「副作用が出る薬」といった印象を持っているのを感じる方が多いのではないでしょうか。
これらの印象は実は過去のニュース報道が大きく影響しているのです。
そのきっかけのひとつが、1992年にテレビで放送された報道番組のアトピー特集です。
当時のメインキャスターが番組の最後に「ステロイドは最後の最後、ギリギリになるまで使ってはいけない薬」と発言したことが多くの視聴者の記憶に深く残りました。
番組の影響力が非常に大きかった時代ということもあり、翌日から全国の皮膚科やドラッグストアで「ステロイドは使いたくない」という声が急増したといわれています。
中には医師から処方された外用薬を使わずに病状を悪化させてしまった例もあったようです。
お客さま自身の体験によるものではなく実際には使ったことがなかったり、昔に少し使ったことがある程度なのに強い拒否反応を示されるケースもあります。
これは家族や知人、テレビや雑誌の情報をきっかけとした「刷り込まれている恐怖感」であることも多いのです。
登録販売者としてこうした背景があることを理解し、単に「炎症を抑える成分」と説明するだけでなく、お客さまの不安に寄り添いながら正しい知識を伝える必要があります。
- ・「以前、テレビなどで不安になる情報が出たことがあったんですよ」
- ・「でも、今は使い方を守ればとても安全で効果的なんです」
- ・「量や期間をきちんと守ることが大切なんです」
重要なのは「怖い」と思っている気持ちを否定しないことです。
怖いと思うのはお客さまのせいではないのです。
不安を増幅させた雑誌やネットの存在
テレビ番組によって「ステロイド=怖い薬」というイメージができあがり、その印象をさらに強めてしまったのが雑誌やインターネットの存在です。
1990年代から2000年代にかけて、週刊誌などで「ステロイド副作用の恐怖」といった見出しが数多く登場しました。
花粉症の方の行動は、理由は何であれ次の3パターンです。
「顔が赤く腫れ上がった」「薬をやめたら全身に発疹が出た」「ステロイド依存で抜け出せなくなった」などです。
こうした副作用があることも事実ですが、それらは長期間、適切でない方法で使用した結果であるケースがほとんどでした。
しかしこうした報道では「正しく使えば安全」という前提なしでステロイド自体が危険であるかのような印象を与えてしまいました。
またネットの普及とともにSNSや個人ブログでも「脱ステロイド体験談」が拡散され、誤った情報が広がってしまったのです。
登録販売者として、このような印象を持っているお客さまがいるということをふまえたうえでの接客が必要です。
- ・「そういう情報、多いですよね。実は私も最初は不安だったんです」
- ・「今は正しく使えば安全で効果的だということが医学的に証明されているんですよ」
- ・「昔と今では使い方や考え方が変わってきてるんですよ」
お客さまが「怖い」と思ってしまうのは誤った情報を信じたからではなく「信じたくなるような体験談や言葉」があったからです。
否定するのではなくクッション的に理解や共感を示すことで接客の糸口が見えてくるのです。
アトピービジネスの存在を知っておこう
ステロイドを避けたいという気持ちに付け込んだ商法が「アトピービジネス」と呼ばれています。
これは、「ステロイドは危険」という不安を利用して、高額なスキンケア商品や民間療法を売り込む業者がおこなっているものです。
これらは科学的根拠が乏しい商品が多く治療効果が証明されていないどころか、かえって肌の状態を悪化させてしまうケースもあります。
特にインターネットやSNSでは「体験談風」の広告が多く真偽の見極めが難しくなっています。
登録販売者として「なぜこのお客さまはステロイドを避けたいのか」を丁寧に聞き、もし不安の背景にこうした商法の影響があると感じたら忌避感を取り除くように説明しましょう。
- 「この人気の虫刺され治療薬は使ったことありませんか?実はこれもステロイド剤なんです。」
- 「最近のステロイド剤は吸収後に分解される『アンテドラッグステロイド』というものなんです。」
- 「『ステロイドの副作用』で騒がれたのは「飲み薬」や「最強ランク」のステロイドです。このステロイド剤はランクが低く幼児でも使用可能ですよ」
「正しい情報で安心できる選択ができるようにする」ことが私たち登録販売者の役目であり、責務です。
「脱ステロイド」への理解と接客

お客さまがステロイドに対する忌避感を抱いていると感じたときはまずは共感から入る必要があります。
ではこうしたお客さまの状況を考えてみましょう。
お客さまの気持ちを理解しよう
接客の中でステロイドを避けたいというお客さまの言葉を聞くと、登録販売者として疑問に思うもしれません。
しかしまずその気持ちに寄り添ってみましょう。
多くのお客さまは「過去に副作用が出た」「家族や友人に使ってはいけないと言われた」「ネットやテレビで怖い話を見た」といった、何らかのきっかけをもとに不安を感じています。
そしてその不安は理屈ではなく感情なので、いくら「安全」「大丈夫」と言葉だけで伝えても、すんなりとは受け入れてもらえないのです
たとえば、過去にステロイドを使用して皮膚が赤くなったり、乾燥がひどくなった経験がある方は、「また同じことが起きたらどうしよう」と心配になります。
また、お子さんに使用する場合は「小さい体に強い薬を使うのが怖い」と感じる親御さんも多くいらっしゃいます。
ここで私たち登録販売者がすべきことは、まず「その不安はよくわかります」と共感することです。
そして「今は使い方を守ればとても安全に使えるようになっています」とまずは安心していただきましょう。
正しい情報を届けることも大切ですが、その前に「この人は話を聞いてくれる」と思ってもらえる空気を作ることが基本であり信頼関係を築く第一歩です。
急な中止で起こるリバウンド現象の存在
ステロイド外用薬を自己判断で急に中止してしまうと「リバウンド」と呼ばれる強い症状の再発が起こることがあります。
リバウンドとは、薬の使用を中断した直後に、炎症やかゆみ、赤みなどの症状が以前よりも強く現れる現象です。
特にアトピー性皮膚炎などで長期的に使っていた場合、皮膚のバリア機能が弱っているため、このような症状が起こりやすくなります。
このとき、お客さまは「やっぱりステロイドは怖い」と感じてしまい、さらに忌避感が強まってしまうこともありますが、実際にはこれは副作用ではなく急な中止による反応であることが多いのです。
このような反応が起こる可能性があることを把握しておき、お客さまから「やめたらひどくなった」と相談された場合は、「それは急に薬をやめたことによるリバウンドかもしれません」と説明することが大切です。
ステロイド剤の使用を中止する場合は医師の指導のもと、徐々にステロイドのランクや使用量を落としていく方法が推奨されていることも伝えておくと、お客さまの不安軽減につながります。
ネットに多数存在する体験談の影響
インターネットやSNSにはステロイドに関する体験談が数多く投稿されており、それらが購買や使用の判断に大きな影響を与えているのが現状です。
たとえば「脱ステロイドで肌がきれいになった」「自然派クリームに切り替えてよくなった」というような前向きな体験談は、希望に満ちていて魅力的にも感じられます。
しかしそうした話の裏側には離脱症状を経た過程があったり、一部の人にしか当てはまらないケースであったりすることも少なくありません。
さらに、民間療法や高額な代替商品に誘導するような投稿も多く、正しい医療情報と混ざって発信されているため、情報の取捨選択が難しくなっています。
登録販売者として重要なのは、「ネットの情報が間違っている」と真っ向から否定しないことです。
- 「体験談ってすごくリアルで参考になりますよね」
- 「ただ、お肌の状態や症状は本当に人それぞれなので、合う・合わないが出やすいんです」
と、事実ベースの情報に引き戻してあげるのがポイントです。
情報過多の時代だからこそ、信頼できる人からの説明が、お客さまにとって大きな安心につながることを忘れずに接客しましょう。
ステロイドの接客はどうすべき?

では実際の店頭での接客はどうすべきでしょうか。
想定されるパターンや問題を深く堀り下げてみましょう。
若年層にも存在する「ステロイド忌避」の理由
ステロイドに対する忌避感は中高年層だけのものではなく、ステロイドバッシングがおこなわれた頃に生まれていなかったり幼少期だった10代〜30代の若い世代にも「ステロイドは使いたくない」という声が存在します。
むしろ、ネットリテラシーが高い世代ほど情報過多によって不安を抱えていることが多いのです。
若年層の忌避感の背景には、SNSやYouTubeなどの動画コンテンツで広がる脱ステロイド体験談や、自然派・オーガニック志向の影響があります。「ステロイドをやめて肌がきれいになった」「使ってたらどんどん悪化した」というような投稿は、画像やビフォーアフター付きで拡散され、説得力を持ってしまいます。
また、情報を自分で調べて判断する文化が根づいている世代でもあるため、「店員にすすめられたから」では納得してもらえません。
資格者の意見よりネットの口コミを優先してしまう...などという場面に遭遇した方も多いはずです。
だからこそ、登録販売者の立場としては「正しさ」よりも「納得感」を意識した接客が求められるのです。
「医療ネグレクト」につながる可能性
「子どもには絶対にステロイドを使いたくない」という声も店頭ではよく耳にします。
親としての愛情や不安から出てくる言葉ですが、実はこの「善意」が「医療ネグレクト(医療的な無視や放置)」につながってしまう可能性があるのです。
かゆみで眠れなかったり皮膚が割れて痛がっている...といった状態を「薬を使いたくないから」と放置したり代替療法で対応すると症状が悪化し、感染症を引き起こすリスクもあります。
さらにアトピー性皮膚炎が重症化した場合、顔の強い炎症から白内障や視力低下などの合併症が起こることも知られています。
小さいお子さまの症状の接客時には受診の有無の確認は必須ですし、このような状態のままステロイドを使用せずに幼少期を過ごしてしまった方には注意してください。
必要に応じて受診勧奨をおこない、正しい医療を受けさせるよう促すのも登録販売者の役割です。
登録販売者としてできること
ステロイドに対する不安を持つお客さまに接する際、私たち登録販売者ができることは「正解を押し付けること」ではなく、「選択肢を整えること」です。
薬の専門家としての立場は大切ですが、接客のゴールは「納得して安心して帰っていただくこと」であり「信頼を得て再来店していただく」ことです。
そのためには薬の知識と同じくらい信頼されるコミュニケーションが求められます。
大切なのは「怖い」と感じる気持ちに共感することです。
「そのお気持ち、すごくよくわかります」と言葉に出して伝えるだけで、お客さまの緊張感はぐっと和らぎます。
次に「正しい情報」をかみ砕いて伝えることも必要です。
たとえば「これは強さが一番弱いタイプで、赤ちゃんにも使われることがあるんですよ」など、使用のハードルを下げる情報をやさしく加えてあげるとお客さまも安心しやすくなります。
それでも不安が強いお客さまには、非ステロイド系の選択肢を紹介しつつ、「もし症状が長引いたら、皮膚科で診てもらうのも一つの方法です」と受診勧奨を添えるのも大切な役割です。
私たち登録販売者の責務は「薬を売る」だけではなく「薬の使い方を案内してQOLを向上させること」です。
迷っているお客さまに少しでも安心できる判断のお手伝いをするためにも、積極的にお声がけしてみましょう!

執筆者:ケイタ店長(登録販売者)
ドラッグストア勤務歴20年、一部上場企業2社で合計15年の店長経験を活かし、X(旧Twitter)などで登録販売者へのアドバイスや一般の方への生活改善情報の発信を行っている。X(旧Twitter)フォロワー数約5,000人。
【新着】登録販売者のための業界コラム
- 2025年12月03日 【現役ドラッグストア店長直伝】冬商品で接客スキルを劇的に磨く3つのコツ
- 2025年11月21日 現役薬剤師が教える。登録販売者の新人教育マニュアル|OJTの進め方と後輩指導のコツ
- 2025年11月21日 現役薬剤師が伝授|インフルエンザ時に使える解熱剤の見分け方と登録販売者の声かけ技術
- 2025年11月06日 【2026年法改正で必須!】現役店長が教える「OD対策」現場対応完全ガイド 〜登録販売者が押さえるべき「3大変更点」と心構え〜<登録販売者のキャリア>
- 2025年10月30日 登録販売者はブランク後も復職できる!管理者要件と安心して働くためのポイント