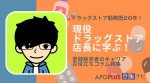【現役ドラッグストア店長直伝】虫よけ剤の本当の意味と使い方<登録販売者のキャリア>

例年より早く真夏日が到来し、本格的な夏シーズンがやってきました。
これから真夏にかけて売上の伸長が見込まれるのが「虫よけ剤」です。
登録販売者の皆さまの店舗でも虫よけ剤の売上が伸びていると思いますが、虫よけ剤の知識はインプットできていますか?
「皮膚薬は勉強したけど虫よけ剤は全部同じ」「防除用医薬部外品より医薬品が効く」などと思っていませんか?
実はほとんどのお客さまが知らない「虫よけ剤の本当の意味」があるのです。
登録販売者としてこれを知らずにお客さまに正確な情報をお伝えできません。
今回は虫よけ剤の種類や形状の特性を解説し、お客さまの生活シーン別の提案方法も紹介します。
お客さまにとってもメリットが大きく登録販売者としてもスキルアップできるので、今回のコラムを理解し身につけておきましょう!
目次
虫よけ剤の落とし穴を把握しておこう

夏に需要が高まる虫よけ剤ですが、接客はしていますか?
「会社指示だから」「医薬品だから」と安易にお勧めするのではなく根拠と自信をもって接客できるよう、虫よけ剤の仕組みを理解しておきましょう。
そもそも「虫よけ剤」はどうして効く?
「虫よけ」という言葉を聞くと「虫が近付けない」と受けとってしまう人も多いですが、なぜ虫に刺されなくなるか知っていますか?
実は虫よけ剤は蚊のような「吸血する虫」にしか効かないのです。
どうして蚊はピンポイントで人を見つけられるのでしょう。
それは人が呼吸で吐き出す二酸化炭素や、体から発する体温、そして汗に含まれるにおいなどを感知して近付いてくるのです。
虫よけ剤は蚊などの「感知するセンサー」を一時的に鈍らせたり、方向感覚をくるわせたりする働きをしているのです。
つまり蚊を殺虫したり、衣類の防虫剤のような働きをするのではないのです。
蚊のセンサーを鈍らせることで、人に近付いても「肌がどこにあるのか分からない」状態になり、刺せなくなってしまうのです。
虫よけ剤は肌に「蚊が刺せない膜」を張るようなもの...ともいえます。
この理屈を分かっていないと接客で表面的なことしかいえなかったり、使用方法のアドバイスができなくなってしまいます。
「蚊の方向感覚が分からなくなって肌を刺せなくなる」ということは覚えておきましょう。
虫よけ剤を使っても刺されるのはどうして?
「虫よけ剤を使っても刺された」という経験やお客さまからの話を聞いたことは皆さんもあると思いますが、これはなぜだと思いますか?
虫よけ剤の特徴でもある「蚊の方向感覚が分からなくなって肌を刺せなくなる」機能が働いていない...ということでもあります。
結論からいえば、塗れていないのです。
原因は商品の効果ではなく、実は塗り方に問題があることがほとんどなのです。
先ほど「虫よけ剤は肌に蚊が刺せない膜を張るようなもの」と書きましたが、もしその膜に塗り忘れによる「穴」がたくさん開いていたらどうなってしまうでしょう?
そう、その穴に止まった蚊に刺されてしまうのです。
特に人気のスプレータイプの虫よけ剤だと吹きかけただけで満足してしまいがちです。
しかしそれだけでは肌の表面に均一に行き渡っていないため、塗りムラができてしまうのです。
接客の際は「スプレー後に手でしっかり塗り広げるか、手にスプレーして塗ってください」と一言添えてください。
塗り広げるだけも虫よけ効果はアップするのでお客さまにも満足していただけるはずです。
形状別のメリットとデメリット
店頭にはエアゾールスプレーやポンプスプレー、ジェルタイプなど多くの虫よけ剤が存在します。
それぞれの特徴をしっかり説明できると、登録販売者としての信頼感がぐっと高まります。
代表的な形状のメリットとデメリットを見ていきましょう。
・エアゾールスプレータイプ
ガス式で噴射するタイプで広範囲に一気に吹きかけられるため楽に使用できます。
サラサラした使用感の商品が多く服の上から使えるタイプもあるのでお出かけ前にサッと使いたいときに便利です。
ただ薬剤を吸い込んでしまいやすかったり、塗りムラが発生しやすいデメリットが存在します。
また地域にもよりますが使用後に廃棄するのが手間だったり、ガスを使っているので火の近くでは使えない、飛行機に持ち込めない、という欠点もあります。
・ポンプスプレータイプ
ガスを使っていないので、スプレータイプに比べて吸い込むリスクが低く、室内でも比較的安心して使えます。
飛行機に持ち込める商品が多く、必要な分だけプッシュして使えるので量の調節もしやすいのでもっとも人気のタイプです。
ただ一度に出る量が少なく、腕や足全体など広い範囲に使うには何度もプッシュする必要があります。
エアゾールタイプと同じく、塗りムラが発生しやすいため肌に吹きかけた後に手で塗り広げる必要があります。
・ジェルタイプ
肌に直接塗るため塗りムラなく均一に塗ることができます。
薬剤が飛び散る心配がないので、小さなお子さまに塗ってあげる時や顔周りなどに使いたい時に便利です。
デメリットは塗るのに時間と量が必要な点です。
時間がないときなど使いづらいタイミングがあります。
他にもシートタイプやシールタイプが販売されています。
シートタイプはコストパフォーマンスが悪く、シールタイプは成分がハーブ系なので効果が低いのが難点です。
お客さまの使用用途や小児に使うかどうか、よく確認したうえでお勧めしてください。
虫よけ剤の成分の特徴を覚えておこう

では虫よけ剤の成分を確認していきましょう。
大きく分けて「ハーブ系」「ディート」「イカリジン」の3種類です。
それぞれ使用できる年齢や適用害虫が違うので把握しておきましょう。
ハーブ系の特徴と効果
レモングラスやシトロネラ、ユーカリ油といった植物由来の精油(エッセンシャルオイル)を使った「ハーブ系」の虫よけ剤です。
主にベビー用品売場などでシールタイプのものが販売されています。
このハーブ系は他の成分と異なり「蚊の方向感覚が分からなくなって肌を刺せなくなる」ものではありません。
つまり蚊のような吸血系の害虫以外にも効果があります。
ただし効果の強さや持続時間が、医薬品成分に比べて弱いということは覚えておきましょう。
また天然成分だからといって誰の肌にも絶対に安全ではなく、植物に対してアレルギー反応が出てしまう方がいることも覚えておきたいポイントです。
このタイプの最大の魅力は、やはり天然由来という安心感です。
化学成分であるディートなどに抵抗がある方や、小さなお子さまのために少しでも優しいものを選びたいと考える方から特に人気があります。
ディートの特徴と適応害虫
お店に並んでいる医薬品と書かれた虫よけ剤の多くに、この「ディート」が使われています。
ここ数年でイカリジンの商品が急増しましたが、それでも根強い人気があるのがディートです。
実はこのディートは第二次世界大戦中に兵士たちをマラリアなどを運ぶ蚊から守るためにアメリカ軍が開発したという歴史があります。
効果は非常に信頼性が高く世界中で長く使われ続けているのです。
ディートの最大の特徴は「対応できる害虫の種類の多さ」です。
害虫の種類は商品の申請内容によって異なりますが、基本的に以下の害虫が適応害虫となります(メーカーによって違います)。
蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ツツガムシ(医薬品のみ)、ヤマビル(医薬部外品のみ)
そして濃度が12%以上になると医薬品扱いとなるため、登録販売者が販売する商品となります。
海外では50%濃度のものも販売されていますが現在日本では30%が最高濃度となります。
近年は30%のものが人気のため、12%濃度の商品はほとんど販売されていません。
なおディートには以下のような年齢制限があります。
12%以下...生後6カ月未満使用不可、6カ月~2歳未満1日1回、2歳~12歳未満1日3回以内
30% ...12歳以下使用不可
ディートのメリットは適用害虫が多いこと、デメリットは年齢制限と使用回数が決められていることです。
イカリジンの特徴と適応害虫
ディートは年齢制限があったり独特のニオイがあることから、ドイツで開発されて登場したのが「イカリジン」です。
ここ数年、ドラッグストアの棚でもこのイカリジンを配合した商品が増えてきたように、小さなお子さまを持つお客さまを中心に販売が伸びています。
イカリジンの最大の特徴は「年齢や使用回数の制限がない」ということです。
生後6カ月未満の乳児にも使用回数制限がなく使用できるため、安心して使用できる虫よけ剤として人気です。
ここまで聞くとディートよりも優れていそうですが、もっとも違うのは肝心の適用害虫です。
イカリジンの適用害虫は以下の通りです(メーカーによって違います)。
蚊、ブユ、アブ、イエダニ、マダニ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヌカカ、ヤマビル
日常生活を送るうえでは大きな問題はないので、親子で使える虫よけ剤といえます。
お客さまの生活シーンに合わせた接客法

ではお客さまの需要に対してどう対応したらよいのでしょう。
具体的なパターンで考えてみましょう。
形状から考えてみよう
形状は現在ではスプレータイプが主流となっています。
スプレーは2種類ありますが、お勧めするのは「ポンプタイプスプレー」です。
消費者目線で使用時の状況を考えると、エアゾールタイプは一気にスプレーを吹きかけて終わってしまうことが予想されます。
もちろんポンプタイプもスプレーしただけではかなり「塗りムラ」が発生してしまいます。
このため必ずスプレー後に「塗り広げる」という作業をおこなわないとせっかくの虫よけ剤の本来の力を発揮できません。
特に小さなお子様には「大人が自分の手にスプレーし、子どもの体に塗布する」のがもっとも効果的です。
この流れから「ジェルタイプ>ポンプスプレー>エアゾール」がお勧めとなります。
成分で考えてみよう
では成分から考えてみましょう。
イカリジンが登場したことにより、ハーブ系の需要は大きく下がりました。
ハーブ系の虫よけ剤に需要があるのは「薬剤を使いたくない」というお客さまなので、他に代替商品はほぼありません。
無理に薬剤をお勧めするのはリスクがあるため、店頭に非薬剤の商品があるのならそちらをお勧めしてください。
こうなると比較対象は「防除用医薬部外品か医薬品か」「ディートかイカリジンか」ということになります。
・防除用医薬部外品か医薬品か
これはどちらの成分でも「濃度」が違う、ということです。
実は虫よけ剤の濃度は効果ではなく「日焼け止め」のSPF数値とよく似ているのですが「持続時間」なのです。
環境や汗の量などがあるので一概に数値では表記できないのですが、あくまで参考として下記の持続時間を覚えておいてください。
- ディート
- 30%:5~8時間
- 10%:3~5時間
- 5%~10%未満:1~3時間
- イカリジン
- 15%:6~8時間
- 5%:6時間未満
もちろん汗を拭ったりすると落ちるため塗り直しが必要です。
・ディートかイカリジンか
ではディートとイカリジン、どちらがお勧めなのでしょう。
大きな違いは「年齢制限」と「適用害虫」です。
ディートには年齢制限があるため、防除用医薬部外品でも生後6カ月未満は使用できません。
また医薬品でも12歳未満は使用できないので注意が必要です。
ディートをお勧めするのは中学生以上、と覚えておくと間違いはありません。
お子さまがいるのならイカリジンの商品を提案しましょう。
ではディートはどんな時にお勧めなのでしょうか。
それは「アウトドアのレジャー」です。
適用害虫を比較すると、もっとも大きいのは「ツツガムシ」です。
イカリジンにはツツガムシが含まれていないのです。
ツツガムシは「ツツガムシ病」という感染症を媒介するダニの一種です。
北海道と沖縄以外で確認されていて、1980年代から急増しているので注意が必要です。
【ツツガムシ病とは】
- 感染すると5~14日の潜伏期間を経て、39℃以上の高熱を発症し数日後に全身に発疹が現れる
- ワクチンはない
- ヒトからヒトへは感染しない
- 対策は「刺されない」こと
- 野山や草地、耕作地に生息
夏休みなどでキャンプや釣りなど、アウトドアなどをおこなうのであれば、イカリジンではなくディートをお勧めしてください。
ディートが使用できない年齢の場合は、イカリジンを使用したうえで長袖や長ズボンで肌を覆うのが唯一の予防なのでお伝えしてください。
注意しなければいけないパターンとは?
虫よけ剤に限りませんが、医薬品や医薬部外品の販売で重要なのが「用法容量を守る」ということです。
虫よけ剤で大きな健康被害は起こりにくいのですが、だからといって守らなくてもいいわけではありません。
特に注意しなければいけないパターンは「使用禁止の年齢のお子さまを連れたお客さまがディート剤を購入した場合」です。
この場合は必ずお声がけをしましょう。
そもそも虫よけ剤を「医薬品」と認識して使用しているお客さまは少ないのです。
商品パッケージの説明も文字が小さく読みにくいため、お声がけは必須です。
まとめ
では今回のまとめです。
・虫よけ剤が効くしくみ
吸血する害虫がヒトを察知するセンサーを狂わせ「方向感覚を分からなくさせることで肌が刺せなくなる」という成分です。
・どの形状の虫よけ剤がお勧めか
この理由により「塗りムラ」が致命的となります。
「ジェルタイプ>ポンプスプレー>エアゾール」がお勧めです。
・ディートかイカリジンか
12歳以上で日常生活だったらどちらでも問題ありません。
12歳以上やアウトドアでの使用ならディート剤を優先してください。
以上を把握しておくだけでお客さまの安全が守られるだけでなく、信頼性も増します。
なかなか声掛けする売場ではなかった...という登録販売者の方はぜひお声がけしてみてください!

執筆者:ケイタ店長(登録販売者)
ドラッグストア勤務歴20年、一部上場企業2社で合計15年の店長経験を活かし、X(旧Twitter)などで登録販売者へのアドバイスや一般の方への生活改善情報の発信を行っている。X(旧Twitter)フォロワー数約5,000人。
【新着】登録販売者のための業界コラム
- 2025年12月03日 【現役ドラッグストア店長直伝】冬商品で接客スキルを劇的に磨く3つのコツ
- 2025年11月21日 現役薬剤師が教える。登録販売者の新人教育マニュアル|OJTの進め方と後輩指導のコツ
- 2025年11月21日 現役薬剤師が伝授|インフルエンザ時に使える解熱剤の見分け方と登録販売者の声かけ技術
- 2025年11月06日 【2026年法改正で必須!】現役店長が教える「OD対策」現場対応完全ガイド 〜登録販売者が押さえるべき「3大変更点」と心構え〜<登録販売者のキャリア>
- 2025年10月30日 登録販売者はブランク後も復職できる!管理者要件と安心して働くためのポイント