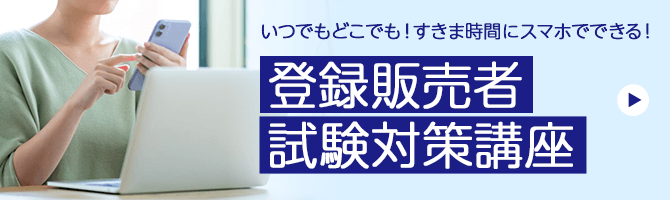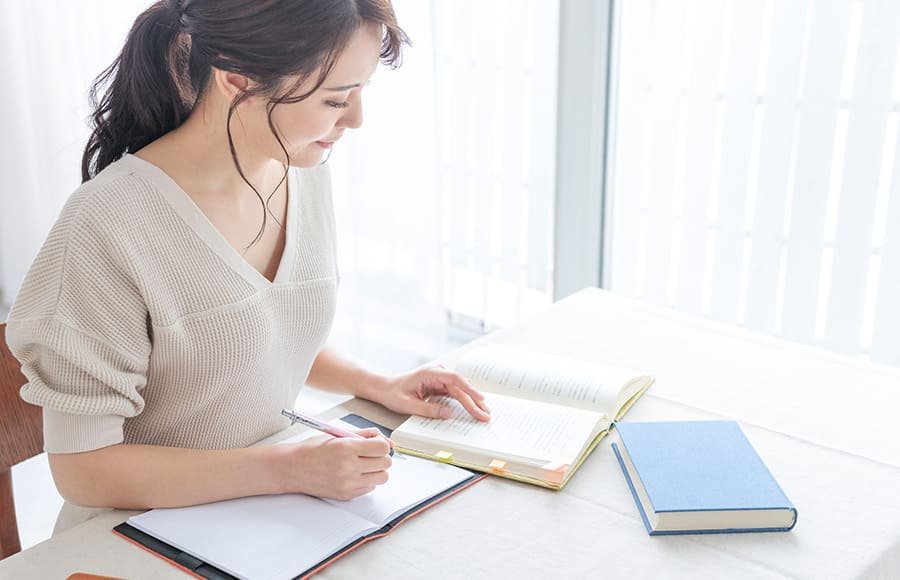【登録販売者試験対策】第2章「人体の働きと医薬品」の頻出内容・学習のコツを解説!

登録販売者試験の第2章で出題される3つのテーマは、「人体の構造と働き」、「薬が働く仕組み」、「症状からみた主な副作用」です。第2章を効率よく攻略することで、余裕をもって第3章以降の学習を進められます。ぜひ、成功を目指して自身のペースに合った計画で勉強を進めましょう。
本記事では、第2章の頻出項目や攻略法を解説します。ぜひ、試験勉強の参考にしてください。
目次
登録販売者試験の第2章 試験の出題範囲と問題数

第2章の出題範囲は、以下の表の通りです。
第2章は全部で20問が出題されます。このうち「人体の構造と働き」がもっとも問題数が多く、第2章の山場です。その後に続く、「薬が働く仕組み」と「症状からみた主な副作用」では、一般的な常識の範囲で解ける問題も多く出題されます。そのため、まずは「人体の構造と働き」から学習に取り組んでいきましょう。
| 項目 | 学ぶ内容 | 問題数 | |
|---|---|---|---|
| Ⅰ | 人体の構造と働き | 各臓器の役割 | 10問前後 |
| Ⅱ | 薬が働く仕組み | 薬の吸収・分布・代謝・排泄、各剤形の特徴 | 5問前後 |
| Ⅲ | 症状からみた主な副作用 | 全身的な副作用、精神神経系の副作用、局所的な副作用 | 5問前後 |
登録販売者試験の第2章 頻出項目と学習のポイント

それでは、先ほどの3つの各テーマについて、頻出項目と学習のポイントを見ていきましょう。
「身体の構造と働き」の頻出項目と学習のポイント
<頻出項目>
「身体の構造と働き」でとくに頻出の項目は、「消化器系」と「循環器系」です。これらの項目では、1回の試験でそれぞれ2~3問ずつ出題されることがあります。
一方、出題頻度の低い項目は「感覚器官」、「骨格系」、「筋組織」です。とくに「感覚器官」は、目・鼻・耳と出題範囲が広く覚えることが多いにもかかわらず、「目」で1問、「鼻・耳」で1問もしくは出題されない時もあり、かけた時間に対して成果が出にくい分野です。
なお、その他の項目は、まんべんなく1問ずつ出題される傾向があります。
【「身体の構造と働き」における各項目の頻出度】
| 分類 | 項目 | 頻出度 | 1試験あたりの平均問題数 |
|---|---|---|---|
| 胃・腸、肝臓、肺、心臓、腎臓などの内臓器官 | 消化器系 | A | 3問 |
| 呼吸器系 | A | 1問 | |
| 循環器系 | A | 1~2問 | |
| 泌尿器系 | A | 1問 | |
| 目、鼻、耳などの感覚器官 | 目 | A | 1問 |
| 鼻 | C | 2項目で0~1問 | |
| 耳 | C | ||
| 皮膚、骨・関節、筋肉などの運動器官 | 外皮系 | A | 1問 |
| 骨格系 | B | 2項目で1問 | |
| 筋組織 | B | ||
| 脳や神経系の働き | 中枢神経系 | B | 0~1問 |
| 末梢神経系 | A | 1問 |
<学習のポイント>
身体の構造の学習では、文字だけでなく、イラストで頭に入れるのが効率的です。臓器の形や位置を確認しながら学習を進めましょう。また、各臓器の役割を覚えるのが苦手に感じる方は、頻出の項目から先に取り組み、出題頻度が低い項目は試験直前に取り組むなど、学習順を工夫するとよいでしょう。
なお、「消化器系」の分野では、覚えるべき消化酵素の種類が多く、つまずいてしまう方もいます。ここで時間をロスしてしまうのは非常にもったいないので、「苦手だな...」と感じる部分が出てきたら、学習を後回しにしてください。
「薬が働く仕組み」の頻出項目と学習のポイント
<頻出項目>
「薬が働く仕組み」は、「薬の吸収・分布・代謝・排泄」と「各剤形の特徴」の2つのテーマにわかれます。どちらも必ず出題されますが、難易度が高いのは「薬の吸収・分布・代謝・排泄」です。「各剤形の特徴」については、時間をかけて学習する必要はなく、過去問を何回か解けば攻略可能です。そのため、「薬の吸収・分布・代謝・排泄」を重点的に学習しましょう。
<学習のポイント>
「薬の吸収・分布・代謝・排泄」は、前項の「身体の構造と働き」の総まとめのような分野です。ここで必ず理解しておきたいことは、「全身作用と局所作用の違い」と「薬の吸収、代謝、分布、排泄のそれぞれの役割」、「肝初回通過効果」です。
このうち、苦手な方の多い「薬の吸収、代謝、分布、排泄」では、まずはそれぞれの言葉の意味と、それがどの臓器でおこなわれるのかを把握してください。次に、体の中で薬がどのように巡っていくのかを「流れ」で理解しましょう。
【吸収、代謝、分布、排泄の言葉の意味】
- 吸収:有効成分を体内に取り込むこと
- 代謝:有効成分が体内で化学的に変化すること
- 分布:有効成分が循環血液中に入り、組織に移行すること
- 排泄:代謝された有効成分が体外へ排出されること
【内服薬の吸収、代謝、分布、排泄の流れ】
- 胃で溶解し、小腸で吸収される
- 門脈を経由し、肝臓で代謝される
- 心臓から血流に乗って全身に分布する
- 腎臓から尿中に排泄される
「症状からみた主な副作用」の頻出項目と学習のポイント
<頻出項目>
第2章の最後のテーマである「症状からみた主な副作用」は、一般的な常識の範囲内で解ける問題も多いので、リラックスして学習を進めてください。超頻出の項目は、上位から「呼吸器系に現れる副作用」「皮膚に現れる副作用」「消化器系に現れる副作用」「重篤な皮膚粘膜障害」です。ここを境にして出題頻度が下がります。
【頻出の副作用ランキング】
- 第1位 呼吸器系に現れる副作用 → 間質性肺炎、喘息
- 第2位 皮膚に現れる副作用 → 接触皮膚炎、光線過敏症、薬疹
- 第3位 消化器系に現れる副作用 → 消化性潰瘍、イレウス様症状(腸閉塞様症状)
- 第4位 重篤な皮膚粘膜障害 → 皮膚粘膜眼症候群(SJS)、中毒性表皮壊死融解症(TEN)
<学習のポイント>
「症状からみた主な副作用」については、基本的にいきなり過去問を解いて出題傾向をつかむ方法で問題ありません。テキストで勉強してから過去問を解きたい方は、超頻出の4項目から学習を進めてくださいね。
登録販売者試験の第2章 攻略のアドバイス
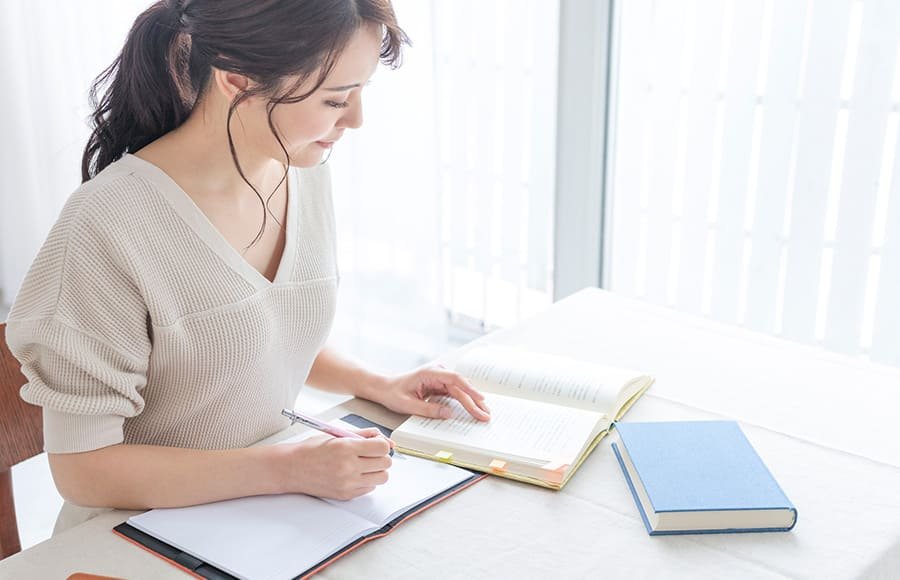
前項では学習のポイントについて詳しく解説しましたが、ここでは第2章全体を通しての攻略のアドバイスをまとめます。
第2章に時間をかけすぎない
登録販売者試験は、医薬品について出題される第3章がもっとも難関といわれます。第3章の出題数(40問)は、第2章(20問)の2倍です。そのため、第2章の学習には時間をかけすぎず、第3章に余力を残すよう、学習計画を立てましょう。
苦手分野は後回しにしよう
第2章では、「消化酵素」や「血液成分」など、細かい暗記が必要な項目もあります。そこに時間をかけすぎてしまうと、簡単に解ける他の分野の学習がおろそかになってしまいます。細かい知識はその分野を大まかに学習した後の方が頭に入りやすいので、後回しにしてとにかく前進しましょう。
テキストでの学習が不要な部分は過去問演習でOK
最初にお伝えした通り、「薬が働く仕組み」と「症状からみた主な副作用」では、一般的な常識の範囲で解ける問題も多く出題されます。そのため、このような分野では、テキストでの学習はおこなわず、初見で過去問を解いていく方法で攻略することも可能です。
ただし、学習方法は個々人の性質に合った方法が一番ですので、テキストでの学習から始めた方が安心という方は、その方法で問題ありません。
まとめ|登録販売者試験の第2章は効率よく学習しよう
登録販売者試験の勉強において、第2章はできるだけ効率的に学習を進め、第3章に時間を割けるようにしたいものですね。そのためには、「頻出項目から先に学習する」、「苦手分野は後回しにする」、「過去問演習を中心におこなう」といった方法がおすすめです。
あなたなら必ずできます。第2章を攻略し、ぜひ合格を勝ち取りましょう。

執筆者:村松 早織(薬剤師・登録販売者講師)
株式会社東京マキア 代表取締役
登録販売者や受験生向けの講義を中心に事業を展開
X(旧:Twitter)、YouTube等のSNSでは、のべ2万人を超えるフォロワー・チャンネル登録者に向けて、OTC(一般用医薬品)についての情報発信をおこなっている。
- ■著書
- ・医薬品暗記帳 医薬品登録販売者試験絶対合格! 「試験問題作成に関する手引き 第3章」徹底攻略(金芳堂)
- ・薬機法暗記帳 医薬品登録販売者試験絶対合格! 「試験問題作成に関する手引き 第4章」(金芳堂)
- ・これで完成! 登録販売者 全国過去問題集 2023年度版(KADOKAWA)
- ・村松早織の登録販売者 合格のオキテ100(KADOKAWA)
- ・やさしくわかる! 登録販売者1年目の教科書(ナツメ社)
【新着】登録販売者のための業界コラム
- 2026年02月04日 【専門家監修】正月太りの原因&最短リセット法|食事・サプリ・漢方で無理なく解消するコツ
- 2026年02月04日 【専門家監修】胃腸炎に効くドラッグストアの市販薬5選!症状や原因別の選び方のポイントもあわせて解説
- 2026年02月03日 登録販売者に年齢制限はあるの?正社員・パートなど働き方別に解説
- 2026年02月02日 登録販売者試験に受かったら。合格後の手続きや流れを分かりやすく解説!
- 2026年01月30日 登録販売者になるために必要な勉強時間は?働きながら合格できるスケジュールと効率化のコツ