2026年ドラッグストア業界の未来図|市場動向・M&A・登録販売者のキャリアと転職のポイント

ドラッグストア業界はここ数年で急速に成長しており、今後10年で「店舗数は約1.6倍」「売上は約1.5倍」とも予測されています。昨今のドラッグストアは、医薬品や化粧品以外にも、生活雑貨やペット用品、生鮮食品や冷凍食品など、幅広いジャンルを取り扱う店舗も少なくありません。
そのため、スーパーやコンビニエンスストアとの競争も激化しており、M&A再編や人手不足問題など大きな課題とともに転換期を迎えています。この記事では、そんなドラッグストアをとりまく業界の課題や、各企業の成長戦略に加え、登録販売者への影響や将来展望について解説します。
これからドラッグストアへの就職・転職を考えている方や、すでに現場で働いていて将来が不安な方は、ぜひこの記事を自身のキャリアアップにお役立てください。
【この記事からわかること】
- 2025年以降のドラッグストア業界の市場規模予測とM&Aによる再編の動き
- ワンストップ化やDX推進、調剤併設が進む中で変わる登録販売者の役割
- 人手不足やコスト増など業界課題への対策と、将来性を見極める転職のポイント
目次
- ・ドラッグストア業界の特徴|登録販売者の働き方にどう影響するか
- ・ドラッグストア業界の今|市場動向と登録販売者を取り巻く環境
- ・登録販売者がドラッグストアを転職先に選ぶときのチェックポイント
- ・ドラッグストア業界の課題と企業の成長戦略|どんな人材が求められているか
- ・ドラッグストア業界の将来展望2025→2026|登録販売者の役割はどう変わる?
- ・登録販売者のキャリア戦略|現場からその先へステップアップする方法
- ・ドラッグストアのM&Aと業界再編|登録販売者の働き方はどう変わる?
- ・まとめ|成長と再編が進むドラッグストア業界で登録販売者がチャンスを掴むには
- ・監修者
ドラッグストア業界の特徴|登録販売者の働き方にどう影響するか

お客さまにとってライフラインとなりつつあるドラッグストアですが、業界をさらに成長させるためには、業界の特徴をつかんでおくことが重要です。今後のキャリアアップや転職活動に活かすためにも、まずはドラッグストアの特徴を把握しておきましょう。
政策の影響を大きく受ける規制産業
医薬品の販売は「薬機法」(正式名称:医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律)による規制を受けるため、政府の取り決めによる影響を受けやすいのが特徴です。薬機法は、国の医療・福祉政策により改正が実施されることがあります。改正内容がドラッグストアの収益に影響をおよぼすことも少なくありません。
立地や商圏の影響を大きく受ける
ドラッグストアの収益は以下の条件によって左右されることが多くあります。
- 商圏の規模
- アクセスのしやすさ
- 競合店舗の有無
また、メインターゲットとなる年代によって売れやすい商品も大きく異なります。そのため、地域の特性やターゲット層の属性をふまえた品揃えやサービス展開が必要です。
市場規模と成長性
ドラッグストア業界の市場規模は、2024年に市場全体で10兆円を突破するなど、ここ十数年で大きく成長しました。コロナ禍のピーク後も、インフルエンザをはじめとするウイルス対策の意識は高まり続けています。そんな現代生活に欠かせない商品の需要もあるため、ドラッグストア業界は安定成長が期待できるといえるでしょう。
参考:激流オンライン「ドラッグストアの売上高が10兆円超え、食品等の構成比が約3割」
ドラッグストア業界の今|市場動向と登録販売者を取り巻く環境

ここからは、ドラッグストア業界の現状を俯瞰しつつ、市場全体の動向について解説していきます。特に、成長著しいECやコンビニとの競争は激化しているため、現場で働く登録販売者の働き方への影響は少なくありません。理想のキャリアやワークライフバランスのためにも、押えておくべき変化をチェックしておきましょう。
ワンストップタイプのドラッグストアの増加
近年は、ワンストップタイプのドラッグストアが増えてきています。これは、医薬品だけではなく、化粧品や日用品、食品などをまとめて1カ所で購入したいというニーズを反映したものです。こうした店舗形態は、買い物の効率アップやお客さまの満足度アップなどに貢献しています。
一方で、登録販売者にとっては対応領域の広がりが課題になっていくでしょう。医薬品の相談に加え、健康食品やサプリメント、日用品との違いや使い分けを聞かれる場面も増えています。また、品出しや売場管理を兼務するケースも多くなっているため、限られた時間の中で専門業務と店舗業務をどう両立するかが重要になるでしょう。
競争の激化
ワンストップタイプのドラッグストアが増加したことで、ECサイトやコンビニエンスストアとの競争が激化しています。
特にコンビニエンスストアに関しては、OTC薬(市販薬)の販売が一部解禁されたことに加え、ECサイトで購入した医薬品の「受け取り窓口」としての機能も強化されつつあります。近隣にドラッグストアがない地域では、24時間営業のコンビニは大きな脅威となる可能性があります。ドラッグストア側は、専門家による相談対応や品揃えの豊富さなど、独自の強みをより明確にする必要があります。
こうした環境の変化は、登録販売者の役割をより明確にするでしょう。価格や利便性ではECやコンビニに劣る場面がある中で、ドラッグストアが選ばれ続けるためには、専門知識を活かした対面での相談対応や、症状に応じた適切な受診勧奨といった付加価値が不可欠です。そのため、登録販売者には、単なる販売員ではなく、「相談できる身近な医薬品の専門家」としての役割が、これまで以上に求められるようになっていくと考えられます。
調剤併設型店舗の増加
大手チェーンではドラッグストア店舗に調剤薬局を併設しています。お客さまは、持ち込んだ処方箋の処理が行われている間に、生活用品や食品の購入ができるというわけです。こうした、ドラッグストア×調剤薬局という一体型の店舗も増えてきており、医療機関隣接の調剤薬局が閉局している曜日・時間帯は、特に利便性が高い店舗となっています。
規模拡大による収益構造の強化
ドラッグストア業界では、店舗数が増えて市場規模が拡大すると、取り扱う金額は大きくなり、仕入れ先への交渉力も向上し、単価や仕入れ量などの融通が利きやすくなります。大規模企業になれば、プライベートブランド(PB)の開発や他社へのPB提供により、さらなる収益向上も可能です。
OMO戦略の推進
競争が激化している中、ドラッグストアは「価格」や「立地」だけでは差別化しにくくなっています。加えて、ECサイトやコンビニエンスストアの利便性向上により、来店前にオンラインで情報収集・比較を行う消費行動が一般化しました。こうした背景から、オンラインとオフラインを分断せずにつなぐOMO戦略の重要性が高まっています。
「OMO戦略」とは「Online Merges with Offline」の略で、オンラインとオフラインを融合させた顧客体験を提供する取り組みです。ドラッグストアのOMOでは、オンラインで情報収集や注文をし、店舗で商品を受け取る仕組みが代表的であり、専用アプリでのオンライン販売や割引クーポンの配布、商品情報の配信、ポイントサービスなどを提供する企業もあります。
今後は、顧客データや購入傾向などを活用し、「なぜこの商品を選んだのか」「次に必要になりそうな商品は何か」を踏まえた提案型の接客が求められています。登録販売者にとっては、OTC薬の知識に加え、デジタルツールを活用してお客さまの行動を理解し、信頼関係を築く力が新たな強みとなっていくでしょう。
企業同士の提携・合併
コンビニエンスストアやECサイトとの競争に打ち勝つために、企業同士の提携や合併も積極的に行われています。激しい競争に勝つための生き残り戦略が顕著に表れつつあるのが現状です。そして、今後も合併をはじめとする企業の再編や立て直しが続いていくと予想されており、業界の内部が大きく変わる可能性があります。以下のコラムでも最新動向を紹介しているため、あわせて参考にしてください。
【登販向けに解説!】ドラッグストア業界の最新動向をご紹介!
人手不足・コスト増の顕在化
ドラッグストア業界でも、物流2024年問題での配送コスト上昇の影響を受け、配送ルートや納品時間の見直しが進んでいます。たとえば、これまで開店前に届いていた商品が日中納品に変更され、品出しのピークがずれるといったケースも増えており、限られた人員の中で売場対応と並行して作業を行わなければならない店舗も少なくありません。
また、業界内における人材不足も課題です。「少ない人数でレジ・売場対応・在庫管理を同時に回さなければならない」「登録販売者が接客と品出しを兼務する時間が増えた」といった現場の声も聞かれます。こうした状況を受け、各社には同業他社に負けない労働条件の提示や、シフト調整・業務分担を工夫した働きやすい環境づくりが求められています。
これらに加えて、業務フローの見直しや社内ルールの明確化、オペレーションのマニュアル化も進めていけば、運営コスト抑制にもつながるでしょう。登録販売者として働く際は、求人を比較し、「人員体制」「残業の実態」「教育・マニュアルの整備状況」といったポイントのチェックをおすすめします。
登録販売者がドラッグストアを転職先に選ぶときのチェックポイント

さまざまな働き方が期待できる登録販売者ですが、ここでは就業先としてドラッグストアを選ぶ際のポイントをお伝えしていきます。
企業規模(大手企業・中小企業)
大手チェーンは、収入やキャリアアップのモデルがある程度確立されており、段階ごとの教育制度も整っています。広域異動が必要な場合もありますが、地域内社員と比較すると基本給も高くなります。また、採用や教育コストの観点から、パートやアルバイトでも、引越し先の近隣店舗への異動が可能な大手チェーンもあります。中小企業の場合は、お客さまとの距離も近く、広範囲の異動を気にせず、やりがいを感じながら働ける場合も多いでしょう。
店舗の特徴
調剤併設型店舗では、医療機関との連携や要指導薬などの展開に伴う高度な知識が求められます。美容や健康特化型店舗では、より精通した知識と専門性が求められ、場合によっては免税対応や語学力が必要となることもあります。郊外型の大手チェーンでは、多数の品目を取り扱っていることが多く、食品や日用品のプライベートブランドも充実しています。
立地
都心にある店舗では客数が多く見込まれるため、立地に由来する多様な客層や需要に対応する順応力が求められます。
郊外型店舗では自家用車で来店するお客さまが多く、購入点数の高さが期待できるため、そこを意識した配慮やサービスが喜ばれるでしょう。
ドラッグストア業界の課題と企業の成長戦略|どんな人材が求められているか
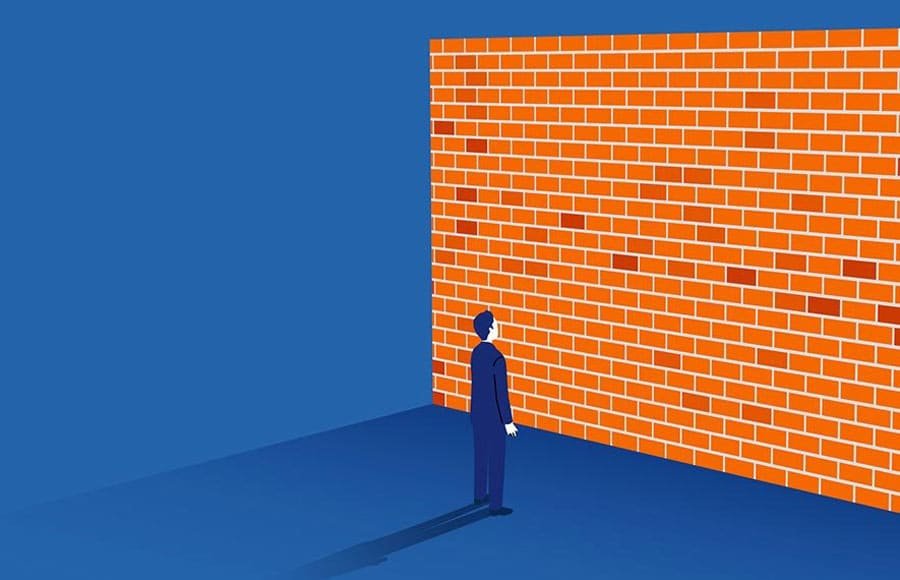
近年ドラッグストア業界は成長を続けていますが、同時にいくつかの課題に直面しています。ここでは、今後の課題とそれに対応する企業の取り組みについて解説します。
需要予測AI・在庫最適化の強化
現在、ドラッグストアは、業務が多いことによる離職者の増加や、店舗数の増加、人件費削減などにより人材不足が顕著です。そのため、在庫管理やお客さまの健康管理を効率化でき、人手不足の解消も期待できるAI技術に注目が集まっています。
たとえば、サイバーエージェントの連結子会社であるMG-DXは、2024年8月から、ドラッグストア・調剤薬局向けに「遠隔接客AIアシスタント」の提供を開始しました。「遠隔接客AIアシスタント」はAI技術を活用した受付業務の自動化と、薬剤師が遠隔地から接客できる仕組みを組み合わせ、店舗での接客をサポートするサービスです。
今後AI技術を導入するドラッグストアが増加すると、AI技術(ハード面)の活用によって向上した生産性を、労働環境の改善(ソフト面)に還元できるため、業界全体の資質向上が見込まれます。
健康サポート機能の向上
ドラッグストアは、地域住民の健康維持や健康増進の役割も担っています。コンビニエンスストアやECサイトとの激しい競争を勝ち抜くためには、専門家が常駐するドラッグストアならではの健康サポート機能のさらなる向上が求められるでしょう。
たとえば、スギ薬局では、健康なときの疾病予防や啓発、さらには介護・終末期の生活支援に至るまで、人の健康をトータルに支える「トータルヘルスケア戦略」を掲げています。目標は、健康状態やライフステージにかかわらず、どんなときでも頼りにしてもらえるドラッグストアです。
施策のひとつとして、管理栄養士常駐店舗で行われる無料の「健康相談会」があります。これは、問診、体重・筋肉量・体脂肪・血圧などを測定し、結果説明を通して、管理栄養士から健康維持のためのアドバイスがもらえるというサービスです。ささいな不調も気軽に相談でき、病院よりもより身近な健康のサポーターとしての役割を果たしています。
高齢化社会への対応
今後は、高齢者や慢性的な疾患を抱える恐れのある方へ長期的なフォローが必要となってくるでしょう。そのため接客の際には、単にお薬の購入相談ではなく生活習慣病などの予防を念頭に置いた丁寧な対応が求められます。
地域密着型サービスの強化
郊外型の店舗では、健康イベントや測定会なども行われています。また、来店頻度も高いことからお互いを認知しているということもあります。そのような店舗では、「前回のお薬服用後の体調」などの話題をきっかけに、以降の来店や指名相談につなげられることもあります。こうした接客も地域密着型サービスのひとつであるといえるでしょう。
登録販売者の専門性強化
近年のドラッグストアの躍進とともに登録販売者についての認知度も高くなっています。OTC薬についての相談を気軽にしていただけるよう、試験に合格したあとも毎年の研修などを通じてスキルアップも継続していく必要があるでしょう。
ドラッグストア業界の将来展望2025→2026|登録販売者の役割はどう変わる?

さまざまな課題を抱えているドラッグストア業界ですが、今後はどのように進展していくのでしょうか。ドラッグストア業界の将来展望について解説します。また、登録販売者としての就職先にドラッグストアを選ぼうか迷っている方は、以下のコラムもご参考ください。
【登販】ドラッグストアはやめたほうがいい?懸念点や対策を解説
業界規模の大幅な拡大
ドラッグストア業界の市場は現在拡大し続けていますが、今後もこの傾向は続くことが予測されています。日本チェーンドラッグストア協会の発表によると、2030年までに全国ドラッグストアの総売上高は13兆円(2022年比152%)、店舗総数は3万5,000店(同161%)となることが予測されています。
参考:ヘルスビジネスオンライン「2030年 売上13兆円産業へ/JACDS」
セルフケアプラットフォームとして進化
ドラッグストア業界の規模が今後も拡大すると予測されている背景には、「セルフメディケーション」の推進があります。WHOの定義によると、セルフメディケーションとは「自分自身の健康に責任をもち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」です。
高齢化が進む日本では、医療費の増加が国の財政を圧迫しています。そのため、「自分の身体は自分で守る」との意識のもと、処方箋を使わずOTC薬を活用しながら不調に対応することが推進されています。一方で、若年層による濫用の恐れのある医薬品の使用状況に鑑み、法制強化が同時に進められていく背景もあることから、これまで以上に販売時の確認や情報提供が欠かせなくなっています。
加えて、セルフメディケーションの推進に伴い、医療用医薬品の中でOTC薬と同等の成分や効能効果をもつ「OTC類似薬」については、保険適用外となるような法整備が進められています。こうした状況もふまえると、今後ますますドラッグストアにおけるOTC薬の売上は増加していくと予測されます。
登録販売者や薬剤師は、お客さまが適切なOTC薬を購入できるように専門的な立場として相談を受け適切なアドバイスをし、必要に応じて受診勧奨を行うことがいっそう求められるようになるでしょう。
OTC薬のオンライン販売率の増加
データからも、OTC薬のオンライン販売率は、今後増加していくとの予測がされています。2023年にオンライン販売されたOTC薬の売上は904億円で、これはOTC薬の売上全体の6.9%です。2029年のオンラインでの売上は2023年比で24.6%増加すると見込まれており、オンライン販売率も1.2倍に増加するとされています。
また、2024年には、現行は対面販売のみであった「要指導医薬品」についても、オンラインでの服薬指導・販売を認める方針が発表されました。このことも、OTC薬のオンライン販売を拡大させるひとつの要因になるでしょう。
参考:Fuji Keizai Group「市販薬EC市場(小売りベース)を調査」
参考:厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会「薬機法等制度改正に関するとりまとめ」
DXの推進
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を業務に取り入れて、さまざまな業務の効率化や自動化を図ることです。DXは多くの業界において推進されていますが、ドラッグストア業界でも今後推進されていくことが予測されます。
たとえばツルハグループは、独自のキャッシュレス決済サービスの導入や、スマホアプリの活用を通したお客さま一人ひとりにあわせた商品の提案など、積極的なDXを推進している企業です。変化する消費者のニーズに応えられるだけでなく、人件費を抑えたり人手不足を解消したりするためにも効果的であるため、今後DXを推進する企業はますます増えることが予測されています。
ドラッグストア業界でのDXが進めば、登録販売者は医薬品相談や健康アドバイスなど、より専門性の高い業務に集中しやすくなるでしょう。加えて、アプリ操作やPOSシステム、デジタルツールへの理解が求められる場面も増えるため、ITリテラシーやデータを活用した接客スキルが、新たな評価ポイントになる可能性もあります。
登録販売者のキャリア戦略|現場からその先へステップアップする方法

DXの進展やM&Aによる再編、人手不足の深刻化といった中、ドラッグストア業界での働き方も大きく変化しつつあります。登録販売者も、どの方向に専門性を伸ばすのか、どのポジションを目指すのかといったキャリア戦略を、早い段階から意識することが重要です。ここからは、登録販売者として医薬品の販売に従事しつつ、キャリアアップのためにしておくべきことなどをお伝えします。
今後求められるスキルセット
セルフメディケーションがこれまで以上に浸透した場合、ドラッグストアでは、以下のようなスキルアップが必要となるでしょう。
- 接客・専門性の向上
- 店舗管理・運営知識の習得
「接客・専門性の向上」の面では、調剤補助への積極的な参加により、OTC薬に含まれる医療用成分の知識を深め、処方薬との違いを理解することで、より的確な服薬指導が可能になるでしょう。また、一人ひとりの生活背景にあわせた一歩踏み込んだカウンセリングも重要です。
「店舗管理・運営知識の習得」に関しては、自店のPOSシステムを理解し、売場や在庫管理、販売価格など商品情報を迅速に確認・管理ができるスキルが必要です。さらに、商品カテゴリや売場の専門用語などを習得し、単なる品出しや接客を超えて、売上や在庫管理、発注計画に貢献できる能力が必要になるでしょう。
未経験からキャリアを積むステップ
試験合格後の業務は、品出しやレジ業務、POP作成といった基本的な店舗オペレーションからスタートします。そうして法定要件をクリアすると、晴れて登録販売者として従事することができます。大手チェーンの多くは試験支援制度がありますので、働きながら合格を目指すこともできます。
一定程度経験を積むと、次の段階を目指すことになるでしょう。店舗責任者の上長はブロック長やエリアマネージャーという役職もあり、その後は本社勤務で店舗運営とは違った業務に携わることも可能です。
キャリアアップの選択肢
キャリアアップの選択肢は、店長やブロック長だけでなく、調剤併設店で医療用医薬品や医療保険制度の知見を深め、専門性を伸ばす働き方も可能です。また、大手チェーンでの教育担当や、本社勤務での商品開発やバイヤーなどで、店舗勤務とは違ったやりがいを見いだすこともできるでしょう。めまぐるしく変化する登録販売者制度やOTC薬をとりまく環境だからこそ、働き方やキャリアの幅も広がっていくことも期待できます。
ドラッグストアのM&Aと業界再編|登録販売者の働き方はどう変わる?

ドラッグストア業界では、市場競争の激化や経済規模を追求する動きが顕著になってきているため、企業の成長戦略のひとつとしてM&A(合併・買収)が進展しています。たとえば、2025年12月1日には業界二大チェーンであるツルハホールディングスとウェルシアホールディングスが経営統合し、その時点での「日本最大ドラッグストアチェーン誕生」などと話題になりました。
M&Aの目的は、競争力強化や地域戦略の強化、経営効率化です。これは、一見すると業界の将来性を示しているように感じますが、中小企業にとっては生き残りをかけた戦略的な判断が求められる危機的状況かもしれません。
M&Aのメリット
売り手側の企業から見れば、後継者がない場合でも廃業することなく事業の継承ができ、その後の企業成長も期待できます。また、安定性を確保できるため従業員の雇用維持にもつながるでしょう。買い手側としても迅速な事業拡大が実現できますし、事業の多角化や競争力向上が期待できます。
M&Aのデメリット
売り手側のデメリットとして経営権を失うことはもちろんですが、買い手が見つからないというリスクや希望条件での売却とならないことも考えられます。買い手側は、多額の買収資金が必要です。自己資金だけで賄えない場合は、借入金の返済負担や金利が発生します。
調剤薬局業界のゆくえ
調剤薬局業界でもM&Aが加速し、個人薬局は厳しい経営状態からの脱却のため、大手チェーン傘下へ入ることを選択するケースが増えています。そんな中、厚生労働省が推進する、かかりつけ薬局制度では、単に処方箋の受付ではなく個別の健康サポートを行い、在宅訪問や24時間対応も可能です。調剤薬局が生き残るためには、こうした制度下で、いかに地域住民の力になれるかがカギになっていくでしょう。
登録販売者の働き方への影響
ドラッグストア業界全体が活性化しているため、登録販売者はさまざまな形態で働くことが可能です。加えて、その後のキャリアパスも多様化しています。一方で、M&Aの渦中にある場合、新たなサービスや決済システムへの対応を求められるなど、業務が煩雑になることがあるかもしれません。積極的に新しいことを学んでいく意欲が、働き方の幅を広げるカギになるでしょう。
ドラッグストア業界に関して登録販売者からよくある質問
- Q. ドラッグストア業界は今後も安定して働けますか?将来性はありますか?
- A. ドラッグストア業界は、少子高齢化やセルフメディケーション推進を背景に、今後も市場拡大が見込まれており、地域の生活インフラとしても、さらに重要になるでしょう。競争や再編も進むため、成長戦略や人材投資の姿勢をチェックすることが、安定したキャリア形成のポイントになります。
- Q. 人手不足が深刻と聞きますが、登録販売者の働き方はきつくなりませんか?
- A. 人手不足は深刻ですが、近年はDXの推進や業務マニュアルの整備、シフトの見直しなどにより、現場負担の軽減に取り組む企業も増えています。転職時に「人員配置」「残業時間」「教育体制」などを確認し、働きやすさを重視し、無理なく働ける環境を選びましょう。
- Q. 登録販売者として、今後どのようなスキルや経験を身につけるべきですか?
- A. OTC薬の知識だけでなく、生活背景を踏まえたカウンセリング力もより重要になっています。また、POSや在庫管理などの店舗運営知識、DXツールへの理解も評価されやすいスキルです。こうした知識や経験を積めば、店長やエリアマネージャー、本部職など、キャリアの選択肢を広げることができるでしょう。
まとめ|成長と再編が進むドラッグストア業界で登録販売者がチャンスを掴むには

ドラッグストア業界は今後も成長が続くと予測されていますが、競争の激化が進んでいるのが現状です。また、お客さまのニーズが多様化する中で業務も膨大になり、人手不足が深刻な課題となっています。こうした背景から、地域への貢献のための事業を推進して信頼を得たり、デジタル技術を取り入れて業務を効率化させたりする企業が増えています。
今後は、単に医薬品を販売するだけでなく、地域の健康活動の拠点となり、住民のライフラインの一翼を担う役割が求められるでしょう。この記事で紹介した業界の課題や各企業の取り組みを、転職先選びや業界研究にぜひお役立てください。
監修者

當房 清香(とうぼう さやか)
登録販売者・薬機法管理者・調理師(ハラール認証)・国際中医薬膳師など
登録販売者として健康や薬に関するWEBライターとして活動。裁判所書記官としての経験や、オーガニックマスターコーディネーター・食品添加物に関する資格などの資格を活かし、「自分や子どもの未来は、現在カラダに取り入れているものでつくられていく」 ことを幅広い視点でお伝えしている。
【新着】登録販売者のための業界コラム
- 2026年01月27日 登録販売者必見!疲労を感じるお客さまへのサプリの接客と受診勧奨
- 2026年01月09日 【現役ドラッグストア店長直伝】登録販売者が「辞めたい」と思わない3つのメンタル維持法(2026年対策付き)
- 2026年01月07日 2026年ドラッグストア業界の未来図|市場動向・M&A・登録販売者のキャリアと転職のポイント
- 2026年01月07日 登録販売者の年収は低い?現場にインタビューしてリアルな声をお届け!平均給料を調査
- 2026年01月07日 ドラッグストア店長の年収はいくら?平均額の内訳と600万円を目指す昇給のコツ



