登録販売者は知っておきたい!EDLP戦略がドラッグストアで導入される背景と登販に求められる役割

こんにちは、登録販売者転職のアポプラス登販ナビライターチームです。
近年、ドラッグストア業界では「エブリデイロープライス(EDLP)」の導入が進んでいます。EDLP戦略は、常に低価格で商品を提供できるため、消費者にとって魅力的な戦略です。一方で、企業側では利益率の低下や競争の激化といった課題も出てきます。本記事では、EDLP戦略の概要や導入背景、登録販売者に求められる役割について解説します。
目次
- ・エブリデイロープライス(EDLP)戦略とは?
- ・EDLP戦略がドラッグストア業界で導入される背景
- ・EDLP戦略を導入しているドラッグストア
- ・EDLP戦略を導入するメリット
- ・EDLP戦略を導入するデメリット
- ・EDLPを導入する店舗で登録販売者に求められること
- ・まとめ|EDLP戦略の企業で働く登録販売者は付加価値の提供を意識しよう
エブリデイロープライス(EDLP)戦略とは?
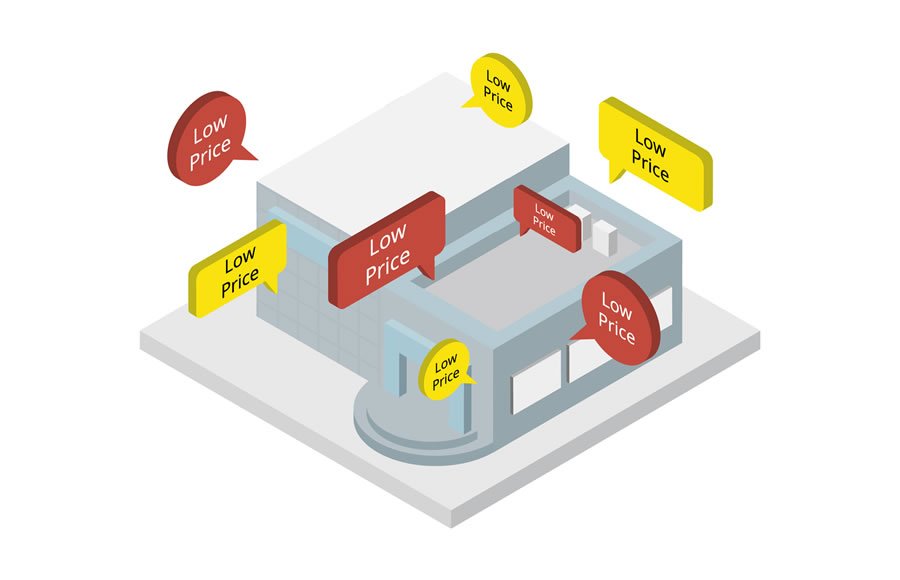
エブリデイロープライス(EDLP)戦略とは、日常的に低価格で商品を提供する販売戦略のことです。従来の方式はハイアンドロー戦略と呼ばれていて、安くなるのは特売やキャンペーン時、大幅な値引きを実施した時のみでした。
その点、EDLP戦略では特売をほとんど実施しない代わりに、通年低価格を維持しています。EDLP戦略は業界にとって、価格の信頼性を向上させる狙いがあります。消費者は常に安定した価格で商品を購入できるため、特売時期に関係なく安心して買い物ができるのです。
EDLP戦略がドラッグストア業界で導入される背景

ではなぜ、EDLP戦略がドラッグストア業界で導入されているのでしょうか。背景は主に以下の4つです。
1つ目は、従来の特売中心の競争から差別化をはかるためです。ドラッグストア業界は従来、特売を中心としたハイアンドロー戦略を採用する企業が多く、競合との差別化が難しい状況が続いていました。そこで登場したのが、EDLP戦略です。EDLP戦略を導入することで、安定した低価格で商品を提供でき、他社との差別化がはかれるようになりました。
2つ目は、コロナ禍による消費者の購買行動の変化です。2020年から始まった新型コロナウイルスの影響により、特売のタイミングを狙って買い物をするのではなく、日常的に安定した価格を求めるようになったのです。これにより、EDLP戦略のニーズが高まりました。
3つ目は、価格変動を嫌う消費者ニーズへの対応です。消費者のなかには、価格が頻繁に変動することを好まない層もいるため、価格の変動が少ないEDLP戦略は、価格変動を好まない消費者にとっては魅力的に映ります。
4つ目は、物流や仕入れコストの最適化です。特売をおこなうと、一時的な大量仕入れや追加の物流コストが発生するケースがあります。EDLP戦略を導入すれば、仕入れや物流のコストを平準化できるため、経営の安定化にもつながるのです。
このような背景があって導入されたEDLP戦略は、ドラッグストア業界に大きな変化をもたらしたといえるでしょう。下記コラムでは、ドラッグストア業界の動向を紹介しているため、あわせて参考にしてください。
EDLP戦略を導入しているドラッグストア

多くのドラッグストアがEDLP戦略を導入していますが、とくにEDLP戦略を推進して企業成長をしている企業を3つ紹介します。転職を検討している登録販売者の方は、ぜひご参考にしてください。
クリエイトエス・ディー
クリエイトエス・ディーはEDLP戦略を推進した結果、2023年5月期決算において、売上高が3,809億6,300万円と、前年と比べると8.6%も増加しています。
営業利益で見ると、189億1,200万円(4.1%増)の他、経常利益は194億2,800万円(4.1%増)、親会社に帰属する当期利益は129億2,500万円(2.6%増)と、EDLP戦略がきちんと結果に出ているのがわかります。低価格を維持した結果、消費者の購買意欲が高まったため、売上が増加したといえるでしょう。
参考:株式会社クリエイトSDホールディングス「2023年5月期 決算説明資料」
クスリのアオキ
クスリのアオキグループは、EDLP戦略を推進し、消費者にとって買い物がしやすい店舗づくりを目指しています。なかでも特徴的なのは、タイムパフォーマンスを重視している点です。OTC(一般用医薬品)の販売だけではなく、食品や日用品、生活雑貨などの取り扱いを増やし、2026年5月期に「売上高5,000億円」という財務目標を設定しています。
参考:株式会社クスリのアオキホールディングス「中期経営計画」
コスモス薬品
33期連続増収企業であるコスモス薬品は、数ある小売企業のなかでもとくにEDLP戦略を推進しています。コスモス薬品は、上場小売業のなかでも販売管理費比率16%と、もっとも効率のよい経営を実現しているため、毎日特売価格を実現しているのです。
販売管理費比率を抑えられる理由は、ハイテクとアナログの両方を駆使した店舗オペレーションをしているからです。コスモス薬品は小売企業でありながらドラッグストアのビジネスモデルとして注目されています。
EDLP戦略を導入するメリット

多くの企業がEDLP戦略を導入していますが、一体どのようなメリットがあるのでしょうか。EDLP戦略は消費者にとってだけではなく、企業側にも多くのメリットがあります。なかでも代表的なメリットを3つ解説します。
固定客を獲得しやすい
EDLP戦略は、安定した価格を提供できるため、固定客を獲得しやすいのがメリットです。消費者は特売のタイミングを気にすることなく、1年中いつでもお得に購入できるため、リピーターが増加します。登録販売者としては、リピーターのお客さまとの間に信頼関係を築きやすく、顧客満足度を高めるのに貢献できるでしょう。
適正在庫を実現しやすい
適正在庫を実現しやすいのもEDLP戦略の大きなメリットといえます。価格を一定に保つことで、需要の予測が比較的容易になるため、必要以上の在庫を抱えることなく、適正な在庫量を保てるのです。発注作業も担当している登録販売者の方は、欠品や過剰発注などのミスを減らせるでしょう。
さらに、たくさんの量を一括で仕入れることで、仕入れのコストを低減できるという点で利益向上に貢献します。
広告やオペレーションコストを削減できる
EDLP戦略では、商品価格を一定にするため、広告やオペレーションコストを削減できるのもメリットです。従来のハイアンドロー戦略では、特売広告を作成したり、価格タグを変更したりしなければならないなど、手間とコストがかかっていました。
EDLP戦略を取り入れることで、これらの業務が不要になるため、登録販売者や薬剤師などを含む店舗スタッフの負担軽減にもつながります。
EDLP戦略を導入するデメリット

EDLP戦略の導入には、メリットだけではなくデメリットもあることを理解しておくことで、万が一のリスクにも柔軟に対応できるはずです。ここでは、代表的なデメリットを3つ解説します。
利益率が低下する
低価格で商品を売る戦略であるため、ある程度の集客が見込めないと、利益率の低下につながってしまうのがデメリットです。たしかに消費者にとっては買いやすくなりますが、多く買ってもらわないと、店舗の利益はどんどん下がってしまいます。
また、価格を下げればよいというものでもありません。なぜなら、わざわざ買ってもらえても、品質が悪かったらリピートにつながらないからです。こうしたデメリットを回避するためには、適正な価格や品質を維持することが求められます。
特売と比べて爆発的な売上増や集客が難しい
EDLP戦略を導入した店舗では、常に低価格で商品を購入できるため、爆発的な売上の増加や、集客が難しいのもデメリットです。従来の戦略であるハイアンドロー戦略では、特売のチラシやクーポンを配布することで、その日の売上の爆発的な増加や集客が狙えました。
一方、EDLP戦略は一定の価格であるがゆえに起爆剤となる要素に欠けるのです。EDLP戦略に特売をプラスしてしまうと、さらなる利益低下につながるため、他の要素で集客や利益増加を狙っていく必要があります。
価格競争が激化する
EDLP戦略は大手企業だからこそできる戦略であるため、競争に打ち勝とうとして、価格競争が激化する可能性があるのもデメリットです。他社に打ち勝とうと価格をどんどん下げてしまっては利益につながりません。
そのため、親身な接客や購買につながりやすい売り場づくりを通して、価格以外のところで他の企業と差別化をはかることが、競争に勝つことにつながります。
EDLPを導入する店舗で登録販売者に求められること

EDLP戦略を導入して、競合他社との価格競争が激化していくなかで、登録販売者には一体何が求められるのでしょうか。
EDLP戦略を導入すると、どうしても「低価格=低品質」というイメージが付いてしまうものです。また、特売による集客もできなくなってしまいます。そのため、価格以外の付加価値を生み出していかなくてはなりません。最後に、登録販売者ができる付加価値につながるサービスを解説します。
専門知識を活かした接客
登録販売者ならではの専門知識を活かした接客を通して、価格以外の付加価値を高められます。消費者が付加価値を感じられるように、商品選びのサポートや適切なアドバイスをすることが重要です。
たとえば、症状に合ったOTC(一般用医薬品)の提案や、健康維持に役立つ商品を紹介することで、顧客満足度を向上させられます。
また、商品単価が低いなかで、お客さまひとりあたりの売上を増やす「アップセル」のための戦略も重要です。登録販売者が専門的な知識を活用して商品を提案すると、比較的高価な商品でも買ってもらえる可能性が高まります。価格の適正度合いや商品のもつ特徴、メリットをしっかり説明し、消費者に安心感を与えましょう。
登録販売者は、いわばOTC(一般用医薬品)のスペシャリストです。専門知識を活かしてリピートの獲得につなげてください。
EDLPに適した売り場づくり
EDLP戦略では特売の告知ができないため、売り場づくりが購買意欲を左右するといっても過言ではありません。とくに、商品がもつ価値を視覚的に伝え、消費者の購買意欲を掻き立てる効果的な陳列やPOP(販促用ポスター)を活用することが重要です。
また、EDLP戦略を導入している店舗では商品の単価が低いため、お客さまひとりあたりの買い上げ点数を増やす「クロスセル」が欠かせません。関連商品を近くに陳列するなど、まとめ買いを促す工夫が効果的です。
さらに、特売がない分、季節ごとの需要を意識したディスプレイ変更も大切です。たとえば、冬場は風邪薬や保湿用品を前面に配置し、春先には花粉症対策商品を目立たせるといった工夫が効果的といえます。
一方、整腸剤や解熱鎮痛剤など、年間を通してリピート率の高い商品を把握し、それらに特化した売り場づくりでリピーターを獲得することも、売上を安定させるのに寄与します。
まとめ|EDLP戦略の企業で働く登録販売者は付加価値の提供を意識しよう
EDLP戦略は常に低価格で商品を提供することを掲げ、多くのドラッグストアが導入している戦略です。EDLP戦略を導入する企業は固定客を獲得しやすく、広告やオペレーションコストを削減できる一方で、利益率の低下や、特売と比べて爆発的な売上増が見込みにくいといったデメリットもあります。
EDLP戦略を導入する店舗で働く登録販売者には、専門知識を活かした接客やお客さまの購買意欲を高めるための売り場づくりが求められます。EDLP戦略のデメリットを補う役割を果たせるよう、ただOTC(一般用医薬品)を販売するのにとどまらず、積極的に付加価値を提供することを意識しましょう。
【新着】登録販売者のための業界コラム
- 2026年01月27日 登録販売者必見!疲労を感じるお客さまへのサプリの接客と受診勧奨
- 2026年01月09日 【現役ドラッグストア店長直伝】登録販売者が「辞めたい」と思わない3つのメンタル維持法(2026年対策付き)
- 2026年01月07日 2026年ドラッグストア業界の未来図|市場動向・M&A・登録販売者のキャリアと転職のポイント
- 2026年01月07日 登録販売者の年収は低い?現場にインタビューしてリアルな声をお届け!平均給料を調査
- 2026年01月07日 ドラッグストア店長の年収はいくら?平均額の内訳と600万円を目指す昇給のコツ







