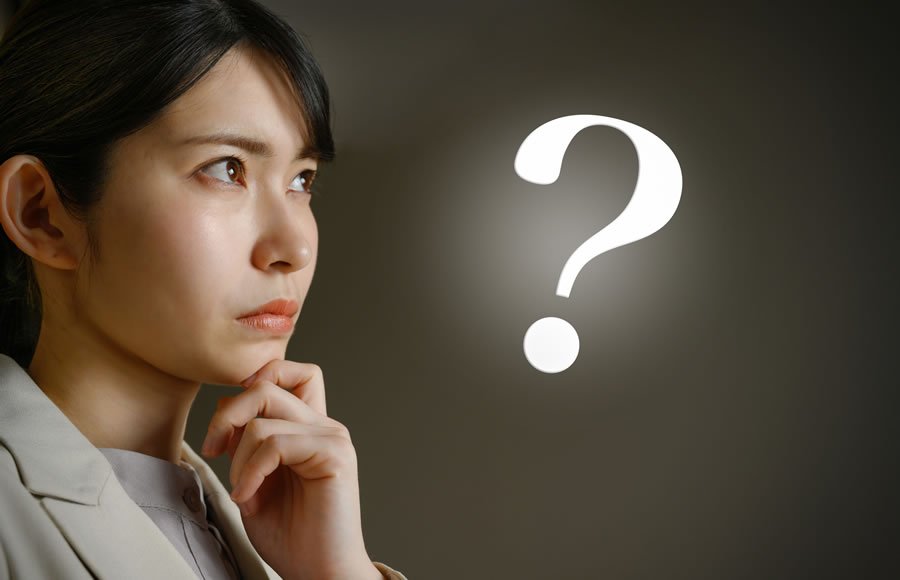登録販売者がネット販売で注意すべき点?特定販売についてわかりやすく紹介

こんにちは、登録販売者転職のアポプラス登販ナビライターチームです。
医薬品のネット販売(特定販売)は、ドラッグストアや薬局での業務と異なり、お客さまと直接対面せずにおこなうため、特有の知識やスキルが求められる分野です。ネット販売の導入により、オンラインで幅広いお客さまに医薬品を提供できるようになった一方、販売時に注意すべきポイントが増え、医薬品の種類や法令遵守に対する深い理解が欠かせません。
本記事では、ネット販売(特定販売)の基本的な概要とともに、登録販売者としてネット販売をおこなう際に必要なスキルや知識について解説します。
目次
- ・登録販売者が知っておきたいネット販売(特定販売)とは?
- ・ネット販売(特定販売)で登録販売者が注意しておきたいこと
- ・特定販売での禁止事項
- ・特定販売をおこなうにあたって登録販売者が身につけておきたいスキル
- ・まとめ|登録販売者が特定販売をするならルールの理解が大切
登録販売者が知っておきたいネット販売(特定販売)とは?

特定販売は、店舗販売業や配置販売業、卸売販売業といった従来の販売形態に該当しない新しい販売方法として定義されており、店舗でOTC(一般用医薬品)を扱う登録販売者が知っておくべき分野です。具体的には、店舗を持つ薬局やドラッグストアが、ネットやカタログ、電話を通じて医薬品を郵送で販売する形態を指します。
特定販売の導入により、より多くのお客さまに医薬品を届けられるようになった一方で、医薬品の種類や販売に関する規制、取り扱い方法について正確な知識が必要です。ここでは、特定販売に関する基本的な情報や、登録販売者が注意すべきポイントを解説します。
また、登録販売者がおこなう特定販売の仕事内容や給与などについて知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
登録販売者のネット販売、通信販売の求人とは?仕事内容や給与などを解説
医薬品販売の特定販売では店舗が必要
医薬品の特定販売をおこなうには、必ず許可を受けた店舗を設置する必要があります。すでに取得している「薬局開設許可」や「店舗販売業許可」の対象店舗があれば、新たに場所を確保する必要はありません。
許可に関する書類も既存のものを流用できる場合が多いですが、特定販売をおこなうために追加で申請が必要な場合もあります。なお、特定販売届出書には店舗の平面図(店舗の配置を示した図)を添付し、販売の基盤となる設備や陳列スペースを明確に記載する必要があります。一般的な通信販売のように自宅を保管場所とする営業形態とは異なり、医薬品販売では必ず専用の店舗が必要となる点に留意しましょう。
特定販売の申請に必要な書類
特定販売をおこなうにあたって、いくつかの書類を所轄保健所に提出する必要があります。申請時には、特定販売届出書の提出が必要で、広告手段や配送方法、ネットを使用する場合のホームページアドレスなどの記載が求められます。
また、薬局や販売店の平面図を添付し、第一類医薬品や指定第二類医薬品の配置場所、情報提供設備などの詳細を示さなければなりません。所轄保健所ごとに必要書類が異なる場合もあるため、最寄りの保健所に確認するなど地域の規定にしたがって準備をしましょう。
インターネット販売ができるOTC(一般用医薬品)
インターネットで販売可能なOTC(一般用医薬品)には、リスク区分が設けられています。要指導医薬品(ダイレクトOTCやスイッチ直後の品目)や医療用医薬品はネット販売が禁止されていますが、以下のOTC(一般用医薬品)であれば取り扱いが可能です。
- 第1類医薬品:リスクが高いため、薬剤師が対応し、販売時には情報提供が義務付けられます。
- 指定第2類医薬品:比較的リスクが高く、薬剤師または登録販売者が対応し、販売時の情報提供は努力義務です。
- 第2類医薬品:比較的リスクが高く、薬剤師または登録販売者が対応し、販売時の情報提供は努力義務です。
- 第3類医薬品:リスクが低く、薬剤師または登録販売者が対応し、販売時の情報提供は努力義務です。
ホームページへ必要事項の記載が必要
特定販売をおこなう際、ネットで広告をする場合には、販売用ホームページに記載しなければいけない項目がいくつかあります。具体的には、薬局や店舗の管理および運営に関する情報、要指導医薬品やOTC(一般用医薬品)の販売制度に関する情報、特定販売に関する内容などです。
また、医薬品に関するレビューや口コミ、レコメンドの掲載は禁止されています。指定されたルールを守り、お客さまが安心して医薬品を購入できるような環境を整えることが大切です。
ネット販売(特定販売)で登録販売者が注意しておきたいこと

ネット販売において、登録販売者が適切に医薬品を販売するためには、対面販売と異なる注意点を把握しておく必要があります。購入者が安全かつ効果的に医薬品を使用できるように、使用者の状況確認や情報提供の方法、販売後のフォローアップなどを理解し、適切な対応を心がけることが求められます。
販売前に使用者の状況を確認する
医薬品を販売する前に、使用者の基本情報を確認することが大切です。とくに副作用歴や健康状態は必ず把握しなければなりません。
登録販売者は、メールなどを通じて性別や年齢、症状、既往歴や副作用歴、現在の健康状態、妊娠中・授乳中かどうかなどを事前に確認します。事前確認によって購入者にとって適切な医薬品かどうかを判断し、必要に応じたアドバイスができるようになります。
なお、第2類医薬品に関しては、使用者の状況確認は努力義務となっており、第3類医薬品は必須ではありません。ただし、濫用のおそれがある医薬品や指定された第2類医薬品については、購入者の服用歴や健康状態を慎重に確認し、適正な使用を促すことが求められます。
医薬品に関する情報提供を個別におこなう
第1類医薬品を販売する際には、用法・用量や使用上の注意点など、必要な情報を購入者へ個別に提供する必要があります。また、適切な服用方法を理解してもらい、万が一の副作用に対する対処法を共有します。症状が改善しない場合には、医療機関を受診するよう促すことも大切です。
第2類および第3類医薬品については、個別の情報提供義務はありませんが、購入者が必要な場合には適切な情報を提供し、購入者の不安を解消するよう努めましょう。
使用者が医薬品に関する情報を理解したかチェックする
第1類医薬品の販売では、使用者が提供された情報を正しく理解したかを確認する必要があります。用法や注意点についての理解度を確認することで、安全に使用できる状態であるかを判断します。
再質問や追加の相談があった場合には、薬剤師または登録販売者が丁寧に回答し、購入者が理解しているかどうかを確認したうえで販売をおこなうようにしましょう。
濫用のおそれがある医薬品は購入状況を確認する
濫用の可能性がある医薬品の販売には、購入者が適正に使用することを確認するためのステップが必要です。たとえば、若年層に対しては、氏名や年齢を確認し、他店舗での購入歴もチェックすることで、過剰摂取や不適切な利用のリスクを軽減します。
また、大量購入を希望する場合には、その理由を確認し、適正使用が前提であることを明確にします。対象医薬品については、厚生労働省の最新情報を確認しておくとよいでしょう。
販売記録を作成して保管する
第1類医薬品を販売する際には、販売記録の作成と保管が義務付けられています。医薬品の名称、販売数量、販売日時、担当者の氏名、購入者が情報提供を理解したかの確認など、詳細な情報を記録し、2年間の保管が必要です。
第2類および第3類医薬品では努力義務とされていますが、安全性を考慮し、記録を適切に管理しておくとよいでしょう。また、購入者の連絡先も記録しておくと、回収が必要になった際の迅速な対応が可能です。
特定販売での禁止事項

医薬品の特定販売をおこなう際、通常の対面販売とは異なる規制やルールが存在します。ここでは、特定販売での禁止事項を紹介します。登録販売者として正確に理解し、実施することが大切です。
オークション形式の販売は禁止されている
医薬品の特定販売において、オークション形式での販売は厳しく禁止されています。ネットオークションに医薬品を出品することは法律で禁止されており、購入者がさらに転売目的でオークションを利用するのも違法です。大量購入を希望するお客さまに対しては、オークションでの転売が禁じられている旨をしっかりと周知し、適切に管理する必要があります。
購入者の効能・効果に関するレビューは禁止されている
医薬品の効果や効能について、購入者のレビューや口コミへの記載も誤解を招かないために禁止されています。薬機法に基づき、医薬品の広告・宣伝には厳しい制約があるため、医薬品使用後の評価を含む内容の記載は認められていません。
また、ネット上での広告や販売促進においても、履歴に基づいて特定の医薬品の購入を促すようなレコメンド機能は使用できないため、注意が必要です。
一方で、販売店舗の対応やサービスに関する評価など、効能・効果に直接かかわらない内容についてはレビューが許可されています。
問い合わせに対する自動返信は禁止されている
特定販売においては、問い合わせに対する回答は個別対応が求められており、自動返信や一斉送信による対応は認められていません。一人ひとりの質問内容にあわせて適切な情報を提供する必要があります。
特定販売をおこなうにあたって登録販売者が身につけておきたいスキル

特定販売をおこなうには、店舗業務とは異なる登録販売者としてのスキルが求められるシーンもあります。医薬品の適切な取り扱いと安全な提供を実現するために、業務の効率化と法令順守を支える知識を身につけることが大切です。ここでは、特定販売において登録販売者が身につけておきたい知識やスキルを紹介します。
医薬品をわかりやすい文章で説明するスキル
特定販売においても、対面での販売と同様に医薬品に関する知識が欠かせません。さらに、ネット上での問い合わせ対応には文章での説明が必要になります。そのため、医薬品の効能や使用方法をわかりやすく言葉にする能力も求められます。
医薬品の品質を保ちながら在庫管理・発送するスキル
特定販売においても、店舗での場合と同様に医薬品の消費期限管理を徹底し、お客さまに安全な商品を提供する必要があります。
さらに、特定販売ではお客さまにその場で直接商品を渡せるわけではないため、配送の過程を経ても医薬品の品質が維持されるための工夫が必要です。たとえば、医薬品の特性をふまえたうえで必要に応じて伝票に「直射日光を避ける」「冷所保存」などの注意書きをしたり、緩衝材や保冷剤などを利用したりすることがあげられます。
法令の理解と遵守の意識
特定販売では、法令順守の意識が必要です。医薬品の販売には薬機法をはじめとする多くの法令が適用されているため、ルールを正しく理解して適切に対応するスキルが求められます。
とくに、実際の店舗で取り扱っていない商品の販売や、問い合わせに対する一斉送信が禁止されているなど、特定販売ならではのルールもあります。そのため、店舗での販売に関する法令に加え、特定販売に関する法令の最新情報を常に確認し、販売している医薬品や販売方法が法令違反になっていないか定期的に確かめることが大切です。
まとめ|登録販売者が特定販売をするならルールの理解が大切
特定販売における登録販売者の役割は、ただ商品を提供するだけでなく、お客さまが医薬品を適切に使用できるよう、細やかな情報提供とサポートをおこなうことにあります。特定販売では、法令を遵守するとともに、在庫管理や発送の各段階で医薬品の品質を維持する工夫が求められます。
特定販売の場合、お客さまに医薬品が届くまでの過程は、店舗での販売に比べ長く複雑です。その分、品質管理と安全性の確保を徹底し、お客さまが安心してスムーズに購入できる環境を整えていきましょう。
【新着】登録販売者のための業界コラム
- 2025年10月15日 【登販向け】秋冬に注意!花粉症・寒暖差アレルギー・風邪の違いと接客ポイント
- 2025年10月15日 登販必読!抗ヒスタミンの市販薬の選び方|眠気・副作用・使い分けを徹底解説
- 2025年10月02日 【2025年薬機法改正】ドラッグストアショーで見えた改正のポイントと登録販売者の未来
- 2025年10月02日 【2026年制度変更に備える】OTC類似薬とは?登録販売者が押さえるべき接客・対応ポイント
- 2025年10月02日 【2025年最新版】登録販売者が押さえるべきセルフメディケーション対象商品一覧と対応ポイント