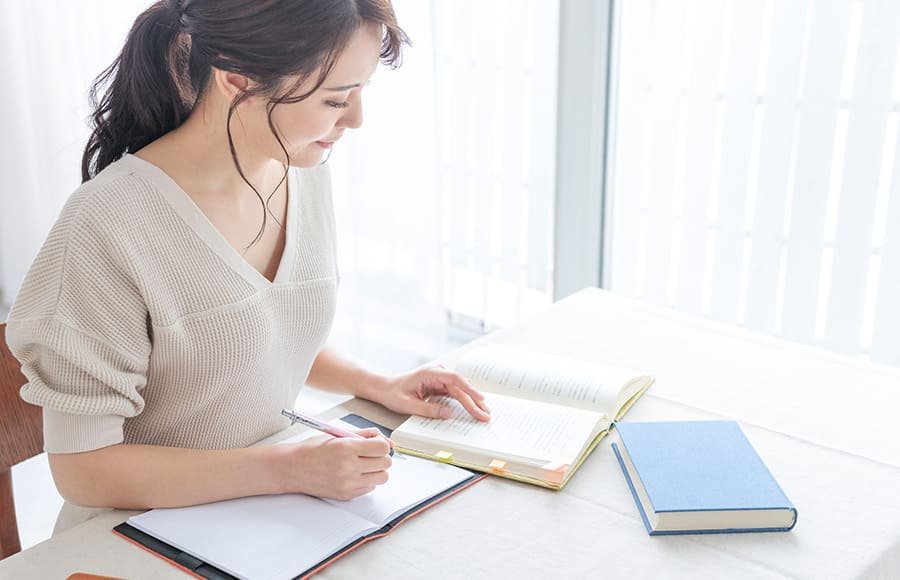【2025年最新版】登録販売者試験の合格点・合格ラインについて解説

こんにちは、登録販売者転職のアポプラス登販ナビライターチームです。
登録販売者試験は、OTC(一般用医薬品)を扱う多くの現場で必要とされる国家資格です。その合格基準や合格ラインは都道府県によって異なっており、受験する地域によっては難易度に差が出ることもあります。
本記事では、試験の概要から合格ライン、そして合格が難しいとされる都道府県まで詳しく解説します。登録販売者試験の受験を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
目次
- ・登録販売者試験の概要
- ・登販試験の合格基準は都道府県ごとに異なる
- ・登録販売者試験の都道府県別合格ライン
- ・登録販売者の合格点・合格ラインに関するよくある質問
- ・まとめ|登録販売者試験の合格ラインを理解し、確実な合格を目指そう
登録販売者試験の概要

登録販売者試験とは、OTC(一般用医薬品)の販売に従事するために必要な公的資格です。OTC(一般用医薬品)のなかでも、第2類および第3類に分類される医薬品の販売が主な対象に該当します。薬剤師でなくても取得できるため、比較的身近な資格として注目されています。
登録販売者資格の大きな特徴は、学歴や年齢に制限がないことです。独学での合格も目指せるため、働きながら挑戦する方も多いです。合格後はドラッグストアや薬局、スーパーなどの医薬品販売部門での勤務が可能となるため、求人の幅が広がるメリットがあります。
また、医薬品の知識を有する人材として職場での信頼や評価が高まるため、将来のキャリアアップも見込めるでしょう。そのため、登録販売者の資格を取得することで、将来的には独立開業の道も見えてきます。自らのキャリアをより柔軟に構築したいと考える方には、有用な資格のひとつといえるでしょう。
登販試験の合格基準は都道府県ごとに異なる

登録販売者試験における合格点は、全都道府県で共通のルールに基づいて設定されています。試験は下記5つの分野にわかれています。
- (1)医薬品に共通する特性と基本的な知識
- (2)人体の働きと医薬品
- (3)主な医薬品とその作用
- (4)薬事関連法規・制度
- (5)医薬品の適正使用・安全対策
全体の正答率が70%以上であることが基本とされていますが、試験に合格するには分野ごとに一定の得点率を満たさなくてはなりません。つまり、正答率が70%であっても分野に偏りがあると合格できるとは限らないのです。
各試験項目の正答率が「3割5分以上」もしくは「4割以上」と公表している都道府県が多いといわれています。そこで正答率が「3割5分」と「4割」だった場合の正答数を表にまとめました。
| 問題数 | 正答率が3割5分の 場合の正解数 |
正答率が4割の 場合の正解数 |
|
| 第1章 | 20 | 7 | 8 |
| 第2章 | 20 | 7 | 8 |
| 第3章 | 40 | 14 | 16 |
| 第4章 | 20 | 7 | 8 |
| 第5章 | 20 | 7 | 8 |
試験の合格基準が3割5分なのか4割なのかは都道府県によって異なります。すなわち、合格点が全国共通であっても、最終的な合格者の人数や合格率は地域によってばらつきがあるのです。
例えば、応募者数が多く競争率の高い都道府県では、同じ点数を取っても不合格になる可能性があります。これは、登録販売者の需要や人口比など、地域ごとの事情を反映して運用されているためです。
そのため、受験者は単に合格点を目指すだけでなく、受験地の傾向や過去の合格率なども確認しておきましょう。
登録販売者試験の都道府県別合格ライン

登録販売者試験に合格するには、全体の正答率が7割以上で、かつ各項目で一定の得点率を満たす必要があり、各項目の合格ラインは都道府県ごとに異なります。
合格ラインは「試験実施後に公表すること」となっているため、今年度試験については公表されていません。2024年の合格基準に関しては以下の表を参照してください。
※この一覧表を作成した2025年6月9日時点では情報公開されていない都道府県がありましたので、空欄の都道府県につきましては、各都道府県のホームページをご確認ください。
| 都道府県 | 合格基準 |
|---|---|
| 北海道 | 4割 |
| 青森県 | 4割 |
| 岩手県 | 4割 |
| 宮城県 | 4割 |
| 秋田県 | 4割 |
| 山形県 | 4割 |
| 福島県 | 4割 |
| 茨城県 | - |
| 栃木県 | 3割5分 |
| 群馬県 | - |
| 新潟県 | 3割5分 |
| 山梨県 | - |
| 長野県 | 3割5分 |
| 神奈川県 | - |
| 千葉県 | 3割5分 |
| 埼玉県 | - |
| 東京都 | 3割5分 |
| 都道府県 | 合格基準 |
| 富山県 | - |
| 石川県 | - |
| 岐阜県 | 3割5分 |
| 静岡県 | 3割5分 |
| 愛知県 | - |
| 三重県 | 3割5分 |
| 福井県 | - |
| 滋賀県 | 3割5分 |
| 京都府 | 3割5分 |
| 兵庫県 | 3割5分 |
| 和歌山県 | 3割5分 |
| 奈良県 | 3割5分 |
| 大阪府 | 3割5分 |
| 鳥取県 | 4割 |
| 島根県 | - |
| 岡山県 | 4割 |
| 広島県 | - |
| 都道府県 | 合格基準 |
| 徳島県 | 3割5分 |
| 香川県 | 4割 |
| 愛媛県 | 4割 |
| 高知県 | 4割 |
| 佐賀県 | 3割5分 |
| 長崎県 | 3割5分 |
| 熊本県 | - |
| 大分府 | 3割5分 |
| 宮崎県 | 3割5分 |
| 鹿児島県 | 3割5分 |
| 沖縄県 | 3割5分 |
(参照:各都道府県のホームページ)
詳しくは各都道府県のHPを参照してください。
登録販売者試験の合格が難しい県は?
各都道府県によって試験項目ごとの合格基準が異なるため「合格が難しい県はどうしたらいいのだろうか」と不安に感じる人も多いのではないでしょうか。
下記の表を見てわかるように、合格率が著しく低い県はありません。合格を目指すには、過去問3年分を解くだけではなく、受験地域外の問題も過去1年分やっておくと有効です。
| 都道府県 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,553人 | 967人 | 62.3% |
| 青森県 | 572人 | 314人 | 54.9% |
| 岩手県 | 501人 | 258人 | 51.5% |
| 宮城県 | 1,193人 | 656人 | 55.0% |
| 秋田県 | 364人 | 182人 | 50.0% |
| 山形県 | 451人 | 237人 | 52.5% |
| 福島県 | 963人 | 457人 | 47.5% |
| 茨城県 | 1,881人 | 875人 | 46.5% |
| 栃木県 | 1,019人 | 436人 | 42.8% |
| 群馬県 | 1,785人 | 914人 | 51.2% |
| 埼玉県 | 2,305人 | 1,077人 | 46.7% |
| 千葉県 | 2,579人 | 1,185人 | 45.9% |
| 東京都 | 4,257人 | 1,948人 | 45.8% |
| 神奈川県 | 2,997人 | 1,432人 | 47.8% |
| 新潟県 | 867人 | 377人 | 43.5% |
| 山梨県 | 352人 | 141人 | 40.1% |
| 長野県 | 859人 | 361人 | 42.0% |
| 富山県 | 577人 | 301人 | 52.2% |
| 石川県 | 782人 | 408人 | 52.2% |
| 福井県 | 197人 | 79人 | 40.1% |
| 岐阜県 | 917人 | 505人 | 55.1% |
| 静岡県 | 1,933人 | 1,095人 | 56.6% |
| 愛知県 | 3,267人 | 1,853人 | 56.7% |
| 三重県 | 969人 | 554人 | 57.2% |
| 関西広域連合(※) | 6,400人 | 2,987人 | 46.7% |
| 奈良県 | 842人 | 352人 | 41.8% |
| 鳥取県 | 258人 | 137人 | 53.1% |
| 島根県 | 271人 | 136人 | 50.2% |
| 岡山県 | 1,478人 | 765人 | 51.8% |
| 広島県 | 1,042人 | 582人 | 55.9% |
| 山口県 | 858人 | 466人 | 54.3% |
| 香川県 | 528人 | 279人 | 52.8% |
| 愛媛県 | 647人 | 335人 | 51.8% |
| 高知県 | 395人 | 184人 | 46.6% |
| 福岡県 | 4,019人 | 1,242人 | 30.9% |
| 佐賀県 | 623人 | 179人 | 28.7% |
| 長崎県 | 538人 | 163人 | 30.3% |
| 熊本県 | 789人 | 247人 | 31.3% |
| 大分県 | 633人 | 226人 | 35.7% |
| 宮崎県 | 504人 | 148人 | 29.4% |
| 鹿児島県 | 859人 | 247人 | 28.8% |
| 沖縄県 | 702人 | 172人 | 24.5% |
※関西広域連合:滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、徳島県
参考:厚生労働省医薬局「令和6年度登録販売者試験実施状況」
| 登販ナビ 注目の人気急上昇ランキング |
|---|
| 【2025年発表】登録販売者必見!ドラッグストアホワイト企業ランキング |
| 登録販売者の転職はエージェントにお任せ!おすすめ転職サイトをご紹介 |
| 【大手5社比較】女性登録販売者が働きやすいドラッグストアはどこ?各社の制度や実績を徹底比較! |
| 登録販売者の転職は40代でも可能!採用される人の特徴とは |
| 登録販売者の管理者要件が実務経験1年以上に!追加研修が必要? |
登録販売者の合格点・合格ラインに関するよくある質問
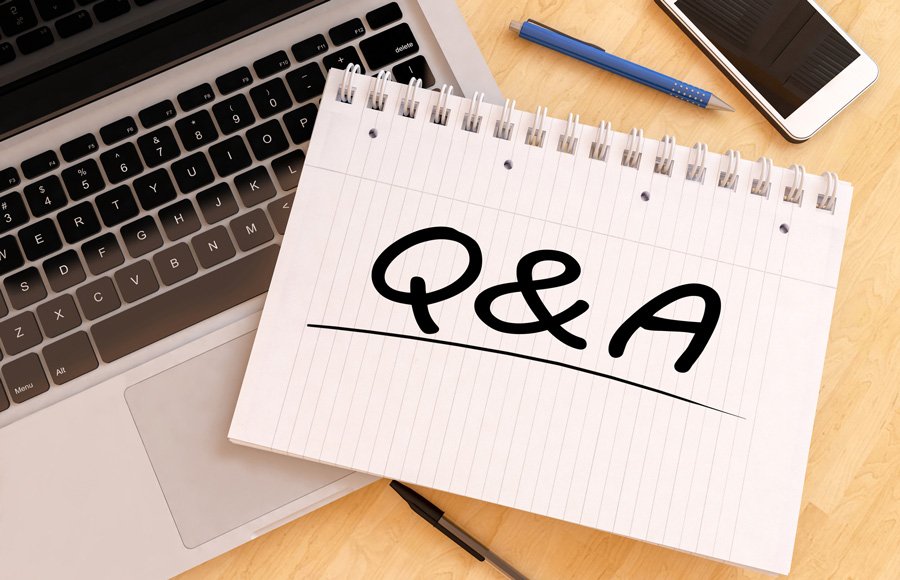
登録販売者試験に関する情報は多岐にわたりますが、なかでも合格点や合格ラインについては疑問を持つ方が多いのではないでしょうか。ここでは、よくある質問に対する回答をまとめて紹介します。
登録販売者の合格率が低い理由は?
登録販売者試験の合格率が低い要因は、受験資格の幅広さと対策不足だといわれています。特別な条件は不要で誰でも受験できるため、事前準備が不十分なまま挑戦する人も多いのが現状です。
とくに独学での勉強は出題傾向を把握しづらく、重要な分野が曖昧なまま試験に臨むケースも多く見受けられます。さらに、問題数が多く選択肢も紛らわしい内容があるため、一定以上の理解力と暗記力が必要です。
登録販売者試験の難易度を他の資格と比べると?
登録販売者試験の難易度は、医療系の資格のなかでは比較的低いとされますが、油断は禁物です。なぜなら、試験範囲が広いうえ、医薬品の種類や作用機序など専門性の高い内容が含まれるためです。
また、宅建や行政書士といった文系資格より暗記量が多く、負担となってしまいます。その一方で、看護師や薬剤師といった医療職の国家試験と比べると、合格に必要な知識量や実務経験のハードルは低めに設定されている傾向にあります。
ただし、試験に合格しただけでは即戦力とはならないため、合格後も継続的な学習が不可欠です。
複数の都道府県を併願できる?
登録販売者試験は、制度上は複数の都道府県で受験できます。ただし、試験日程が重なっている地域も多く、実際に併願するには注意が必要です。
また、出題傾向や合格基準は各自治体で異なるため、事前に確認をしておく必要があります。各県ごとの傾向を把握するには、過去問を活用した事前の分析も欠かせません。
さらに、併願しても合格後は登録する都道府県を1つに絞らなくてはならないため、勤務予定地を想定したうえで受験計画を立てましょう。実務に直結する資格であることから、無理な併願よりも確実に合格できる地域に集中するのがおすすめです。
合格するには何時間勉強が必要?
登録販売者試験に合格するための学習時間は、一般的に300〜400時間といわれています。ただし、これは個人の学習スタイルや過去の知識量によって大きく異なります。医療や薬に関する基礎がある人は効率よく進められますが、初学者は基礎理解に時間がかかるでしょう。
また、仕事や家事の合間に学習をおこなう場合は、1日の確保時間に応じて数カ月から半年の学習期間を見積もるのが現実的です。時間よりも「毎日継続して取り組む姿勢」が最終的な合否を左右するといえます。
登録販売者試験の難易度や勉強方法について、さらに詳しく知りたい方は以下のコラムをぜひ参考にしてください。
登録販売者試験は難しいってホント?難易度からおすすめの勉強方法までを解説まとめ|登録販売者試験の合格ラインを理解し、確実な合格を目指そう
登録販売者試験に合格するためには、各都道府県の合格基準や過去の合格率を正確に把握しておくことが重要です。合格点の傾向や試験の難易度を理解することで、学習の方向性が明確になります。そのため、勉強時間の目安を知ったうえで、自分に適した学習計画を立てましょう。それが合格への第一歩となります。
試験対策でおすすめなのが、アポプラス株式会社が運営するAPC Learningの登録販売者試験対策講座です。薬剤師の村松早織先生による講義動画に加え、キャリアアドバイスなどのサポートも充実しており、業界でもトップクラスの低価格ながらも質の高い内容となっています。
また、登録販売者の転職・就職支援に特化した「アポプラス登販ナビ」のキャリアサポートは、資格を活かした転職におすすめです。業界に精通したキャリアアドバイザーが、希望条件に合った求人を紹介してくれるため、未経験者やブランクのある方も安心して仕事探しができます。
試験勉強と同時に、合格後のキャリアを見据えた準備を始めてみてはいかがでしょうか。
【新着】登録販売者のための業界コラム
- 2026年01月30日 登録販売者になるために必要な勉強時間は?働きながら合格できるスケジュールと効率化のコツ
- 2026年01月30日 ドラッグストアの人手不足?ドラッグストアで働く人が知っておくべき現場の実態と対策
- 2026年01月27日 登録販売者必見!疲労を感じるお客さまへのサプリの接客と受診勧奨
- 2026年01月09日 【現役ドラッグストア店長直伝】登録販売者が「辞めたい」と思わない3つのメンタル維持法(2026年対策付き)
- 2026年01月07日 2026年ドラッグストア業界の未来図|市場動向・M&A・登録販売者のキャリアと転職のポイント