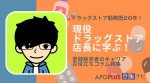【現役ドラッグストア店長直伝】高齢者対応で気をつけたい"いつもの薬"の落とし穴<登録販売者のキャリア>

日本の少子高齢化が叫ばれて久しいですが、皆さんの店舗の年齢層はどうでしょうか。 「午前中は特に高齢のお客さまがほとんど...」という店舗も多いのではないでしょうか?
高齢のお客さまが口にする「いつも飲んでいるから大丈夫」という言葉を鵜呑みにして販売していませんか?
一見安心なその言葉の裏には、実は登録販売者だからこそ気づけるリスクが潜んでいるのです。
今回は「いつもの薬」に潜むリスクを見抜く視点、お客さまの何気ない行動や会話から健康状態を読み解く観察力、そして信頼関係を築きながら自然な流れで受診勧奨につなげる会話術を具体的に解説します。
これらのスキルを学び、お客さまから「相談してよかった」と心から信頼される登録販売者を目指しましょう。
目次
- ●【現役店長が解説】登録販売者が高齢者対応でぶつかる「3つの壁」
- ●明日からすぐ使える!高齢者対応で本当に役立つ3つの実践スキル
- ●ただ聞くだけではない!高齢者の本音とリスクを引き出す質問のコツ
- ●まとめ:高齢者対応は登録販売者のキャリアを左右する必須スキル
【現役店長が解説】登録販売者が高齢者対応でぶつかる「3つの壁」

2025年現在、日本の65歳以上の人口は総人口の約3割に達すると推計されており、国民のおよそ3人に1人が高齢者となります。(内閣府「高齢社会白書」より)
小児や若年層の市販薬購入頻度を考えると、実際の店頭での高齢者対応はこの割合以上になると考えられるため、登録販売者にとって高齢のお客さま対応スキルは必須です。
その組み合わせは大丈夫?登録販売者が見抜くべき成分重複パターン
高齢のお客さま対応で一番よくあるのが「合剤リスク」です。
- 「抗コリン成分」が胃薬と鼻炎薬で重複
- 「解熱鎮痛成分」が鎮痛剤や風邪薬と湿布薬で重複
- 「カフェイン」が風邪薬と栄養ドリンクで重複
ご本人は気づかないまま成分を過剰に摂取してしまい、臓器に負担がかかるケースがあります。
高齢の方は「いつも飲んでいるから安心」と考えがちで、成分までチェックしている人はほとんどいません。
また、「痛み止めは痛み止め」「風邪薬は風邪薬」と名前や用途だけで判断している方も多いため、重複リスクはさらに高まります。
登録販売者の視点から「この薬とこの薬は成分が重複していますね」と見抜くことがとても重要です。
単剤で対応できる症状の場合は単剤を優先するといった判断も、登録販売者の大切なスキルと言えるでしょう。
病院とドラッグストアの「見えない壁」医師が知らない市販薬・サプリの存在
「他に薬は飲んでない」と答えるお客さまの買い物カゴに、サプリや健康食品が入っている...。
その「薬ではない」というお客さまの思い込みに、重大なリスクが潜んでいる可能性を考えたことはありますか?
高齢のお客さまへの対応でもうひとつ大きな壁になるのが「情報が医療機関に届かない」ことです。
接客の機会に伺うとわかりますが、市販薬やサプリメントを日常的に飲んでいても、それを主治医や薬剤師に伝えていない方は本当に多いのです。
実際には処方薬と成分が重なるケースもあり、作用が強まったり弱まったりして思わぬ健康被害を招くこともあるのです。
市販薬でも「風邪薬くらい」「いつものだから大丈夫」という感覚で使い続けている方も多く、その結果、診察や検査の結果、あるいは治療や薬の調整に支障をきたす場合も少なくありません。
こうした情報の断絶が起こると「処方薬・市販薬・サプリメント」が複雑に重なり合い、リスクはさらに高まってしまいます。
だからこそ登録販売者は、お客さまが購入した市販薬やサプリは医療機関に伝わっていない可能性がある...という前提で接客することが必要となります。
「昔から飲んでるから大丈夫」という自己判断に潜む正常バイアスの罠
高齢のお客さま対応で最もハードルが高いのが「自己判断によるリスクの過小評価」です。
ここには大きく2つの思考があります。
- 昔から飲んでいるから大丈夫
- 自分の持病とは関係ない
実際にはリスクがある薬でも気にせず選んでしまうのです。
自分に都合の悪い情報を無意識に無視してしまうこの心理を「正常バイアス」と呼びます。
これは高齢者に限った話ではなく、人間なら誰にでも大なり小なり存在する「思考のクセ」なのです。
そしてもっと厄介なのは、持病そのものを隠して市販薬を買おうとするお客さまです。
「病院に行けと言われたくない」「問診のようなものが面倒」「ほしい薬を買わせてもらえない」という心理で、隠してしまうケースも考えられます。
明日からすぐ使える!高齢者対応で本当に役立つ3つの実践スキル

では具体的に高齢のお客さまへの対応策を順に考えていきましょう。
今までの接客内容と比較し、とり入れられるものは実行してみてください。
成分の重複を判断する力
現場でできる具体的な対策を整理してみましょう。
ここで大切なのは、お客さまが気づかない成分の重なりを登録販売者がチェックするということです。
まず必須なのは接客のさいに購入しようとしている商品のパッケージ裏を一緒に確認することです。
医薬品の名前や効能だけで判断せずにリスクを具体的に伝えましょう。
「同じ成分が入っているので一緒に使えません」
成分は違いますが同じグループの成分で同時使用ができない薬です」
次に大切なのは販売フローの工夫です。
レジで複数の市販薬を一度に購入する場合、非資格者がそのまま会計するのではなくできるだけ登録販売者が最終確認を行うルールを設けると安心です。
高齢のお客さまは代謝機能や臓器の働きが弱っているため、同じ量でも副作用が出やすいので資格者が確認すべきです。
未然に防げる健康被害を自店から出さないという強い意識が求められます。
サプリや健康食品の健康被害を見抜く力
高齢のお客さま対応で見落とされがちなのが、サプリや健康食品の存在です。
医薬品と違って「薬ではない」と思い込んでいる方が多く、主治医に報告していなかったり、薬剤師や登録販売者に伝えないことが少なくありません。
厚生労働省も健康食品と医薬品の併用による健康被害のリスクについて注意喚起しています。
特に、特定の成分が処方薬の効果を弱めたり、逆に作用を強めて副作用を招いたりするケースが報告されています。
出典:厚生労働省「健康食品」
サプリや健康食品は医薬品と同じように体に作用し、時には重大な副作用や飲み合わせのリスクを引き起こすことがありますし、受診や検査のときに悪影響を及ぼす場合もあるでしょう。
また、医薬品医療機器総合機構(PMDA)によれば、一般用医薬品であっても副作用のリスクはあり、特に高齢者は生理機能の低下から副作用が出やすい傾向にあるとされています。
出典:厚生労働省「高齢者の医薬品適正使用の指針」
このリスクは、サプリや健康食品との予期せぬ相互作用によって、さらに高まる可能性があります。
これらは医療現場でも問題視されており、登録販売者にとっても無視できないポイントです。
だからこそ「病院のお薬以外にいつも飲んでいる市販薬やサプリはありますか?」という一言が、お客さまから重要な情報を引き出すカギになります。
そもそも、ご本人がサプリメントや健康食品を医療機関へ申告する必要があると思っていないケースも珍しくありません。
特に高齢者は「薬ではないから関係ない」と思って口にしないことが多いため、最初からこちらが問いかけてあげることが大切です。
ここでは「いつも飲んでいるものがあれば教えてくださいね」と柔らかく伝えるのが効果的です。
また、話を遮らずに最後まで聞く姿勢を見せると、お客さまも安心して情報を出してくれるようになります。
そしてサプリや健康食品は医薬品ほど厳しい規制を受けていないため、成分量や品質にもばらつきがあることも事実です。
だからこそ「薬ではないから安全」と思い込んでいる高齢者に対しては登録販売者がリスクを見抜き、必要に応じて受診や薬剤師への相談を勧めることが重要です。
行動から見えるリスクを予測する力
登録販売者にとって高齢のお客さま対応で重要なのは「行動からリスクを読み取る力」です。
高齢者は体の機能や判断力が若い人と違うため副作用や飲み間違いのリスクが高く、言葉では伝わらないサインを見逃さない観察力が必要となります。
たとえば買い物中に棚やカートに頻繁につかまっている方は、ふらつきや転倒の可能性があるため転倒リスクを高める薬などに注意が必要です。
ふらつきや転倒のリスクがある方に特に注意したいのが「抗コリン作用」のある薬です。
この作用は、めまいやせん妄、認知機能低下などの副作用を引き起こす可能性があり、総合感冒薬・胃腸薬・鼻炎薬など、高齢者に需要が高い多くの市販薬に含まれています。
そしてパッケージの文字は小さいため服用量を誤る危険がありますし、同じ便秘薬や睡眠薬を繰り返し購入する方は症状が長引いていたり薬に依存している可能性もあります。
接客で高齢のお客さまから「なんとなく調子が悪い」「年だから仕方ない」と曖昧に表現することも多いですが、その陰に副作用や病気が隠れていることがあります。
また、他に購入する商品でお酒が含まれている場合も注意が必要です。
飲酒と薬の相性が悪いのはご存じだと思いますが、とくに高齢となると臓器の機能が弱まっている場合が多いため、健康被害のリスクが上がります。
レジでは「複数・リスクが高い市販薬」「アルコール・サプリメントと医薬品の同時購入」には特に注意して接客をおこなってください。
ただ聞くだけではない!高齢者の本音とリスクを引き出す質問のコツ

私たちも「いつもの行動」には注意が及ばないことはありますが、高齢になるとその傾向がより顕著になります。
ドラッグストアではよくある場面ですが、高齢のお客さまから「いつも使っている」「昔から使っている」と言われたときの対応方法を考えてみましょう。
「いつもの薬」に潜む危険性とは
高齢のお客さまからよく出てくる「いつも飲んでいる」という言葉に、対応を迷わされている登録販売者も多いはずです。
こうした言葉には誤解や副作用のリスクが隠れていることがあり、わたし達が安易な販売をしてしまうと、お客さまの健康を害するきっかけになりかねません。
たとえば「昔から飲んでいるから大丈夫」「自分に合っているから」という言葉はよく聞きますが、人間は加齢にともなって体質が変化し、新たな持病が現れることもあります。 10年前や20年前と現在では体調や体質は変わっていると考えるべきですし、もし連用しているのなら、疾病の見逃しや長期連用による依存なども考慮に入れなくてはなりません。
「長期間使用している=安全で自分に合っている」
これは一概に間違いではありませんが、それよりも大きなリスクが潜んでいる可能性があります。
高齢のお客さまに限らず人間は「正常バイアス」が働き、自身の経験が正しいものと思い込みがちです。そのため、使い続けている市販薬の選択に疑いを持っていないことが多いのです。
その市販薬を否定せず「長く使っていらっしゃるんですね」「他のお客さまにも人気なんですよ」などと緩衝的な言葉で距離感を縮めてからアドバイスするのが効果的です。
「実はこのお薬、〇〇と一緒には使えないんですよ」
「もし、〇〇という症状が出ていたら、この薬の副作用かもしれません」
少なくともリスクの存在を優しく伝えることが重要です。
家族の方が購入に来た時も同じような対応で本人に伝えるようアドバイスしてください。
安心される受診勧奨方法を覚えておこう
高齢のお客さま対応で難しいのが「受診勧奨」です。
登録販売者として市販薬では対応が難しいと判断したり長期的な症状と判断しても、実際に受診をお勧めするとさまざまな理由で拒まれるケースも多くあります。
ここで強い言い方をすると反発され、クレームに発展することもあります。
そのため、安心して受け入れてもらえるような言い回しを覚えておくことが大切です。
まず大切なポイントは「否定ではなく共感から入る」ことです。
例えば「このお薬を試してみるのも良いと思いますが...」と一度お客さまの希望を受け止めてから「ただ症状が長引いているようなので、一度病院で診てもらうと、より安心ですよ」と続けると受け入れられやすくなります。
次に、受診による「具体的なメリットを伝える」ことです。
「病院で検査をすれば原因がはっきりするので、同じ症状を繰り返さなくて済みますよ」といった前向きな説明は、お客さまに行動するきっかけを与えます。
不安を煽るのではなく、「楽になる」「安心できる」といったプラスのイメージを持ってもらうことがポイントです。
また「言葉を柔らかくする工夫」も必要です。
「病院に行ってください」より「一度診てもらうと安心ですね」「不安を念のため先生にご相談されると、さらに安心だと思いますよ」といった表現の方が角が立ちません。
特に高齢者は「命令口調」を嫌う傾向があるため、提案型の伝え方を意識しましょう。
さらに、受診勧奨のタイミングも大切です。
お会計の直前などに突然切り出すのではなく、会話の中で「もし続くようなら...」と自然に織り込むことで抵抗感が減ります。
必要に応じて「お薬手帳に今日のお話を書いておきますね」と情報共有を提案すると、医師との連携にもつながります。
登録販売者の受診勧奨は「拒絶」ではなく「安心への橋渡し」です。お客さまの体調を守る最後の砦として、やわらかく、そして確実に伝えるスキルを磨いていきましょう。
まとめ:高齢者対応は登録販売者のキャリアを左右する必須スキル
これからの登録販売者にとって、ますます重要になるのが「高齢者対応力」です。今回のポイントを振り返ってみましょう。
・合剤リスク
一見違う薬(例:頭痛薬と風邪薬)でも、有効成分が重複するリスクがあります。
お客さまと一緒にパッケージ裏を確認し、具体的に伝えることが重要です。
・情報の断絶
市販薬やサプリの使用をご本人が「薬ではない」と思い込み、主治医に伝えていないケースは後を絶ちません。
店頭に立つ登録販売者こそが、そのリスクに気づける最初の専門家かもしれません。
・正常バイアス
「昔から大丈夫」という思い込みは、加齢による体調の変化を見過ごす原因になります。
丁寧な対話で現状を掘り下げることが求められます。
これから必要性が増す「高齢者対応」を磨くために、今回のポイントを必ず抑えておきましょう!

執筆者:ケイタ店長(登録販売者)
ドラッグストア勤務歴20年、一部上場企業2社で合計15年の店長経験を活かし、X(旧Twitter)などで登録販売者へのアドバイスや一般の方への生活改善情報の発信を行っている。X(旧Twitter)フォロワー数約5,000人。
【新着】登録販売者のための業界コラム
- 2026年01月09日 【現役ドラッグストア店長直伝】登録販売者が「辞めたい」と思わない3つのメンタル維持法(2026年対策付き)
- 2026年01月07日 2026年ドラッグストア業界の未来図|市場動向・M&A・登録販売者のキャリアと転職のポイント
- 2026年01月07日 登録販売者の年収は低い?現場にインタビューしてリアルな声をお届け!平均給料を調査
- 2026年01月07日 ドラッグストア店長の年収はいくら?平均額の内訳と600万円を目指す昇給のコツ
- 2025年12月03日 【現役ドラッグストア店長直伝】冬商品で接客スキルを劇的に磨く3つのコツ