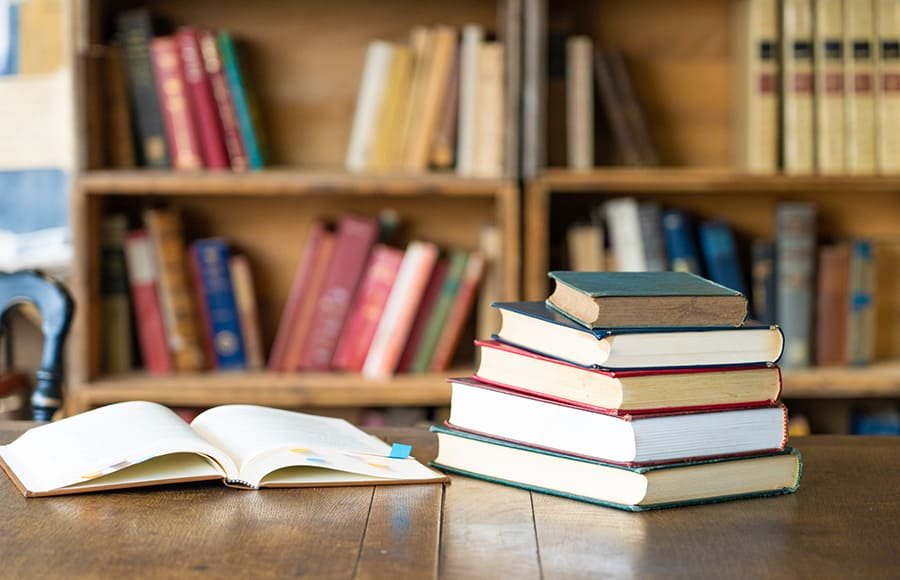登録販売者試験は他県でも受験可能|併願時の注意点を解説

こんにちは、登録販売者転職のアポプラス登販ナビライターチームです。
登録販売者試験は各都道府県で実施され、試験の日程は都道府県によって異なります。そのため、登録販売者試験を受験予定の方の中には、「滑り止めとして他の県の試験を受けてもいいの?」と疑問に思っている方もいるでしょう。
登録販売者試験は、受験する都道府県にこだわる必要はなく、居住地以外の都道府県で受験することが可能です。また、併願受験を活用すると、合格のチャンスを増やせます。この記事では、他県(他ブロック)で試験を受けるメリットや注意点、併願受験のコツなどを解説します。
目次
- ・登録販売者試験の基本と受験地域のルール
- ・他県(他ブロック)での受験や併願するメリット
- ・合格率で受験地(受験ブロック)を選ぶべき?
- ・他県(他ブロック)受験・併願の注意点
- ・他県(他ブロック)で合格した場合の登録手続き
- ・まとめ|登録販売者試験を併願して合格を確実にしよう
登録販売者試験の基本と受験地域のルール

登録販売者試験は、都道府県ごとに実施され、受験する地域を自由に選べます。
ここからは、登録販売者試験を受験する際に知っておきたい基本情報や地域ごとのルールについて詳しく解説します。試験日や受験条件に地域差があるため、試験準備を進める前に必要な情報を得ておきましょう。
試験はどこで受けてもよい
登録販売者試験は、各都道府県で実施されており、原則としてどの県でも受験できます。試験の実施日は都道府県ごとに異なるため、複数の県で試験を受けることも可能です。
複数県で受験することにより、合格の可能性を高められます。たとえば、都道府県ごとに合格率が異なるため、試験が実施される地域を選ぶことで、少しでも有利に進められるでしょう。
厚生労働省のデータによると、東京都の合格率は33.0%、北海道は47.4%といったように、地域によって大きな差が見られます。
併願受験も可能
登録販売者試験の特徴の一つは、併願受験が可能な点です。併願受験とは、試験日が異なる地域で同じ年に複数回試験を受ける方法です。
全国一斉におこなわれないため、地元の試験日と異なる日程で試験が実施される地域で試験を受けられ、その分合格のチャンスを増やせます。このため、他の資格試験に比べて「合格しやすい資格」として人気があります。
ただし、同じ地域の試験日が重なっていると、併願受験はできません。たとえば、群馬県で受験する場合、近隣の長野県や新潟県は同じ関東・甲信越ブロックに属しているため、試験日が重なってしまいます。
そのため、併願受験を希望する場合は、異なるブロックの県を選ぶ必要があります。移動時間や交通費の面から考えると、できるだけ地元の県から近く、かつ試験日が異なるブロックの県を選ぶと、効率的に受験できるでしょう。
他県(他ブロック)での受験や併願するメリット

他県(他ブロック)での受験や併願受験のメリットは、受験機会の増加や柔軟なスケジュール調整にあります。試験日程の違いや地域間の差を活かして、合格を確実にするための戦略として有効です。
ここからは、その利点について詳しく見ていきます。
試験日程の分散によりチャンスが増える
登録販売者試験は、都道府県ごとに試験日程が異なるため、複数の県で併願して受験することで、試験のチャンスが増えます。たとえば、ある都道府県で試験日に都合がつかなくても、別の県で受験できる可能性があります。
これにより、試験のスケジュールに柔軟性が生まれ、受験のチャンスを逃すことが少なくなるでしょう。
スケジュールの調整がしやすい
確実に合格したい人にとって、試験日程を調整できるというのは大きなメリットです。複数の県で受験を検討することで、都合のよい日程を選べ、試験準備に集中しやすくなります。
とくに、仕事や家庭の事情で忙しい人にとって、受験日を自分のライフスタイルに合わせられることは、ストレスの軽減にもつながります。また、もし1回目の試験で思うように結果が出なかった場合でも、別の日程の試験を受けることで、再挑戦の機会を確保できるでしょう。
地元と別地域の両方での就業を想定できる
他県で登録販売者試験を受けることによって、試験合格後は地元に限らず、別の地域での就業機会にも目を向けられます。もし、地元での就業先が見つからない場合でも、別の地域で働く可能性を事前に視野に入れることが可能になります。
そうすると就業先の選択肢が増え、万が一地元での求人が見つからなくても、他県での就業をスムーズに選べるようになるでしょう。
他県での受験や併願のメリットを十分に活かすためには、効率よく学習を進め、準備を万全にすることが重要です。APC Learningの登録販売者試験対策講座は、業界でもトップクラスの低価格ながらも質の高い内容となっています。薬剤師の村松早織先生による講義動画に加え、キャリアアドバイスなども充実しているので、ぜひチェックしてみてください。
APC Learning
合格率で受験地(受験ブロック)を選ぶべき?

地域ごとの合格率は、受験地選びの参考になりますが、合格を確実にするためには他にも考慮すべき要素があります。合格率に一喜一憂せず、自分に合った受験スケジュールを優先することが重要です。
ここからは、合格率と受験地選びに関する注意点を説明します。
「合格率が高い県で受ければ受かりやすい」について
一部の受験者の間では、「〇〇県は合格率が高いから受かりやすく狙い目」という声が聞かれます。しかし実際には、その年ごとに試験の難易度や受験者層が大きく変動するため、単純に合格率が高い県を選ぶだけで確実に合格できるとは限りません。
たとえば、ある年に合格率が高かった県でも、翌年は試験の内容や出題傾向が異なり、難易度があがることも考えられます。また、各都道府県の合格率はさまざまな要因に影響されるため、合格率の高い県を選んだとしても、それが必ずしも自分にとって有利な選択とはいえません。
合格率が高く見える理由の一例
合格率が高く見える理由の一つには、その地域の試験日が最後のブロックである場合があげられます。他県での試験後に出題傾向を十分に勉強した受験者や、すでに他県で受験経験を積んだ「2回目受験」の人たちが集中します。
試験に臨む受験者の多くが経験者となり、試験問題に対する理解度が高くなった結果、試験に合格する人が多くなり、合格率が相対的に高く見えるわけです。これは決して問題が簡単なわけではなく、むしろ経験者が多いことが要因となっているため、過信せず準備を進める必要があるでしょう。
数字に惑わされず自分に合ったスケジュールを重視しよう
合格率はあくまで目安に過ぎないことを認識しましょう。どの県で受験するかを決める際に、合格率を参考にするのは一つの手段かもしれませんが、それだけに頼ってスケジュールを決めることは避けるべきでしょう。
重要なのは、自分の生活リズムや試験準備に適したスケジュールを優先することです。合格率に惑わされず、自分の状況に合わせた試験スケジュールを立て、着実に準備を進めることが大切です。
他県(他ブロック)受験・併願の注意点

他県での受験を計画する際には、申し込み期限や試験要項など、地域ごとの異なるルールに注意が必要です。受験手続きや交通手段をしっかり準備し、スムーズに受験できるようにしましょう。
ここからは、試験を他県で受ける際の注意点について解説します。
試験要項・申し込み期限・会場確認はそれぞれの自治体でおこなう
他県で登録販売者試験を受験する際は、各都道府県の試験要項を確認することが重要です。試験申し込み手続きは自治体ごとに異なるため、公式ホームページで最新情報をチェックしましょう。
試験申し込みの流れは以下の通りです。
- 受験申請書の入手:地元の保健福祉事務所や健康福祉センターで入手、または郵送で取り寄せ可能です。配布時期が異なるため、期限内に入手しましょう。
- 申請書の提出:必要事項を記入し、必要書類を添えて提出します。直接持参が原則ですが、郵送受付できる場合もあります。
- 受験票の受け取り:申請後、手元に受験票が郵送されます。試験当日に必ず持参しましょう。
- 試験当日:受験票を持参し、試験会場で受付します。
試験日が被らないかを事前に確認をしておく
複数の県で受験を予定している場合、試験日が重ならないか、試験の申し込み期限に間に合うかなどを十分に確認することが大切です。
とくに他県で受験する際、移動日や試験日が重なると受験が困難になる場合があります。併願受験を希望する場合、都道府県ごとの試験日程が異なるかどうかを事前にチェックし、スケジュールを調整しましょう。
受験会場への交通・宿泊の準備も忘れずに
他県で受験する場合、試験会場への交通手段や宿泊の手配も重要なポイントです。
とくに遠方の会場を選んだ場合であれば、交通費がかさむことも考えられます。公共交通機関や自家用車での移動費用を予算に組み込み、必要に応じて宿泊を手配することが求められます。
試験会場が交通アクセスの悪い場所にある場合は、前日から宿泊することも考慮すべきです。宿泊施設は、ホテルやビジネスホテル、民泊などが選べるため、自分の予算に合わせて手配しておきましょう。
試験ごとに受験料が必要となる
受験料は都道府県によって異なり、一般的に12,800円から18,200円の間で設定されています。支払い方法としては、収入証紙を申請書に貼り付けるのが主流です。
収入証紙は郵便局や法務局で購入でき、これが税金を支払った証明となります。地域によっては、クレジットカードやペイジー(Pay-Easy)、銀行振込で支払える場合もあるため、支払い方法を事前に確認しておきましょう。
受験料は必ず期限内に支払いを完了させ、証明書など必要な書類も適切に準備しましょう。
他県(他ブロック)で合格した場合の登録手続き

試験に合格した後は、登録手続きが必要です。他県で登録販売者試験に合格した場合の登録手続きについて、注意点と必要書類を解説します。
合格後の手続きをスムーズに進めるために、事前に準備を整えておきましょう。
合格証は「合格した県」から発行される
登録販売者試験に合格すると、合格証が「合格した県」から郵送されてきます。この合格証は、後の登録販売者としての従事登録に必要な重要な書類となるため、大切に保管しましょう。
合格通知は、受験申し込み時に記載した住所に届くため、引っ越し等で住所が変わる場合は、必ず転送手続きをおこなってください。受験後の住所変更ができない場合もあるため、注意しておきましょう。
登録は「実際に働く予定の都道府県」でおこなう
試験に合格しても、実際に登録販売者として働くためには、所定の登録手続きが必要です。複数の都道府県で試験に合格した場合でも、勤務先が所在する都道府県で登録手続きをおこなわなければなりません。
登録手続きの際には、必要書類や提出方法が都道府県ごとに異なるため、各都道府県の担当窓口で確認し、手続きを進めましょう。また、登録証の交付には約2週間から1カ月程度かかる場合が多いため、余裕を持って手続きをおこなうことをおすすめします。
登録手続きに必要な書類
登録販売者としての従事登録をおこなうには、書類や手数料が必要となります。具体的にどの書類が必要か、またその入手方法や費用についても事前に確認しておくことが重要です。
多くの場合、勤務先の都道府県のホームページで必要書類や申請方法を確認できるため、事前に準備を整えておくとスムーズに進められます。
必要な書類は、販売従事登録申請書、合格証の原本、本籍の記載された書類、医師の診断書(該当者のみ)、雇用関係を示す書類、そして登録手数料などです。
ただし、各都道府県の担当部署により異なる場合があるため、しっかりと確認してから準備を進めましょう。
必要書類について詳しく知りたい方は、以下のコラムも参考にしてください。
「登録販売者販売従事登録」に必要な書類や注意点とは
まとめ|登録販売者試験を併願して合格を確実にしよう
登録販売者試験は、他県で受験したり、併願受験したりすることで、合格のチャンスを増やせます。試験日程や合格率、受験地の選び方を工夫することで、効率的に試験を進められるでしょう。
受験要項や申し込み期限、受験料などをしっかり確認し、準備を整えることが大切です。
【新着】登録販売者のための業界コラム
- 2025年12月03日 【現役ドラッグストア店長直伝】冬商品で接客スキルを劇的に磨く3つのコツ
- 2025年11月21日 現役薬剤師が教える。登録販売者の新人教育マニュアル|OJTの進め方と後輩指導のコツ
- 2025年11月21日 現役薬剤師が伝授|インフルエンザ時に使える解熱剤の見分け方と登録販売者の声かけ技術
- 2025年11月06日 【2026年法改正で必須!】現役店長が教える「OD対策」現場対応完全ガイド 〜登録販売者が押さえるべき「3大変更点」と心構え〜<登録販売者のキャリア>
- 2025年10月30日 登録販売者はブランク後も復職できる!管理者要件と安心して働くためのポイント